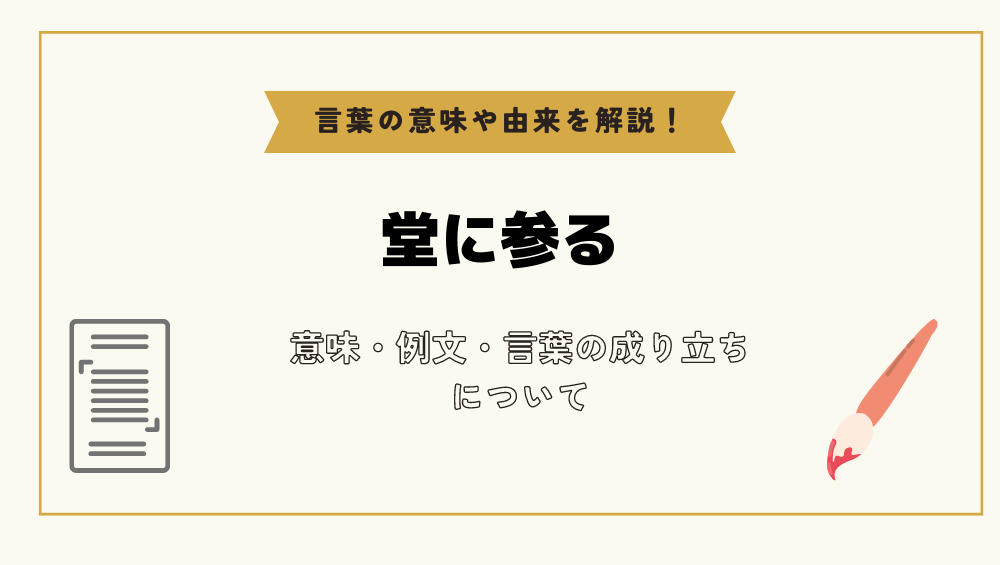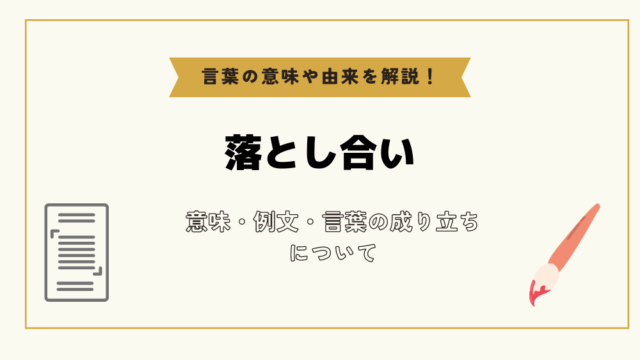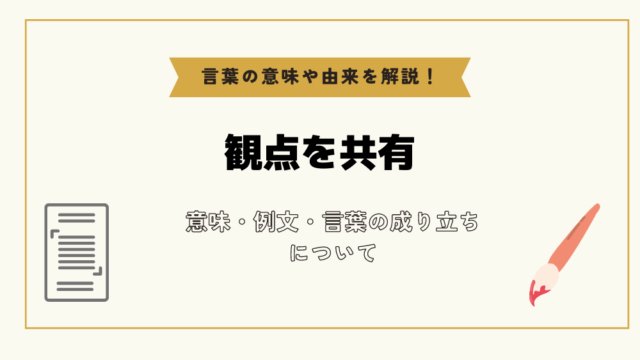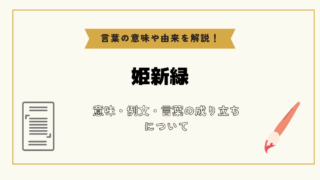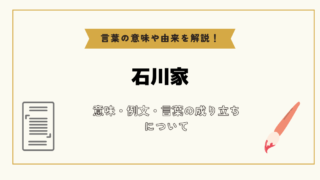Contents
「堂に参る」という言葉の意味を解説!
「堂に参る」という言葉は、お寺や神社などの宗教施設にお参りすることを指す表現です。
具体的には、厳かな雰囲気の中で祈りを捧げ、信仰心を持って巡礼することを指します。
この言葉は、日本の伝統文化や宗教に根付いており、特に仏教関連の施設に参ることを表す際に用いられます。
「堂に参る」の読み方はなんと読む?
「堂に参る」は、「どうにまいる」と読みます。
この表現は、古文や和歌などの古典的な文献でよく見られる形式です。
しかし、現代の会話や文章でも理解されることが多く、その意味も広く認知されています。
「堂に参る」という言葉の使い方や例文を解説!
「堂に参る」という表現は、主に宗教的な行為や場面で使用されます。
例えば、「お寺に堂に参る」という風に使います。
また、仏教の寺院や神社を訪れ、心を静めながら祈りを捧げる行為を指すことが一般的です。
例文として、「先日、友人と一緒に有名なお寺に堂に参りました。
心を清めるために、お願い事をしながら静かに鐘をつきました。
」というように使うことができます。
「堂に参る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「堂に参る」という表現は、仏教の影響を受けた日本の宗教文化に由来しています。
かつて、人々はお寺や神社などの宗教施設を訪れ、心を静めながら祈りを捧げることで、幸福や救いを求めました。
そのため、「堂に参る」という表現が生まれ、広まっていったのです。
「堂に参る」という言葉の歴史
「堂に参る」という表現の歴史は古く、平安時代や鎌倉時代から見られます。
当時の貴族や武士たちは、人生の節目や特別な場面でお寺や神社に堂に参り、信仰心を示すことが一般的でした。
その後も、現代に至るまで宗教的な行為や伝統行事で用いられ、日本の文化の一部として息づいています。
「堂に参る」という言葉についてまとめ
「堂に参る」という表現は、お寺や神社などの宗教施設にお参りすることを指す言葉です。
古くから日本の宗教文化に根付いており、心を静めながら祈りを捧げる行為を表します。
伝統的な文化や歴史とともに、今もなお日本人にとって大切な言葉となっています。