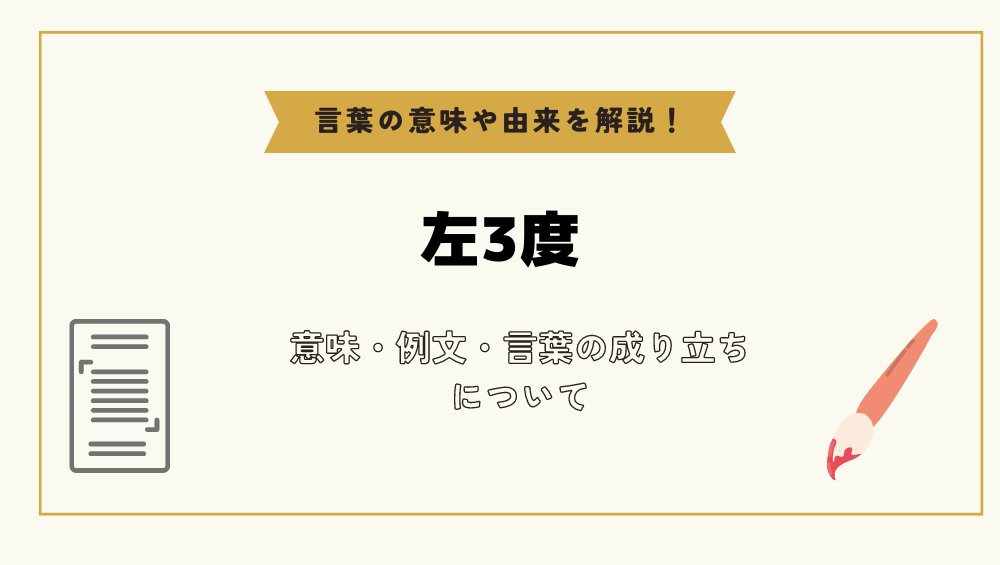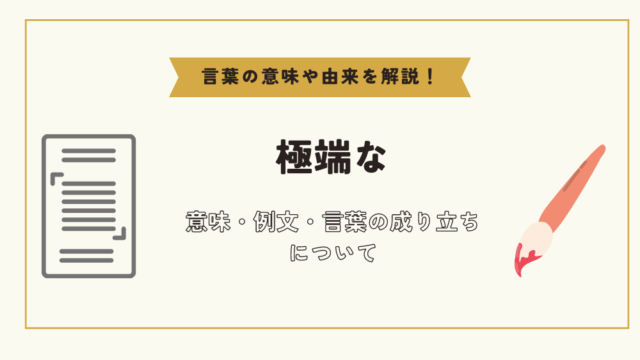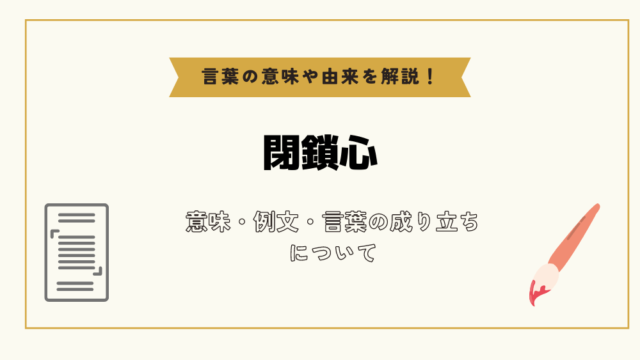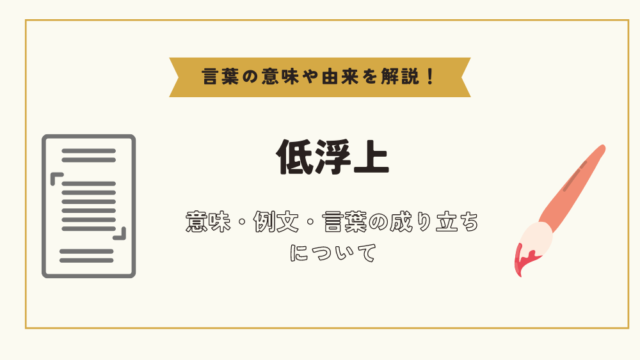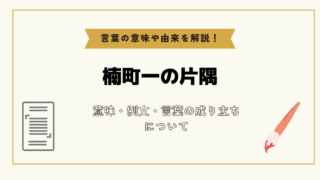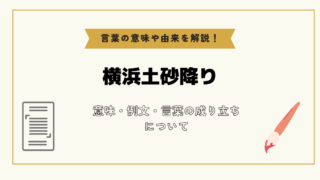Contents
「左3度」という言葉の意味を解説!
「左3度」という言葉は、日本の伝統音楽で使用される基本的な音程のひとつを表す言葉です。音程とは、音の高さや関係性を表すものであり、音楽を奏でる上で重要な概念です。左3度は、音楽理論の中で一般的に使用されており、多くの曲で使われることがあります。
具体的には、左3度は半音の距離を意味します。これは、ピアノの鍵盤で表すと、隣り合う2つの鍵を一つ飛ばした音程になります。左3度の音程は、高さや関係性において個性的な響きを持っており、曲によっては感情表現やメロディの特徴となることもあります。
「左3度」の読み方はなんと読む?
「左3度」の読み方は、「ひだりさんど」となります。日本語の読み方であり、音楽関連の言葉として広く使われています。左3度という表現は、音楽の世界で使われることが多いですが、一般的な会話でも使用されることがあります。
「左3度」という言葉の使い方や例文を解説!
「左3度」という言葉は、日本の伝統音楽や音楽理論の専門的な文脈でよく使用されます。例えば、「この曲は左3度の音程が特徴的なメロディを持っている」とか、「この楽譜では左3度を強調する指示があります」と言った具体的な使い方があります。
また、「左3度」は単独で使われることもあります。例えば、「左3度を使うことで、音楽に深みや複雑さを与えることができます」とか、「左3度の効果を生かして、感情表現を豊かにすることができます」といった表現です。
「左3度」という言葉の成り立ちや由来について解説
「左3度」という言葉の成り立ちは、音楽理論の文脈で生まれたものです。左3度の音程は、西洋音楽においては「大短3度」と呼ばれることもありますが、日本の伝統音楽や民謡においては、「左3度」という呼び方が一般的です。
この呼び方の由来は明確ではありませんが、日本の伝統音楽では他の国の音楽と異なる特徴があり、それが命名の一因になっている可能性があります。
「左3度」という言葉の歴史
「左3度」という言葉は、日本の伝統音楽において長い歴史を持っています。伝統的な楽曲や舞踊には、左3度がよく使用されており、これらの作品は多くの人々に愛されています。
また、左3度は現代の作曲家や演奏家によっても活用されています。彼らは伝統的な要素を継承しながらも、新たな音楽の形を創造しています。
「左3度」という言葉についてまとめ
「左3度」という言葉は、日本の伝統音楽や音楽理論において重要な役割を果たしています。音楽の世界ではその特徴的な音程を活用し、感情表現やメロディの魅力を引き出すことができます。
「左3度」の言葉の由来や歴史は、日本の豊かな音楽文化と深く関わっています。今後も「左3度」を通して、素晴らしい音楽が生み出されることを期待しています。