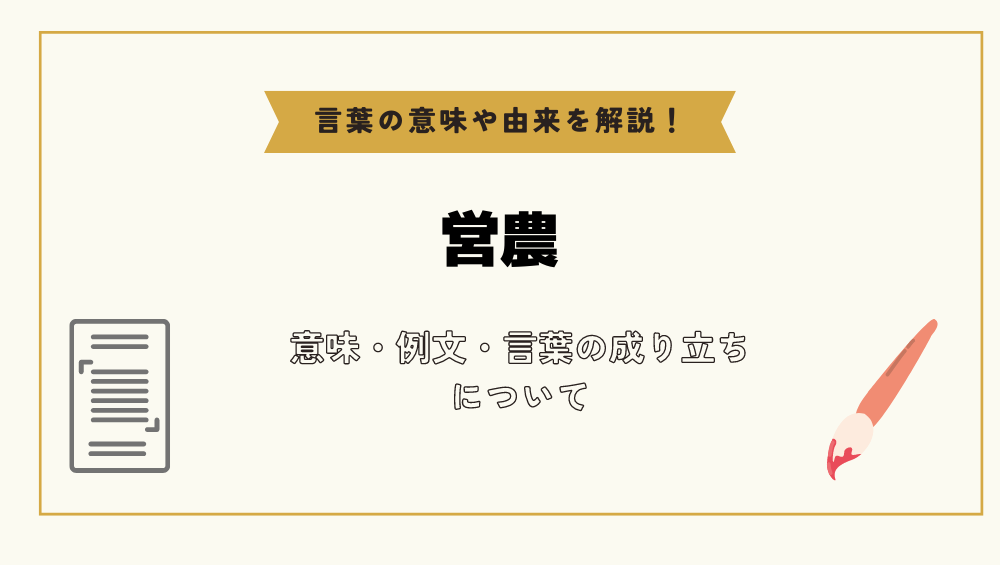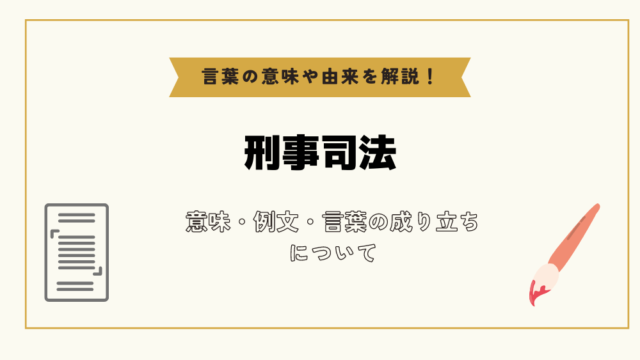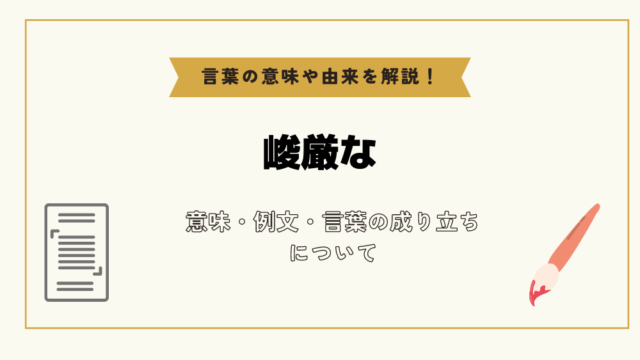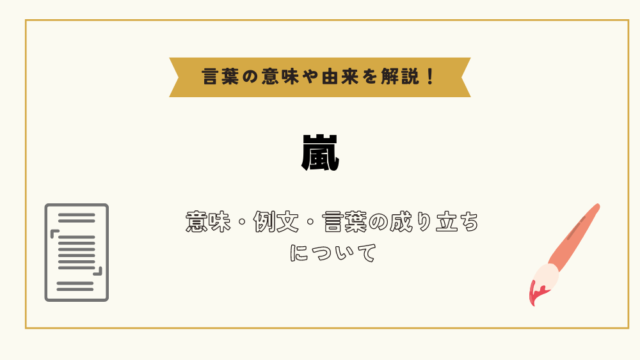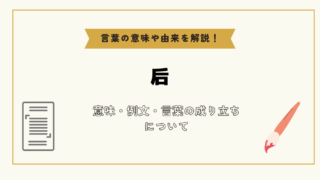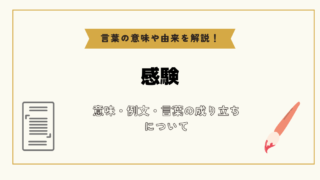Contents
「営農」という言葉の意味を解説!
「営農」という言葉は、農業を行いながら経済的な目的を持って取り組むことを指します。
つまり、農地や畑で農作物を栽培し、それを経済的な利益を求めるために販売したり利用したりすることです。
農業を営むことを「営農」と呼ぶのです。
「営農」は、農業を生業として取り組む人々にとって重要な語彙です。
農業には様々な手法や知識が必要であり、それを用いて効果的に農作物を生産し、市場で需要に応じた販売をすることが望まれます。
「営農」という言葉の読み方はなんと読む?
「営農」という言葉は、”えいのう”と読みます。
“えい”は「経営」の「経」と同じ読み方で、”のう”は「農業」の「農」と同じ読み方です。
「営農」という言葉の使い方や例文を解説!
「営農」という言葉は、農業において経済的な目的を持って取り組むときに使用されます。
例えば、「彼は農地を借りて営農している」といった表現があります。
また、「営農」という言葉は農業における経営的な要素を意味し、効率的な生産や収益性を追求することも含まれます。
例えば、「この地域では新しい技術を取り入れた営農が注目されている」といった使い方があります。
「営農」という言葉の成り立ちや由来について解説
「営農」という言葉は、日本語の古典的な表現から派生しました。
元々は「農耕を営む」という意味で使用されていましたが、時代の変化とともに経営的な要素を強調する意味合いを持つようになりました。
現代の農業は、単に農作物を育てるだけではなく、市場調査や販路確保、効率的な生産管理など経営的な側面も重要になっています。
そのため、「営農」という言葉が使われるようになったのです。
「営農」という言葉の歴史
「営農」という言葉の歴史は古く、日本の歴史とも深く関わっています。
古代から中世にかけて、地域ごとに営まれる農業は自給自足の範囲に留まっていました。
しかし、近代化の波が押し寄せるにつれて、農業は産業化・商品化されていきました。
その結果、「営農」という言葉も現代で使われるようになり、農業経営の意味合いが広まりました。
「営農」という言葉についてまとめ
「営農」という言葉は、農業を経済的な目的を持って行うことを指します。
農業においては効率的な経営・生産が求められるため、「営農」という言葉が使われます。
読み方は”えいのう”です。
日本の農業は長い歴史を持ち、近代化に伴って農業経営の重要性が高まってきました。
農業を営む人々にとって、経営的な目標を持ち、効果的に取り組むことが求められています。