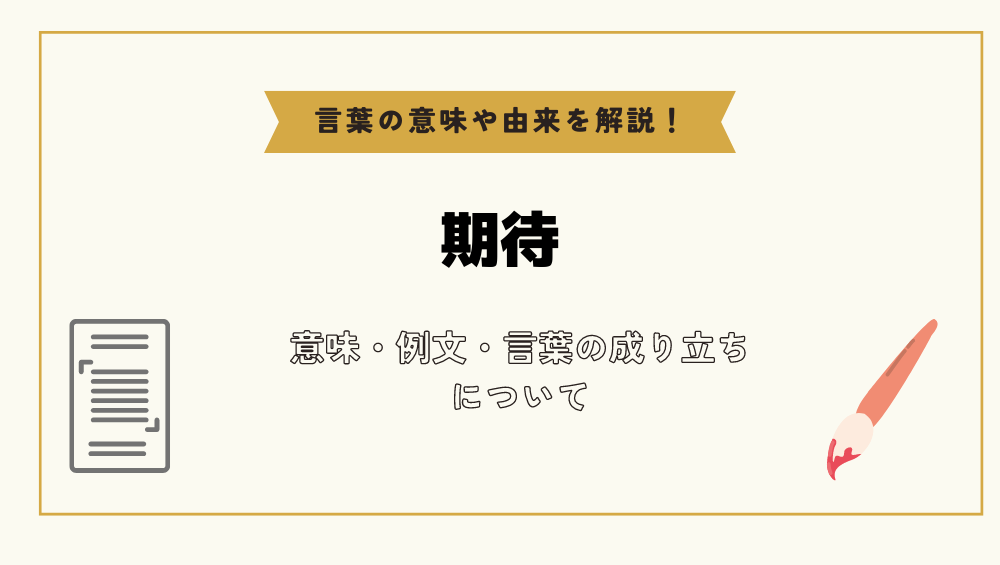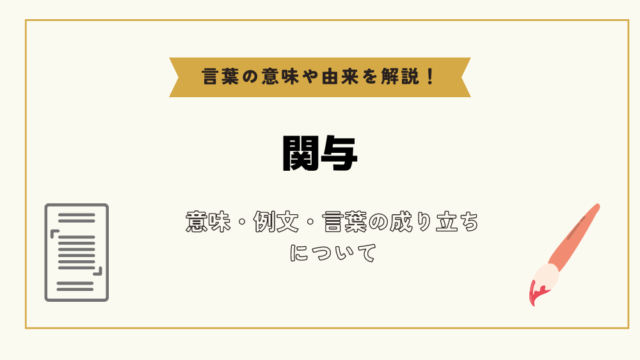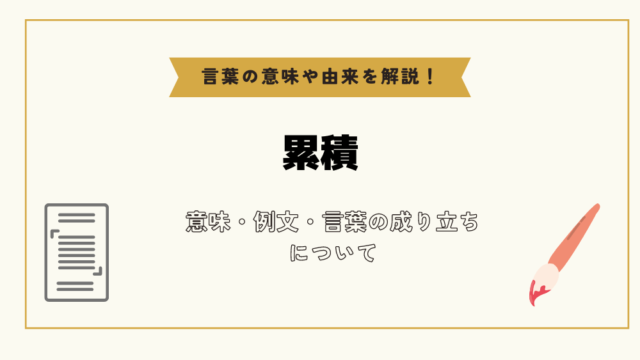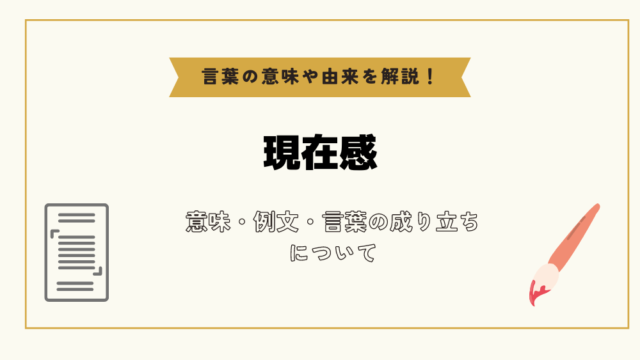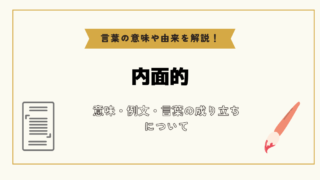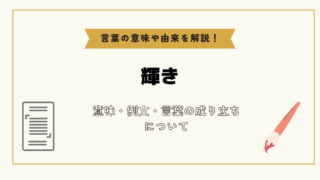「期待」という言葉の意味を解説!
「期待」とは、これから起こる出来事や人の行動に対して、良い結果や望ましい状態を心の中で待ち望む心理的な状態を指します。
日常生活では「明日の天気に期待する」「子どもの成長を期待する」など、未来に向かうポジティブな気持ちを表す語として使われます。
一方で期待には「思い通りにならないかもしれない」という不安や緊張も含まれており、必ずしも楽観的な感情だけを表すわけではありません。
期待という言葉は対象によって「物事」への期待、「人」への期待、「自分自身」への期待といった複数の側面に分けて理解できます。
物事への期待は天候や経済など自分では制御できない要素に向けられ、人への期待は家族や仲間に対して成果や振る舞いを望む気持ちとして現れます。
自分自身への期待は自己効力感とも結びつき、達成目標を立てたり努力を続けたりする原動力になります。
心理学では期待を「予期」や「予測」と区別して扱うことがあります。
予期・予測が比較的中立的な未来の見積もりを指すのに対して、期待はそこに「願望」が加わる点が特徴です。
そのため期待は感情の高まりやモチベーションと密接に関わり、行動の方向性やパフォーマンスにも影響を与えます。
さらに社会学の領域では、期待が人間関係の摩擦を生む要因として研究されてきました。
「期待が裏切られた」と感じると失望や怒りが生じるように、期待はコミュニケーション上の暗黙の約束と見ることもできます。
期待の調整や共有は対人関係を円滑にする上で欠かせないテーマです。
最後にビジネスの文脈では「顧客期待」「株主期待」のようにステークホルダーの要求水準を示す言葉として用いられます。
この場合、期待を正確に把握し超えることが顧客満足度や企業価値の向上につながると考えられています。
「期待」の読み方はなんと読む?
「期待」は一般に「きたい」と読み、訓読みと音読みが組み合わさった熟字訓ではなく、二語とも音読みで発音します。
「期」は音読みで「き」と読み、期間や時期を表す漢字です。
「待」は音読みで「たい」と読み、待つことや迎え入れることを示します。
「きたい」という響きは日常会話で頻繁に耳にするため難読語ではありませんが、日本語学習者にとっては「期」を「き」と読む点が混乱しやすいところです。
同じ「待」の音読みは「たい」「だい」がありますが、熟語によって読み分けが異なるため辞書で確認する習慣が役立ちます。
また、ビジネス文書や学術論文では「期待値(きたいち)」のように複合語として使われるケースが多く、読み間違いがないか校正時に注意が必要です。
電子辞書やIMEの変換候補には「期待」と「希待」が並ぶことがありますが、後者は一般的でなく公用文では避けるのが無難です。
「期待」という言葉の使い方や例文を解説!
期待を表す文では「〜を期待する」「〜に期待が高まる」の形で目的語や主語を明示し、ポジティブなニュアンスを伝えるのが基本です。
動詞化して「期待する」と述語として使うほか、「期待感」「期待値」といった名詞としての活用も見られます。
「高い期待」「大きな期待」のように程度を示す形容詞を伴うと具体的な熱量が伝わりやすくなります。
【例文1】新製品がもたらす技術革新に期待が集まっている。
【例文2】監督は若手選手の活躍を期待して先発起用した。
例文では「集まっている」「して」と補助動詞を組み合わせることで状況の進行や意図を描写しています。
ビジネスの交渉場面で「過度な期待を抱かせないよう数字を提示する」のように、期待をコントロールする表現も重要です。
注意点として、相手に強い圧力をかける意味での「期待しています」はプレッシャーになる可能性があります。
公的なメールでは「ご期待ください」より、「ご期待に沿えるよう努めます」と自分の行動にフォーカスした文に言い換えると円滑です。
「期待」という言葉の成り立ちや由来について解説
「期待」は中国の古典にも見られる熟語で、「期して待つ」という四字句を省略した形が語源と考えられています。
「期」は「期日を定めて待つ」、すなわち「約束の時を設定する」意味を持つ漢字です。
「待」は「まつ」「出迎える」を表し、合わせて「期して待つ」=「期日を心に決めて待つ」という慣用句が成立しました。
漢籍『後漢書』や『史記』には「期待」の用例があり、日本には奈良時代に漢文とともに輸入されたとされます。
当時の用法は現代日本語と大きく変わらず、朝廷が外交使節の到着を「期待」する場面など公的な文章で使われていました。
平安期に国風文化が花開くと和語との混交が進み、「待つ」に対応する概念として「期待」が受容され、やがて音読みの二字熟語が定着しました。
江戸時代の儒学者の書簡では「貴殿の来書を期待候」と見られ、武家や知識人の間で広く用いられたことが分かります。
「期待」という言葉の歴史
日本語の「期待」は平安期の漢籍註釈書に現れて以来、文学・政治・経済と多様な分野で使われ、近代に入ると心理学用語としても定着しました。
近世文学では、井原西鶴や近松門左衛門の作品に「期待」が登場し、登場人物の心情を説明する語として用いられています。
明治期には西洋近代思想の翻訳用語として「hope」や「expectation」の訳語に「期待」が当てられ、学術語としての地位が確立しました。
大正から昭和初期にかけて、経済学者が「期待利潤」「期待収益」の概念を導入し、統計学では「期待値(expected value)」が定義されます。
これにより「期待」は定量的に扱える概念として広く受け入れられ、数学・投資理論・保険数理など専門領域のキーワードとなりました。
戦後はマスコミが「国民の期待」「若者の期待」というキャッチフレーズで多用し、ポジティブイメージが強調されます。
平成以降はSNSの普及によって「期待値が高い映画」「期待しすぎた自分が悪い」のように、カジュアルな感想表現として急速に拡散しました。
「期待」の類語・同義語・言い換え表現
「期待」を言い換える際には「希望」「願望」「予想」「目論見」など文脈に合わせた類語を選ぶことで、ニュアンスの違いを的確に表現できます。
「希望」は実現可能性よりも「願い」の要素が強く、主観的で感情的です。
「期待」は願望に加えて一定の合理的根拠や可能性を暗示する点で「希望」と区別されます。
「予想」はデータや経験に基づく客観的な見込みを指し、感情の入り込みが少ないのが特徴です。
金融取引で使われる「見通し」や「想定」はリスク分析の色合いが強く、ポジティブさよりも現実的な判断を前提にしています。
「目論見」は計画性を含み、やや策略的・ビジネスライクな印象を与えます。
同じ「楽しみにする」を意味する「期待」に比べて、成功や利益を狙う意図が透けて見える場合があります。
言い換えでは目的語や主語との相性も重要です。
たとえば「市場の反応を期待する」を「市場の反応を予想する」に置き換えると、感情表現が薄まり分析的な文章になります。
「期待」の対義語・反対語
「期待」の対義語として最も一般的なのは「失望」「諦念(ていねん)」であり、ポジティブな待望感がネガティブな感情へ転じた状態を示します。
「失望」は期待が裏切られた結果として生じる感情で、「期待」の成否に焦点を当てた言葉です。
「諦念」は仏教由来の語で、結果を受け入れて執着を手放す心境をいい、「期待しない」スタンスを表します。
「悲観」や「懐疑」は将来に対して否定的・懐疑的な見方を示し、期待と相反する価値観として使われます。
心理学の「学習性無力感」は、期待の欠如が行動の停止を招くメカニズムとして研究されています。
ビジネス現場で「過度な期待を是正する」対義表現として「リスク管理」「現実的な見積もり」などが用いられることもあります。
このように対義語は単なる反対概念にとどまらず、状況や学術的背景を踏まえて選択する必要があります。
「期待」を日常生活で活用する方法
期待は目標設定や自己成長のエンジンになるため、意識的に「適切な期待水準」を設けることでモチベーションを最適化できます。
まず、自分への期待を具体的な行動目標に落とし込みます。
例として「一日30分の英語学習を半年続ける」と決めることで期待が行動指針に変わります。
他者への期待はコミュニケーションで共有し、相手が受け止めやすい表現に整えることが大切です。
子育てなら「テストで100点を取って」と言う代わりに「あなたが努力する過程を応援している」と伝えるとプレッシャーを軽減できます。
期待が高まりすぎると失望リスクが増すため、「最悪の場合どうするか」を想定するバックアッププランを持つことも有効です。
心理学でいう「情動調整」によって、期待と結果のギャップがメンタルに与える影響を和らげられます。
日常的に「小さな期待と小さな成功体験」を積み重ねると自己効力感が向上し、より大きな挑戦へ自然に踏み出せます。
このサイクルを回すことがポジティブな期待の育て方のコツです。
「期待」という言葉についてまとめ
- 「期待」は未来の良い結果を願いながら待ち望む心理状態を指す言葉。
- 読み方は「きたい」で、二字とも音読みが基本。
- 古代中国の「期して待つ」に由来し、日本では平安期から用例が確認できる。
- ビジネス・教育・日常会話で広く使われるが、過度な期待は失望を招くので注意が必要。
「期待」は希望と合理的見込みを兼ね備えた、感情と実利の両面を持つ日本語です。
読みやすく使いやすい一方、相手に押しつける形で用いるとプレッシャーや失望につながりかねない点が要注意です。
歴史的には奈良・平安期から漢籍とともに輸入され、近代に学術用語として体系化されました。
現代では「期待値」「顧客期待」など専門用語にも派生し、社会のさまざまな局面で欠かせない概念となっています。
適切な期待設定と共有は、自己成長や人間関係を豊かにする有効なスキルです。
日々の生活で「小さな期待と成功」を積み重ね、健全なモチベーションを育てていきましょう。