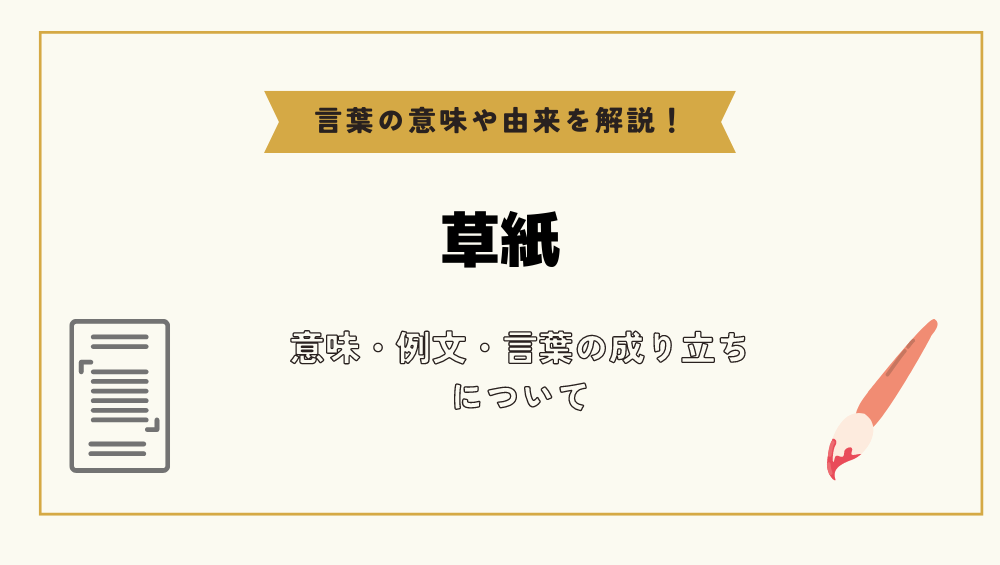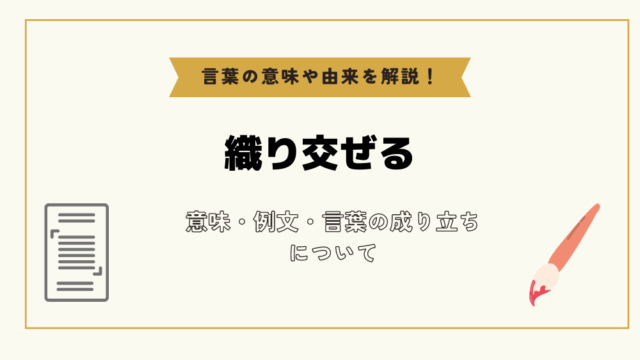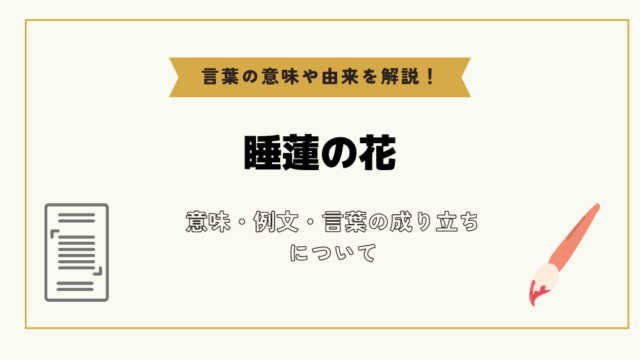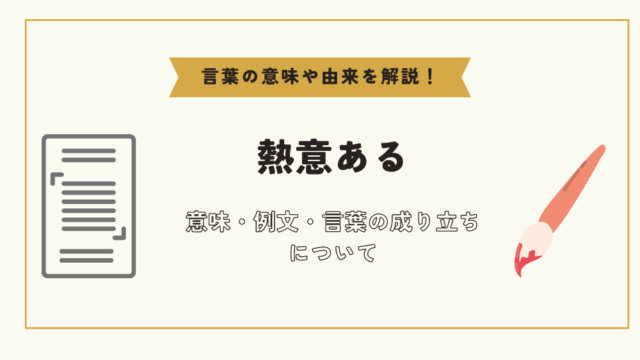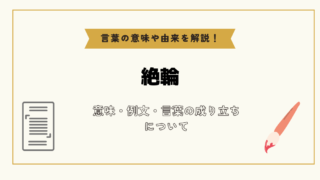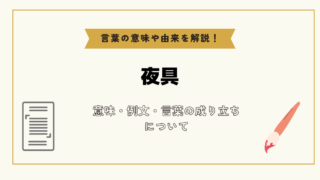Contents
「草紙」という言葉の意味を解説!
草紙(そうし)という言葉は、古代から使われる伝統的な日本の文化の一つです。
「草紙」とは、紙のことを指し、特に日本で古くから使われてきた手書きの書物や日記のようなものを指します。
草紙は、普段の暮らしや思い出を記録したり、詩や字を練習したりするために利用されます。
「草紙」という言葉の読み方はなんと読む?
「草紙」という言葉は、「そうし」と読みます。
日本語の発音の特徴として、1つの文字に対して複数の読み方があることがありますが、「草紙」は「そうし」と読むのが一般的です。
他にも「そうじ」と読むこともありますが、その場合はおそらく掃除の意味になりますので、注意が必要です。
「草紙」という言葉の使い方や例文を解説!
「草紙」という言葉は、古典的な文化や日本の歴史に関連する文脈でしばしば使われます。
例えば、「彼は世界的に有名な俳人で、数々の草紙を残しました」というように使われ、その人物の詩や作品を指しています。
また、最近では、草紙をモチーフにしたデザインの発表会や展示会も増えてきており、草紙を身近に感じる機会も増えています。
「草紙」という言葉の成り立ちや由来について解説
「草紙」という言葉は、古代の日本で生まれました。
当時、紙は貴重な存在でしたが、書物や日記などを書くために欠かせないものでした。
そのため、普通の紙よりも一枚の大きさが小さく、手軽に使えるようにと草紙が開発されました。
また、当時の日本では、万葉集や古今和歌集などの名作が草紙に書かれ、後世に伝えられることとなりました。
「草紙」という言葉の歴史
草紙は、平安時代から江戸時代にかけて最もよく使われていた紙の一つです。
当時は、著名な人物や文化人が詩や文章を書き留めるために草紙を用いていました。
そして、草紙に書かれた作品は多くが後世に伝えられ、日本の文化や歴史の一部として大切にされてきました。
現代では、草紙の伝統が受け継がれ、芸術家や書道家が草紙を使った作品を制作しています。
「草紙」という言葉についてまとめ
「草紙」は、古くから日本で使われてきた伝統的な書物や日記を指す言葉です。
読み方は「そうし」です。
日本の歴史や文化に関連する文脈でよく使われ、詩や作品を書くために利用されてきました。
草紙は、書物や手紙の一部として大切にされ、その伝統が現代に受け継がれています。
草紙は、古き良き日本の文化を彷彿させ、私たちに感動や興味を与えてくれます。