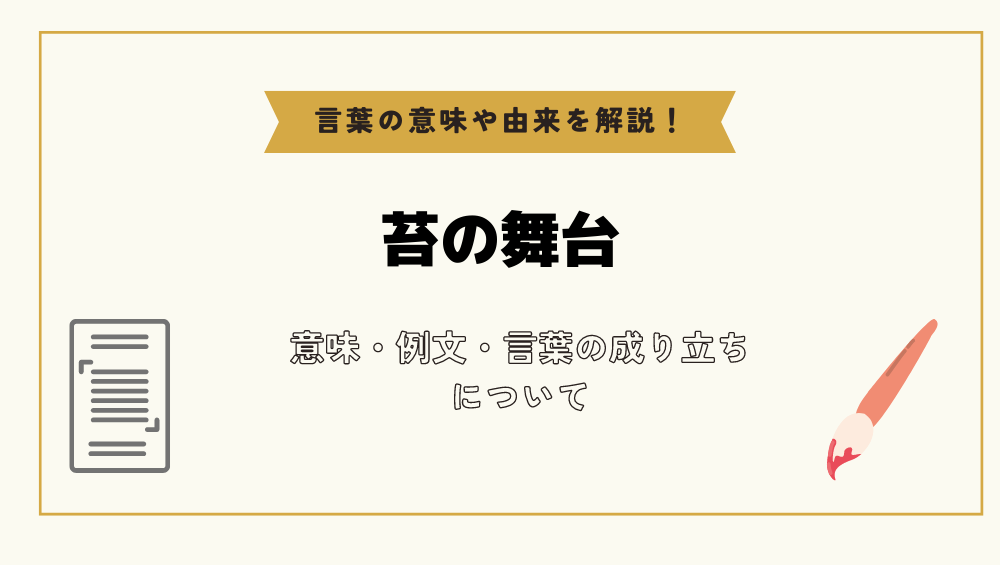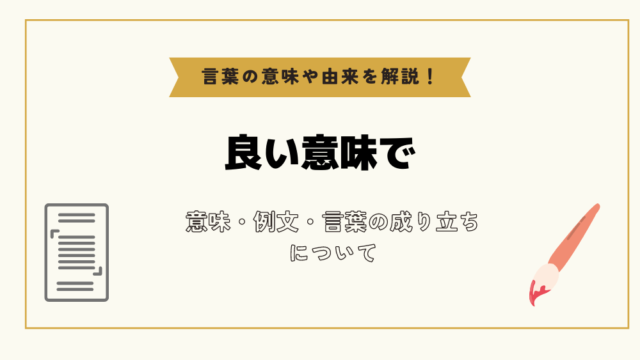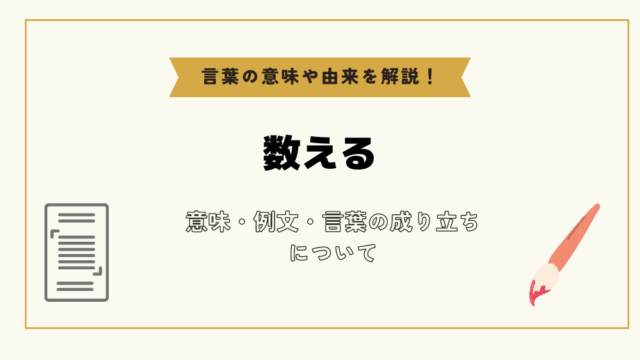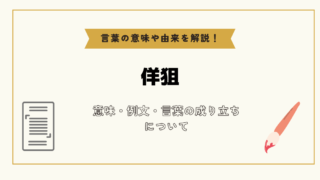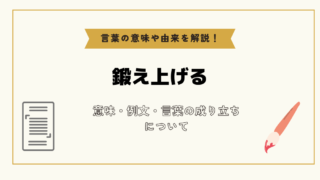Contents
「苔の舞台」という言葉の意味を解説!
「苔の舞台」という言葉は、自然の力強さや美しさを表現するために使われることがあります。
苔は、湿った環境で成長する一種の植物であり、石や木などの表面に美しい緑色のカーテンを作り出します。
この苔の成長を舞台に例えることで、自然の神秘や生命力を感じることができます。
「苔の舞台」という言葉の読み方はなんと読む?
「苔の舞台」という言葉は、「こけのぶたい」と読みます。
日本語の発音にはいくつかのバリエーションがありますが、一般的にはこちらの読み方がよく使われています。
「苔の舞台」という言葉の使い方や例文を解説!
「苔の舞台」という言葉は、雅なイメージや自然の美を表現するときに使われます。
例えば、日本庭園の中にある石組みの庭や、公園の古い木の根元に生えた苔などは、まさに「苔の舞台」と呼ぶにふさわしい場面です。
また、小説や詩においても、自然の中での生活や感動的な光景を表現する際に「苔の舞台」という表現が用いられることがあります。
「苔の舞台」という言葉の成り立ちや由来について解説
「苔の舞台」という表現の成り立ちは、日本の自然美を愛でる文化と深い関わりがあります。
苔は日本の風景や文化に欠かせない存在であり、その美しさや神秘性は古代から詩歌や絵画に描かれ、日本人の心に強く響いてきました。
このような背景から、「苔の舞台」という言葉が生まれたと考えられます。
「苔の舞台」という言葉の歴史
「苔の舞台」という言葉の歴史は古く、日本の文学や芸術においてよく見られます。
平安時代の歌物語や近代文学の中で、「苔の舞台」は幾度となく描かれてきました。
その美しい風景や季節感を通じて、日本人の心にふれることのできる表現として、受け継がれてきたのです。
「苔の舞台」という言葉についてまとめ
「苔の舞台」という言葉は、日本の自然美や風景を描写する際に用いられる表現です。
苔は湿った環境で成長する植物であり、石や木の表面を美しい緑色で覆いつくします。
この成長過程を舞台に例え、自然の神秘や生命力を表現することが「苔の舞台」という言葉の本質です。
日本の文学や芸術で多く見られるこの表現は、雅なイメージを想起させます。