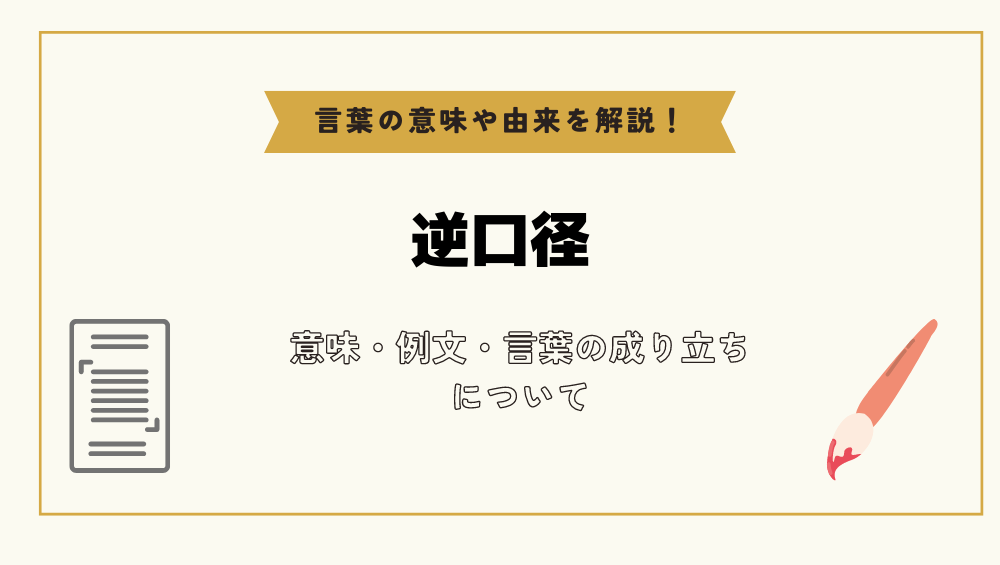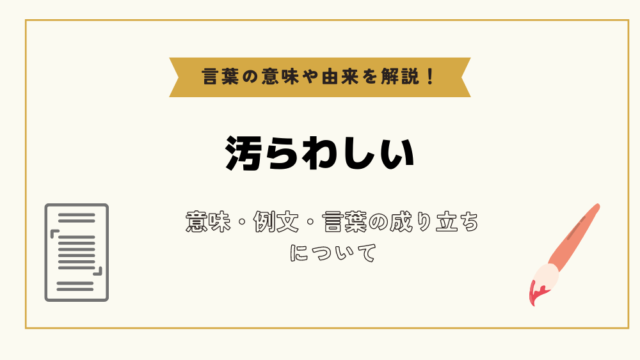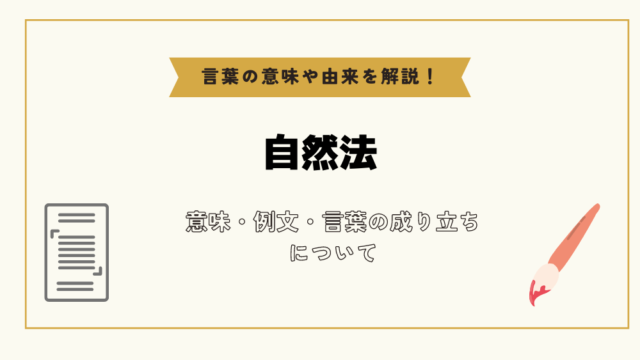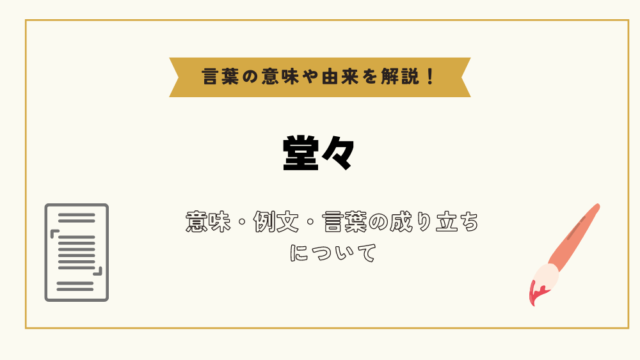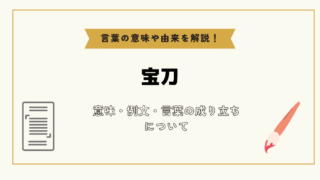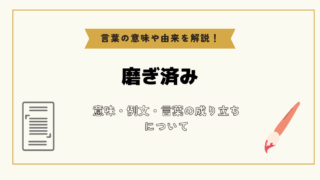Contents
「逆口径」という言葉の意味を解説!
「逆口径」という言葉は、一般的には直径の逆数を指す言葉です。
直径が大きければ逆口径は小さくなり、直径が小さければ逆口径は大きくなります。
逆口径は、主にドリルやネジの規格などで使用されます。
具体的には、ネジのサイズにおいて、「メートル型(M)」や「インチ型(I)」といった単位の後ろに、逆口径の値が付けられます。
逆口径はネジのサイズを表す重要な要素であり、正確な測定が求められます。
「逆口径」という言葉の読み方はなんと読む?
「逆口径」という言葉は、「ぎゃくこうけい」と読みます。
日本語の発音では、”ぎゃく”と”こうけい”の2つの音で表します。
この読み方は一般的で、逆口径を専門とする分野でも同じように呼ばれています。
「逆口径」という言葉の使い方や例文を解説!
「逆口径」という言葉は、主に機械工学や建築などの分野で使用されます。
例えば、ある工場で使われる装置の一部を作るにあたり、逆口径のドリルが必要となる場合があります。
もうひとつの例として、建築現場においては、逆口径のボルトやナットが使用されることもあります。
逆口径の使用は、特定の規格や目的に応じた工具や部品を選ぶ際に欠かせない要素となります。
「逆口径」という言葉の成り立ちや由来について解説
「逆口径」という言葉は、”逆”と”口径”という2つの言葉から成り立っています。
“逆”という言葉は、反対や反転の意味を持ちます。
“口径”とは、円周上の直径を指し示す言葉です。
この2つの言葉を組み合わせることで、「直径の逆数」という意味を持つ「逆口径」という言葉が生まれました。
逆口径は、円周の大きさを表す重要な要素であり、様々な分野で使用されています。
「逆口径」という言葉の歴史
「逆口径」という言葉は、19世紀に工学や建築などの分野で使用され始めました。
当時の技術革新によって、より正確な測定や設計が可能になったことから、逆口径の概念も浸透していきました。
逆口径は、工業化の進展とともに多くの分野で使用されるようになり、現代の製造業や建設業においても一般的な概念となっています。
「逆口径」という言葉についてまとめ
今回は、「逆口径」という言葉について解説しました。
逆口径は、主に直径の逆数を意味し、機械工学や建築などの分野で使用されます。
正確な測定が求められる重要な要素であり、特定の規格や目的に応じた工具や部品の選択に欠かせない要素です。
「逆口径」という言葉は、19世紀の技術革新とともに登場し、現代の製造業や建設業においても広く使用されています。