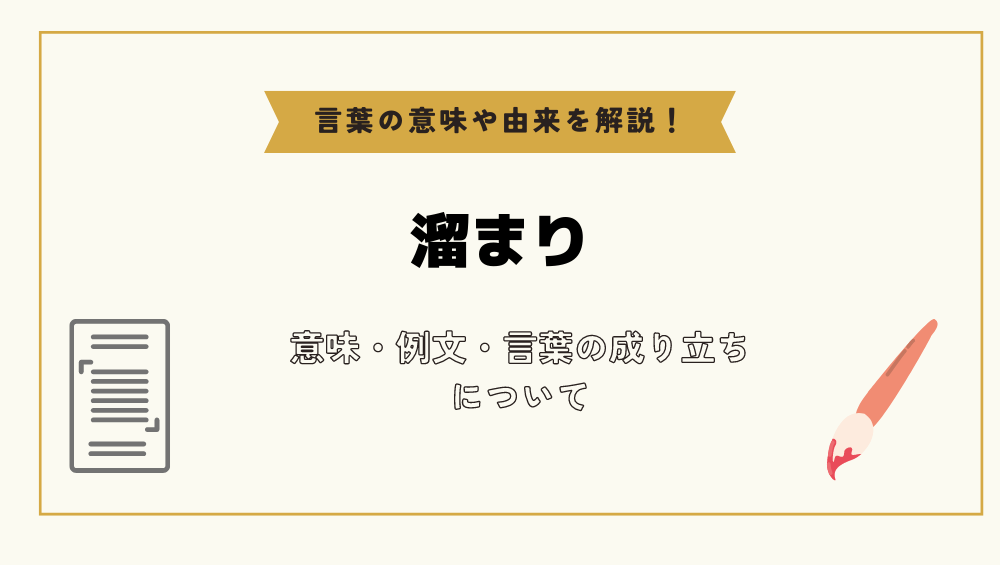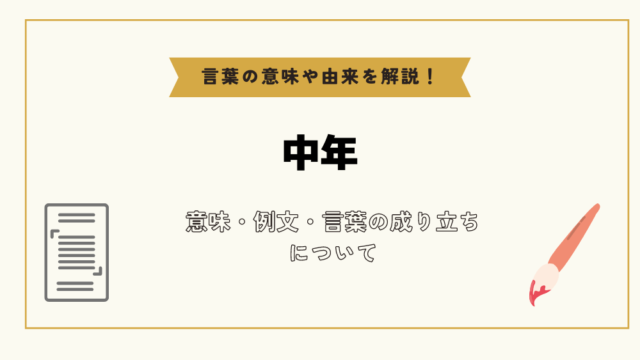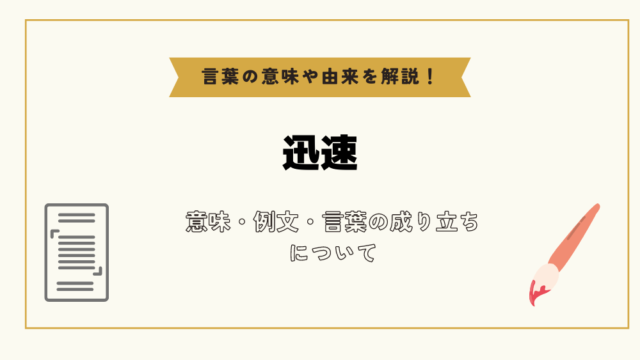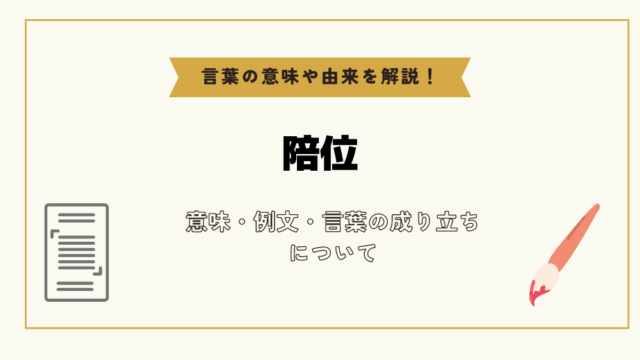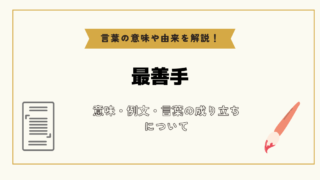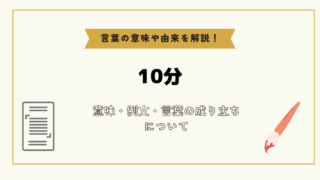Contents
「溜まり」という言葉の意味を解説!
「溜まり」という言葉は、日本語において、水がたまる場所や物が集まる場所を指す名詞です。
例えば、雨が降って水たまりができることや、自然の中にできる池や湖などが「溜まり」と呼ばれることがあります。
溜まりは、一時的に集まったものが積み重なり、形成される場所を表現しています。
「溜まり」という言葉の読み方はなんと読む?
「溜まり」という言葉は、読み方は「たまり」となります。
溜まりは、「たまり」と発音することで、日常的によく使われる表現です。
「溜まり」という言葉の使い方や例文を解説!
「溜まり」という言葉は、水のたまった場所や物がたまる場所を指す名詞としてよく使われます。
例えば、雨が降ってできた溜まりを避けて歩く、台所の流しに食器を溜まりさせる、などの使い方があります。
また、感情や罪悪感なども表現することもあります。
例えば、仕事が忙しいためにストレスが溜まりに溜まり、体調を崩すこともあります。
「溜まり」という言葉の成り立ちや由来について解説
「溜まり」という言葉の成り立ちは、古代中国から伝わった漢字をもとにしています。
元々は「停まる」や「入る」という意味を持っていた漢字が、日本語独自の表現として「溜まる」や「溜まり」と呼ばれるようになりました。
溜まりの由来には、古代の風習や文化的な要素が結びついています。
「溜まり」という言葉の歴史
「溜まり」という言葉の歴史は古く、日本語の始まりとともに存在していました。
古代の日本では、自然の中にできた湖や池などが「溜まり」と呼ばれていました。
また、農業が盛んな時代には、水を貯めることが重要であったため、畑に築かれた「溜まり池」なども存在しました。
さまざまな状況や時代において、「溜まり」という言葉は使われ続けてきました。
「溜まり」という言葉についてまとめ
「溜まり」という言葉は、水がたまる場所や物が集まる場所を指す名詞として用いられます。
読み方は「たまり」となります。
日常会話や文章でよく使用され、親しみやすさや人間味が感じられる表現です。
古代の中国から伝わり、日本独自の表現として定着しました。
古代の風習や文化的要素などが結びついており、様々な状況や時代において用いられ続けてきた歴史を持っています。