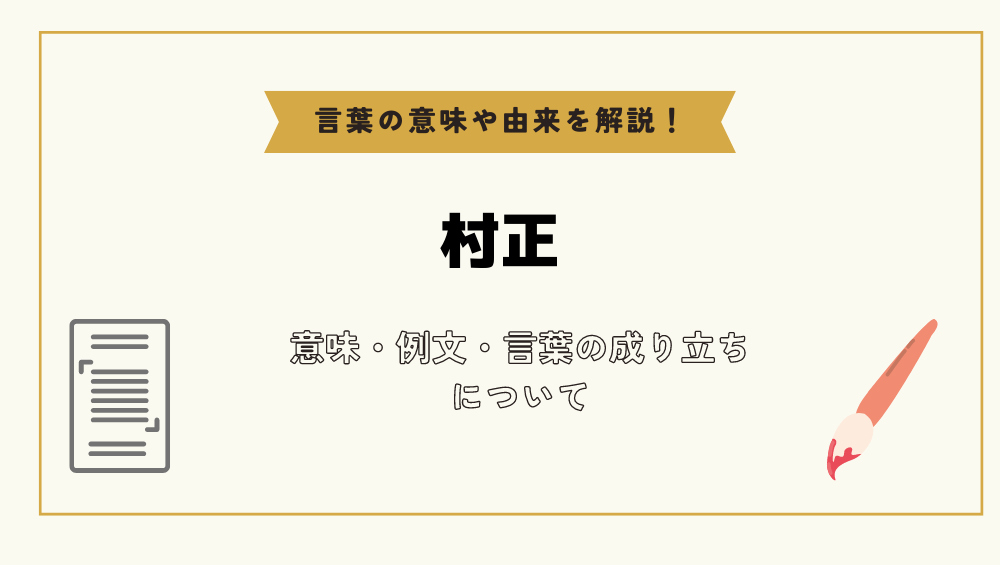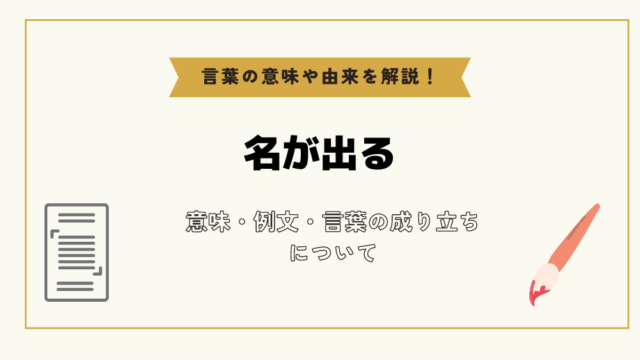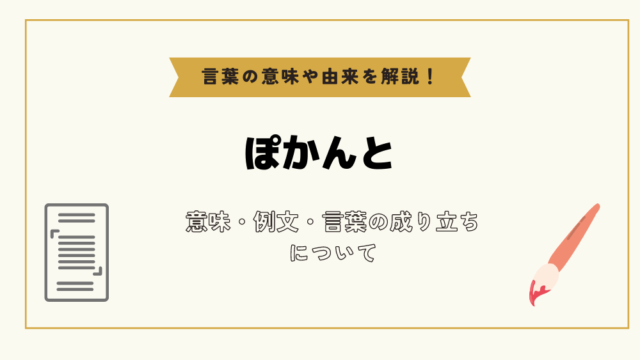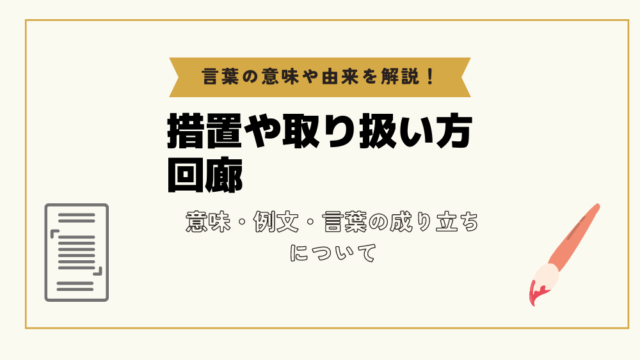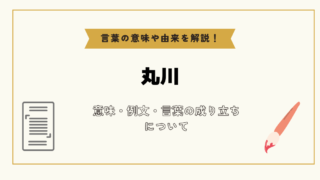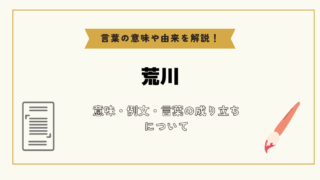Contents
「村正」という言葉の意味を解説!
「村正」という言葉は、日本の刀剣の一つで、特に鎌倉時代から室町時代にかけて作られた名刀のことを指します。
「村正」とは、刀工の名前であり、その名を冠した刀剣を総称して「村正」と呼んでいます。
「村正」という言葉の読み方はなんと読む?
「村正」という言葉は、「むらまさ」と読みます。
日本語の発音で、それぞれの文字を分かりやすく読むという形になります。
音読みではなく、訓読みで「むらまさ」と読むことが正しい読み方です。
「村正」という言葉の使い方や例文を解説!
「村正」という言葉は、刀剣の分野でよく使われます。
「この刀は村正の名刀です」と言ったり、「村正の刀剣展が開催されています」と紹介したりするときに使われます。
また、「村正の刀剣は美しい刃文が特徴です」といったように、その特徴や魅力について説明する際にも使用されます。
「村正」という言葉の成り立ちや由来について解説
「村正」という言葉の成り立ちは、刀工の村正に由来しています。
村正は、鎌倉時代から室町時代にかけて活躍した刀工であり、その創作活動から生まれた刀剣が「村正」と呼ばれるようになりました。
その後、多くの刀工たちが村正を手本として刀を制作するようになり、村正の名は刀剣のブランドとして広まっていきました。
「村正」という言葉の歴史
「村正」という言葉の歴史は古く、刀剣の歴史と深く結びついています。
村正という名前を冠した刀剣は、鎌倉時代から室町時代にかけて作られ、その美しさや切れ味から多くの武士や武将に愛されました。
また、村正の名は刀剣の評価基準としても重要視され、刀剣の鑑定などにおいても重要な要素となっています。
「村正」という言葉についてまとめ
「村正」という言葉は、日本の刀剣の一つであり、特に鎌倉時代から室町時代にかけて作られた名刀を指します。
その美しい刃文や鋭い切れ味から、多くの人々に愛されてきました。
村正は、刀剣の品評基準としても重要であり、刀剣ファンや歴史愛好家にとってはなくてはならない存在です。