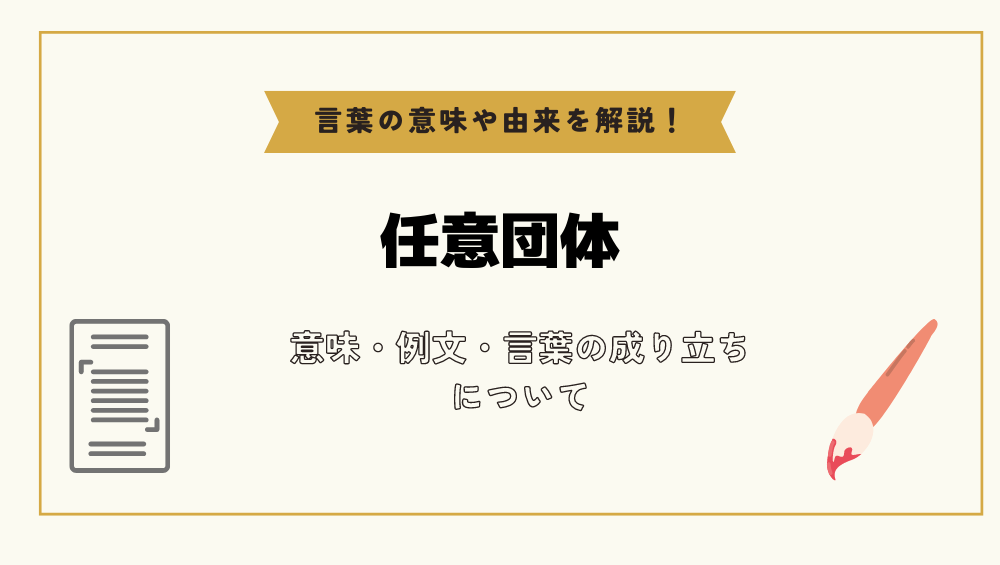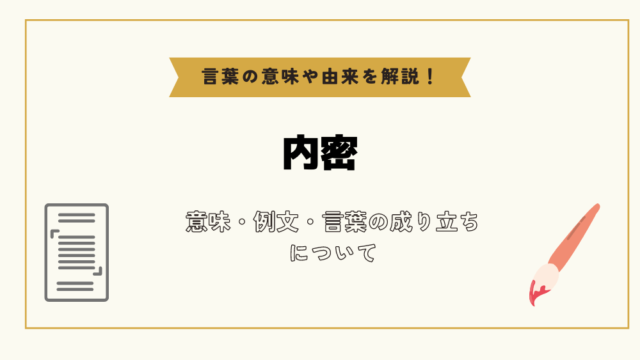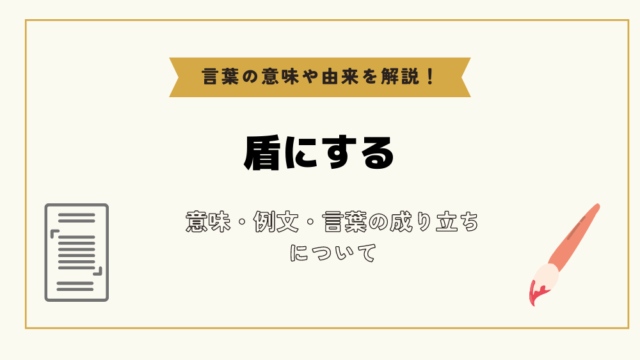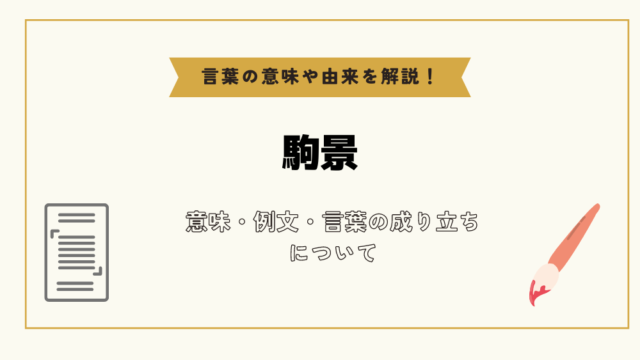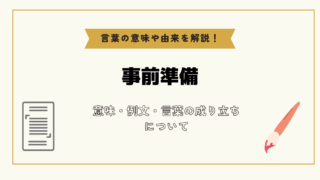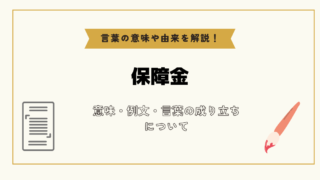Contents
「任意団体」という言葉の意味を解説!
任意団体とは、会員の自主的な参加によって成り立つ法人組織のことを指します。
具体的な目的や活動内容は様々であり、スポーツクラブや文化サークル、ボランティア団体などが典型的な例です。
任意団体は法人格を持つことができ、少人数から大規模な団体までさまざまな形態が存在します。
「任意団体」という言葉の読み方はなんと読む?
「任意団体」という言葉は、「にんいだんたい」と読みます。
漢字の「任意」は、ある行為を強制されずに自由に行うことを意味し、「団体」は複数の人が一緒になって活動する組織を指します。
このように、読み方からも会員の自由な参加が重視されることがわかります。
「任意団体」という言葉の使い方や例文を解説!
「任意団体」という言葉は、法的な性格を持ちながらも、会員の自主的な参加によって成り立つ組織を指すため、様々な場面で使われます。
例えば、スポーツクラブの活動案内で「当団体は任意団体ですので、興味のある方はいつでも参加してください」と表現されることがあります。
また、学生団体の募集チラシには「任意団体なので、予定が合えば是非参加してみてください」と書かれていることもあります。
「任意団体」という言葉の成り立ちや由来について解説
「任意団体」という言葉は、日本の法制度において規定されています。
具体的な成り立ちや由来については、法律的な観点から解説されることが多いです。
任意団体の概念は、自由な結社権や経済的な交渉権を保障する目的で、民法上に位置づけられています。
法律の制定過程や具体的な由来については、民法や関連する法令を調査することで詳細を知ることができます。
「任意団体」という言葉の歴史
「任意団体」という言葉の歴史は、近代日本の法制度の発展と密接に関わっています。
明治時代に民法が制定され、自由な結社権が認められたことで、任意団体の法的地位が確立されました。
その後、経済や社会の変化に伴い、様々な分野で任意団体が設立されるようになりました。
現在では、地域活性化を目指す団体や専門的な研究を行う団体など、多様な分野で活動しています。
「任意団体」という言葉についてまとめ
「任意団体」とは、会員の自主的な参加によって成り立つ法人組織のことを指します。
読み方は「にんいだんたい」であり、会員の自由な参加が重視される特徴があります。
また、様々な場面で使われる言葉であり、スポーツクラブや文化サークルなどが典型的な例です。
日本の法制度において規定されているため、法律の制定過程や由来も重要な要素です。
近代日本の法制度の発展によって生まれた言葉であり、現在では様々な分野で活動する団体が存在します。