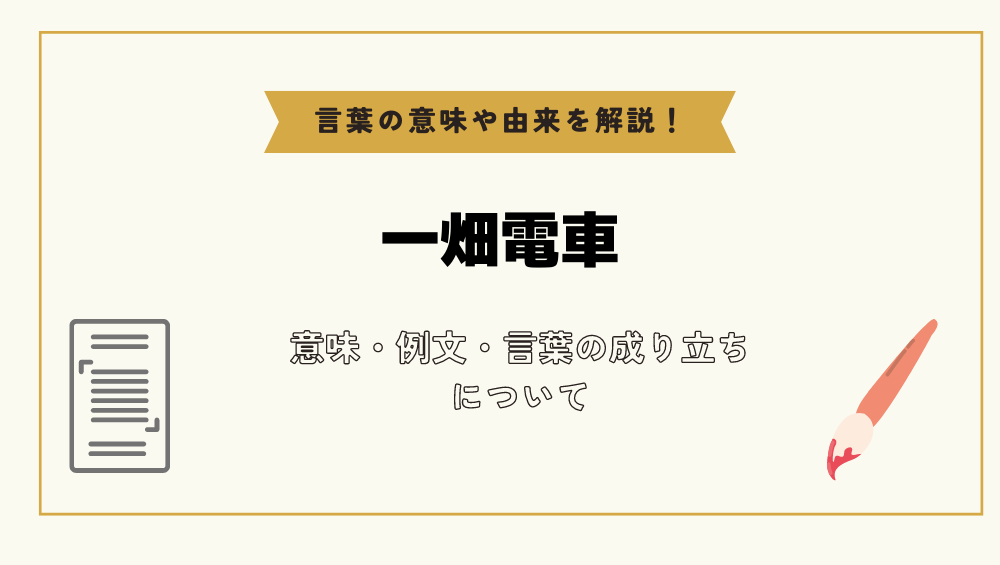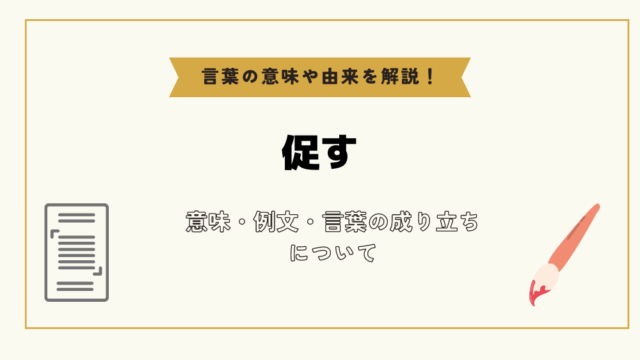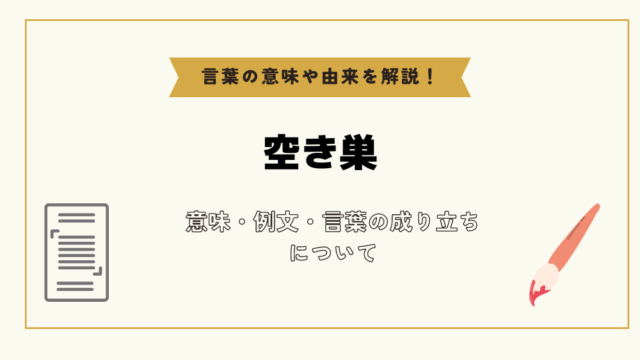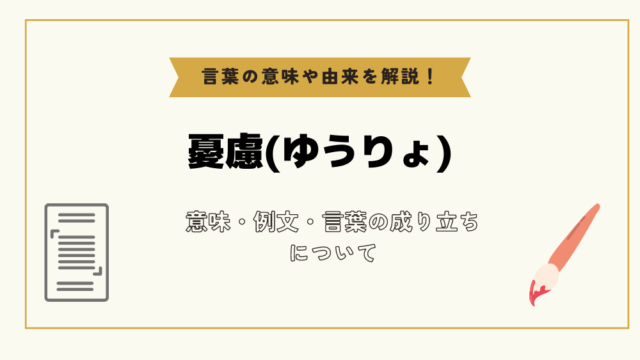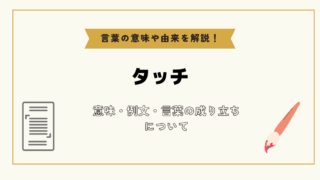Contents
「一畑電車」という言葉の意味を解説!
「一畑電車」とは、山陰地方で運行されている鉄道のことを指します。
主に島根県と鳥取県を結ぶ路線で、観光地へのアクセス手段としても利用されています。
冬の雪景色や春の桜、秋の紅葉など四季折々の美しい自然を楽しみながら、地域の魅力も体感することができる鉄道です。
「一畑電車」という言葉の読み方はなんと読む?
「一畑電車」という言葉は、「いちはたでんしゃ」と読みます。
観光客や地域住民の方々に愛されており、地元の方々にとっては日常の足として欠かせない存在です。
一畑電車は地域の文化や風習とも密接に結びついており、地元の人々にとっての大切な存在となっています。
「一畑電車」という言葉の使い方や例文を解説!
「一畑電車」を使った例文としては、「一畑電車の旅は、自然豊かな風景とローカルな雰囲気を堪能できますよ」といった形で使用することができます。
また、「一畑電車の沿線には、歴史的な観光スポットが多くあります」といったように、観光情報を伝える際にも頻繁に用いられます。
「一畑電車」という言葉の成り立ちや由来について解説
「一畑電車」という名称は、一畑地方に鉄道を敷設する計画が立ち上がった際に、地元住民の意見を元に命名されました。
地域の文化や風習に根ざし、地域の人々の心に寄り添う鉄道を目指していたことが反映されています。
これにより、一畑電車は地域住民に親しまれ、多くの人々が集まる交流の場となっています。
「一畑電車」という言葉の歴史
一畑電車の歴史は、昭和初期に遡ります。
島根県松江市から鳥取県米子市の間に路線を開通させる計画が進められ、1928年に一部区間が開業しました。
当時から観光客の利用が多く、地域の観光振興に大きく貢献してきました。
その後も路線の延伸や改良が行われ、現在に至っています。
「一畑電車」という言葉についてまとめ
「一畑電車」とは山陰地方で運行されている鉄道で、地域の魅力や自然を楽しむことができる交通手段です。
観光客のみならず地元の人々にとっても欠かせない存在であり、地域住民とのふれあいや交流の場としても大切な役割を果たしています。
一畑電車は、地域の魅力をより多くの人々に広めるための貴重な手段となっています。