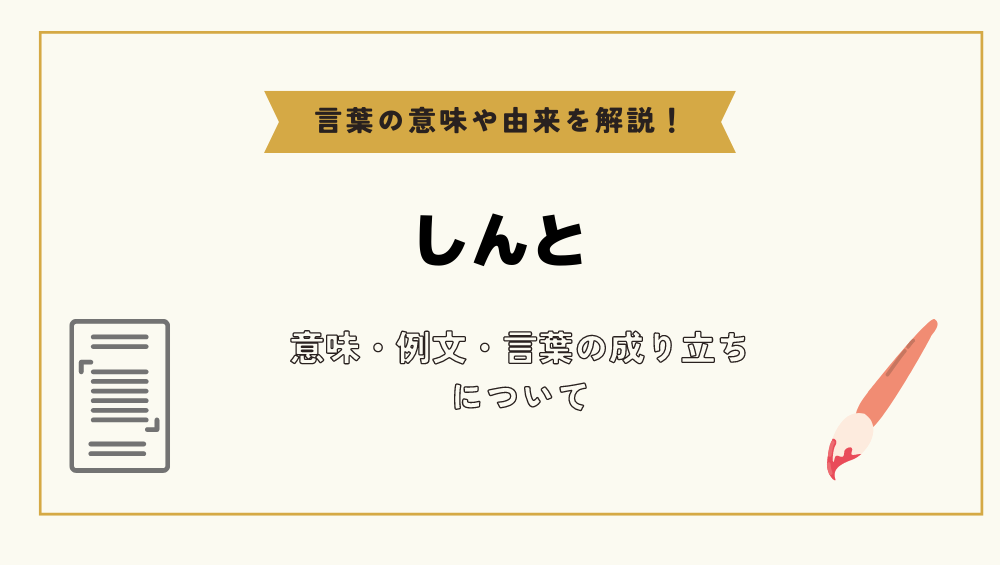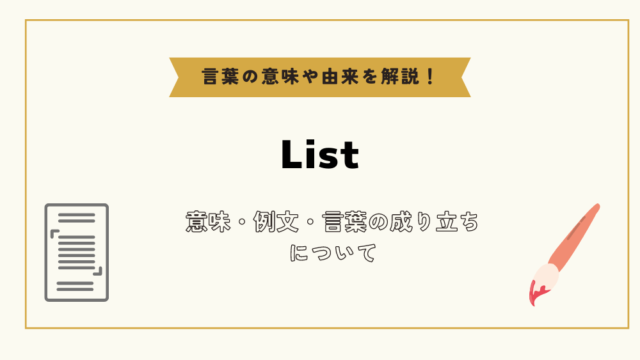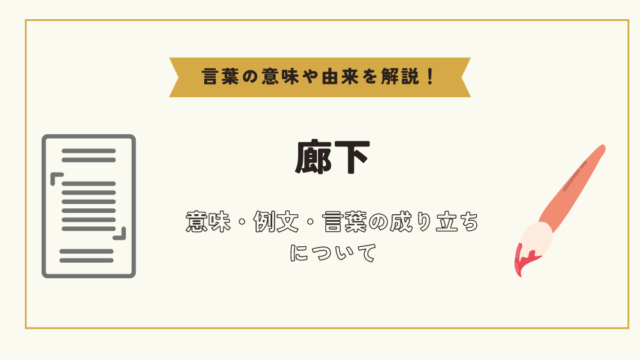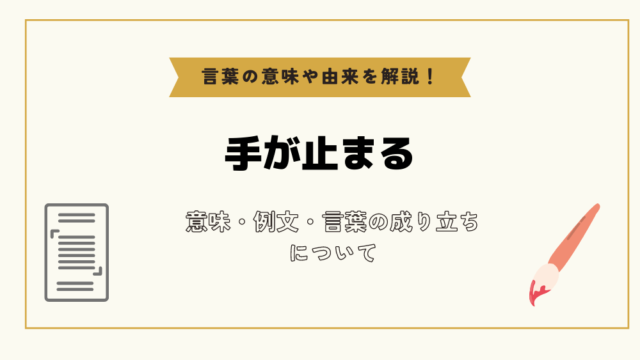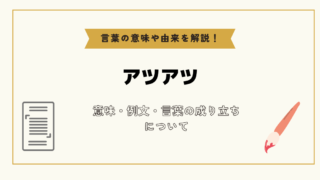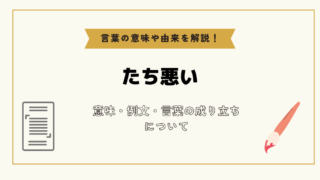Contents
「しんと」という言葉の意味を解説!
「しんと」という言葉は、静まり返っている様子や静寂を表現する言葉です。
何かの音や動きがなく、まるで時間が止まったかのような状態を意味します。
例えば、夜の森の中や図書館での静かな雰囲気を表現するのに用いられます。
また、緊張や緊張感が漂っている様子も「しんと」で表現することがあります。
「しんと」という言葉の読み方はなんと読む?
「しんと」という言葉は、「しんと」と読みます。
特に読み方に変わったルールや発音の注意点はありません。
日本語なので、一般的な読み方で問題ありません。
「しんと」という言葉の使い方や例文を解説!
「しんと」という言葉は、静かな状況を表現するために使われます。
例えば、「しんとした部屋で本を読む」というように、部屋がとても静かな状態で、周囲に音が聞こえないような場面を想像してください。
また、「しんとしている人々の中に一人だけ声を漏らす」といった風にも使えます。
このように人々が静かにしている中で一部の人が声を出す様子を意味します。
「しんと」という言葉の成り立ちや由来について解説
「しんと」という言葉は、動詞「忍ぶ」と形容詞「静か」との組み合わせで成り立っています。
元々は、「忍んで静かにする」という意味から派生した表現であると言われています。
また、この言葉は古くから日本語に存在しており、日本の風土や文化に根付いている言葉と言えます。
「しんと」という言葉の歴史
「しんと」という言葉は、古くから日本語に存在しており、歴史も長い言葉です。
古代の歌や文学にもよく登場し、風雅や精神性を表現するために用いられてきました。
また、武士道や禅宗の修行においても、「しんと」した心を持つことが重要視されてきました。
現代でも、日本人の心の美や精神性を表現する言葉として使われ続けています。
「しんと」という言葉についてまとめ
「しんと」という言葉は、静まり返った状態や静寂を表現するために使われます。
静かな空間や緊張感が漂っている様子を表現するのに適した言葉です。
日本の風土や文化に根付いており、古くから使われてきた言葉です。
心の美や精神性を表現する際にも重要な言葉として用いられます。