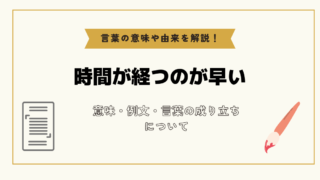Contents
「気のかかる」という言葉の意味を解説!
「気のかかる」という言葉は、大切な人や物事に対して気を遣う、心を配るという意味があります。
気にかけるとも表現されます。
例えば、友人や家族の健康や幸福を心配して、自分ができる限りのサポートや助言をする様子に「気のかかる」という言葉が使われることがあります。
「気のかかる」の読み方はなんと読む?
「気のかかる」の読み方は、「きのかかる」と読みます。
日本語の読み方において、「気」は「き」と読まれることが多く、その後に続く「のかかる」は「のかかる」と頭の中でイメージしながら読むと良いでしょう。
「気のかかる」という言葉の使い方や例文を解説!
「気のかかる」は、相手や物事に対して心を配る態度を表現するために使われる言葉です。
例えば、友人が病気で入院している場合、その友人の安否を心配し、定期的に連絡を取ったり、お見舞いに行ったりすると「友人のことが気のかかる」と表現することができます。
また、大切な仕事のプレゼンテーションに向けて準備をしている時に、上司が「この資料にもっと気を使ってみてはどうか」とアドバイスをくれる場合にも、「上司は私の成果に気のかかる人だ」と言えます。
「気のかかる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「気のかかる」という言葉の成り立ちは、日本語の表現や感覚に由来しています。
「気」は、人間の内面や感情、思考を表す言葉であり、「かかる」は、身に起こる、関わるという意味を持ちます。
これらを組み合わせることで、心を配る態度を表す言葉となったのです。
「気のかかる」という言葉の歴史
「気のかかる」という言葉は、古くから使われてきましたが、具体的な歴史は明確には分かっていません。
ただし、日本人が人間関係や他者への思いやりを大切にする文化を持っていることから、「気のかかる」という表現が生まれ、広まってきたと考えられています。
「気のかかる」という言葉についてまとめ
「気のかかる」という言葉は、大切な人や物事に対して心を配る態度を表現するために使われます。
日本語の文化や感覚に由来しており、人々の思いやりの表れともいえる言葉です。
大切な人との関係を築きながら、お互いを気にかけることで、より豊かな人間関係を築いていきましょう。