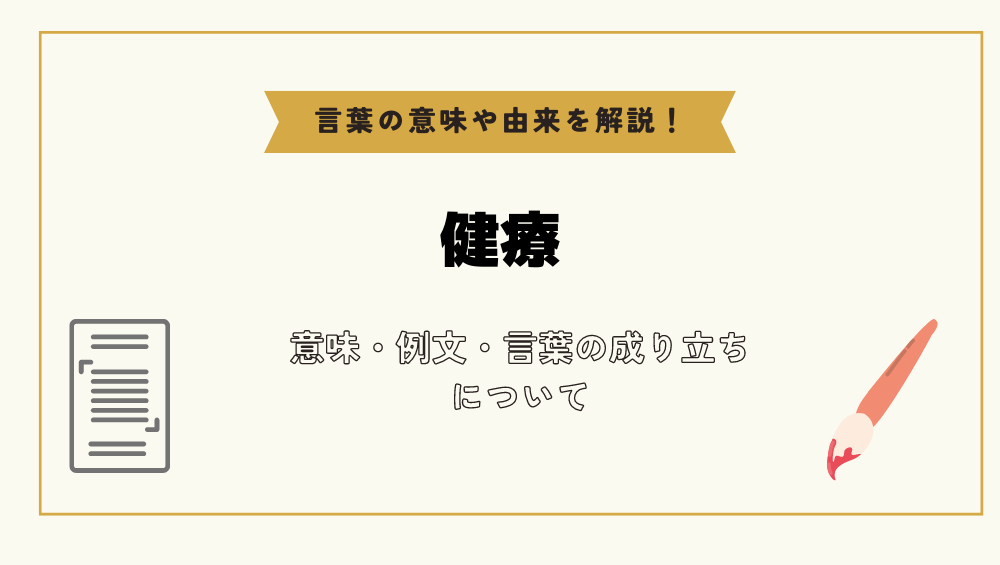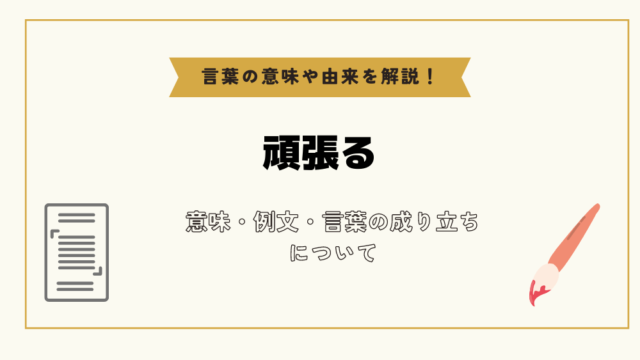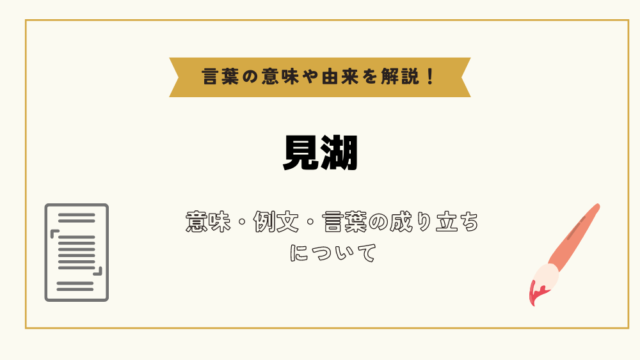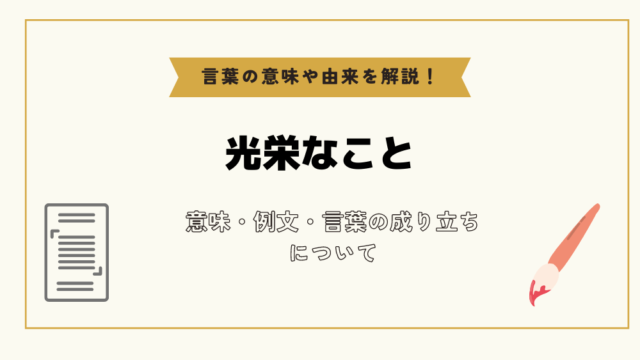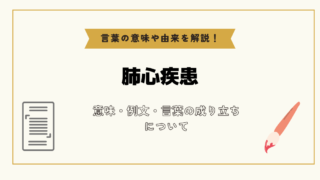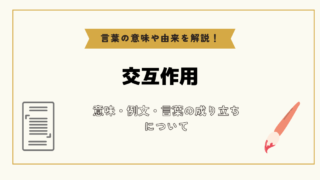Contents
「健療」という言葉の意味を解説!
「健療(けんりょう)」とは、身体や心の病気や障害を治療することを指す言葉です。
日本語の「健康」と「療法」を組み合わせた言葉であり、患者の体調や病状を改善し、健康を回復させることを目的としています。
「健療」という言葉の読み方はなんと読む?
「健療」という言葉は、「けんりょう」と読みます。
漢字の「健」は「けん」と読みますが、「健康」や「健康診断」と同じく、「けんりょう」となります。
正確に読むことで、また意味を理解して使うことが大切です。
「健療」という言葉の使い方や例文を解説!
「健療」という言葉は、主に医療や健康関係の文脈で使われます。
例えば、病院やクリニックで患者の健康を回復させるために行われる治療や手術、薬物療法などが「健療」と呼ばれます。
また、心の健康を回復させるための心理療法やカウンセリングも「健療」と言えます。
例文としては、「彼女は精神的な悩みを抱えていたので、専門の心療内科で健療を受けています」というように使うことができます。
「健療」という言葉の成り立ちや由来について解説
「健療」という言葉は、日本語の「健康」と「療法」を組み合わせた造語です。
日本語における医療の概念や病気の治療方法は、古くから存在しており、それがさらに発展した結果、「健療」という言葉が生まれました。
「健療」の由来には具体的な情報はありませんが、「健康」と「療法」という言葉が組み合わさったことで、治療の道具や方法を含んだ意味が生まれたと考えられます。
「健療」という言葉の歴史
「健療」という言葉の使用が始まった具体的な時期や文献は不明ですが、日本の医療や健康に関する文化や歴史は古く、古代から医療行為が行われてきました。
江戸時代には、一般的な病気や怪我の治療を行う庶民のための「町医者」が存在し、それが近代の医療体制に繋がっていきました。
そして現代では、医療技術の発展や医療制度の整備により「健療」という言葉が広く使われるようになりました。
「健療」という言葉についてまとめ
「健療」という言葉は身体や心の病気や障害を治療することを指し、主に医療や健康関係の文脈で使用されます。
漢字の「健」は「けん」と読み、「健康」や「健康診断」と同じく、「けんりょう」と読むことができます。
「健療」という言葉の由来は明確ではありませんが、日本の医療文化の中で生まれたものであると考えられます。
日本の医療の歴史は古く、現代では医療技術の進歩により「健療」という言葉が一般的に使われるようになりました。