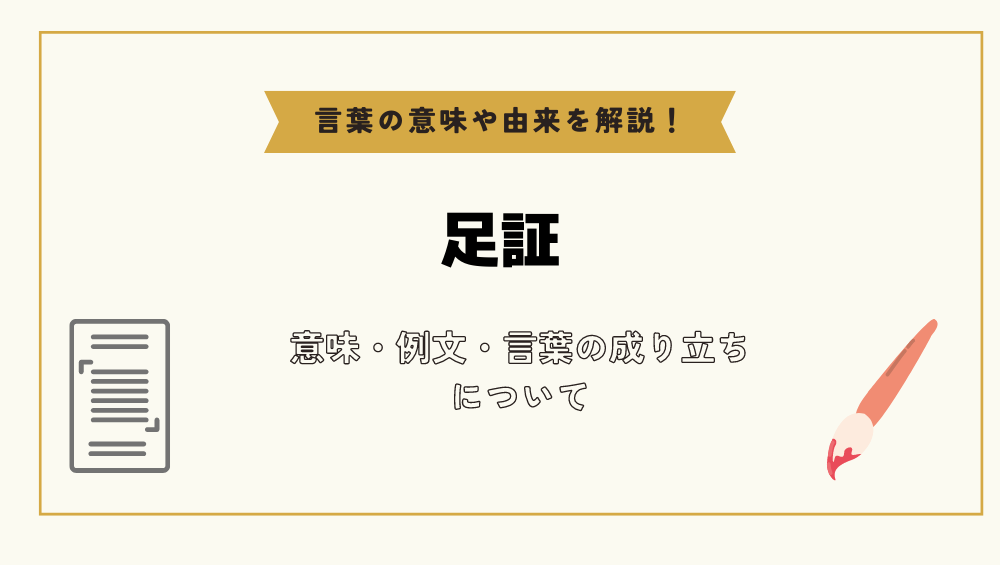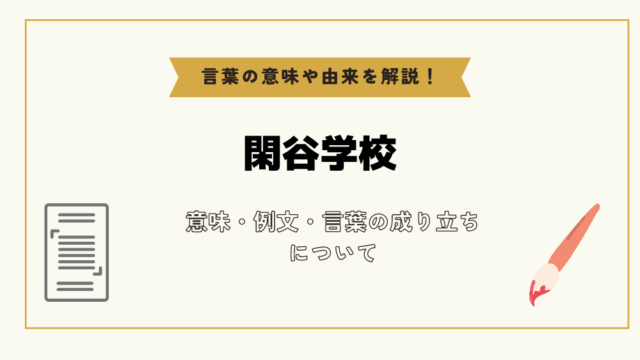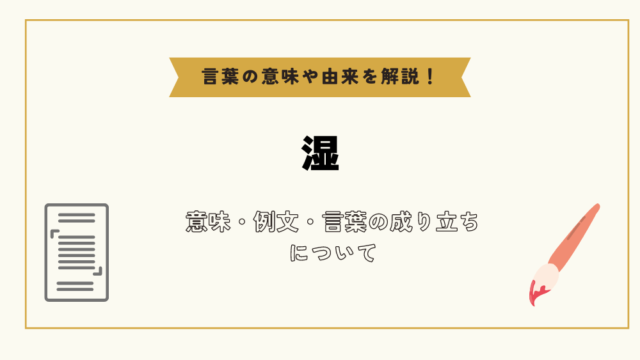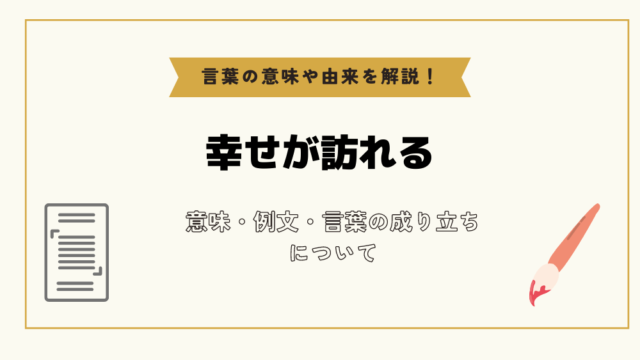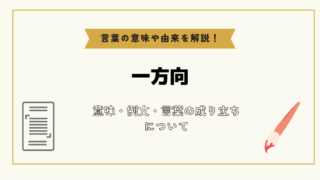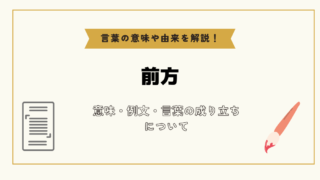Contents
「足証」という言葉の意味を解説!
。
「足証」という言葉は、日本語の中で使われる表現の一つです。
この言葉は「足し証拠」とも読まれ、何かの証拠や根拠を追加することを指します。
例えば、ある事件の真相を明らかにするために、新たな証拠を見つけ出した場合などに使われることがあります。
。
この言葉は、日本語の中で珍しい表現ではありませんが、普段の会話や文章の中ではあまり使われることはありません。
しかし、法律や事件の調査など、特定の分野で使われることが多いです。
「足証」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「足証」という言葉は、「たっしょう」と読みます。
2つの文字それぞれを読むと、「たりしょう」となりますが、合わせて「たっしょう」となります。
この読み方は、一般的に広く使われているものです。
「足証」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「足証」という言葉は、主に法律の分野や事件の調査などで使われます。
例えば、ある事件の真相を究明するために、新たな証拠が必要な場合に使えます。
「足証」という言葉を使う例文としては、「その証言には矛盾があったため、新たな足証を見つけなければならない」といった文が挙げられます。
「足証」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「足証」という言葉は、その成り立ちについては特定の由来はありません。
個々の字の意味や音読みを組み合わせて成り立っています。
ただし、「足し証拠」という意味合いや、追加することを表す「足す」などから派生していると考えられます。
「足証」という言葉の歴史
。
「足証」という言葉は、古くから使われているわけではありません。
比較的新しい言葉と言えるでしょう。
ただし、具体的な起源や初出の文献などは不明です。
言葉の使用が一部の特定の分野に限られているため、広く知られているとは言い難いです。
「足証」という言葉についてまとめ
。
「足証」という言葉は、証拠や根拠を追加することを意味する表現です。
法律の分野や事件の調査などで使われることが多く、あまり一般的な言葉ではありません。
その成り立ちや由来は特定のものはなく、新しい言葉と言えます。
しかし、一部の特定の分野ではよく使われる言葉です。