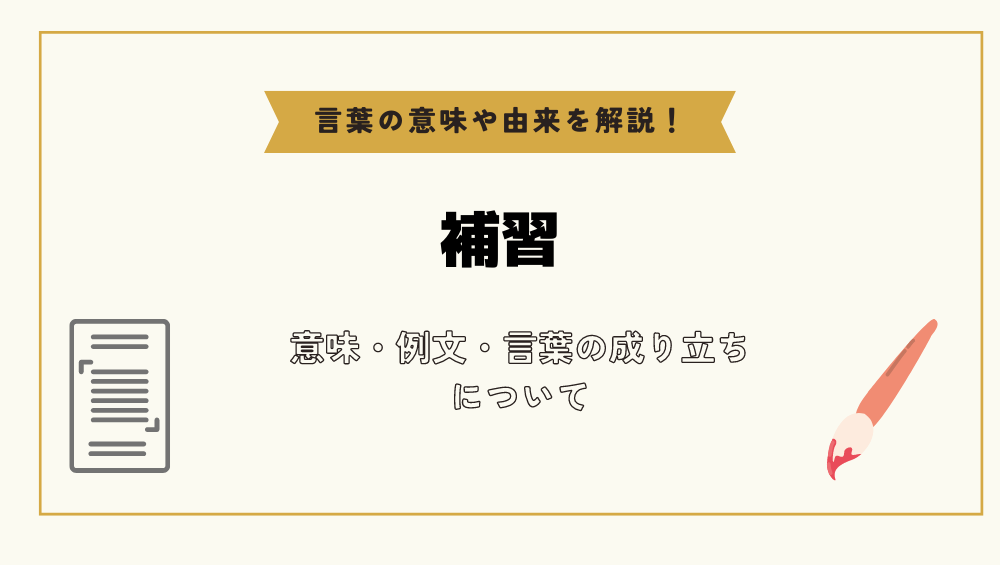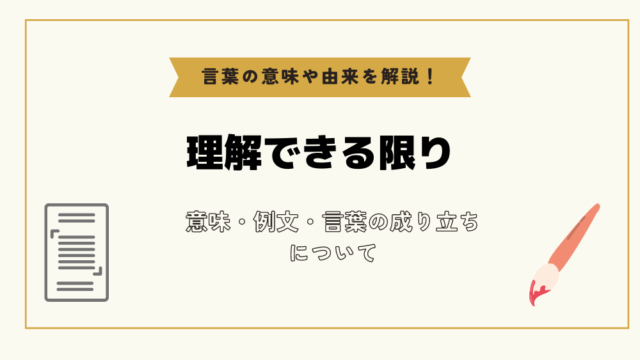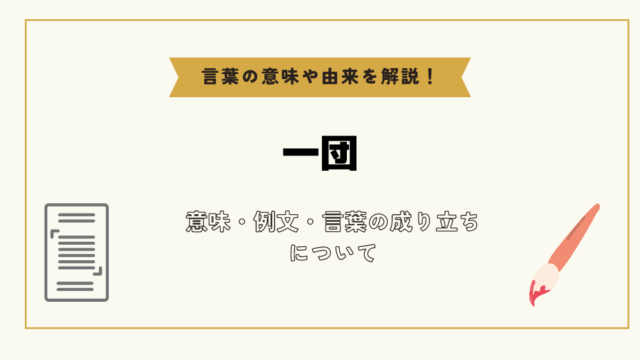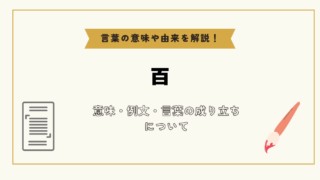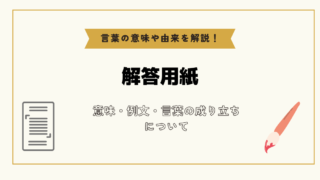Contents
「補習」という言葉の意味を解説!
「補習」とは、学校の授業で学びきれなかった内容や理解ができなかった箇所を補うための追加の教育です。
もともと学校の授業においては、時間的制約や生徒の理解度の差などから、全ての内容を完璧に習得することは難しい場合もあります。
そのため、学校の補習授業や塾などにおいて、一度の授業では理解が難しい箇所や課題に取り組むことができます。
補習を受けることで、学校の授業での理解度を向上させることができます。
「補習」という言葉の読み方はなんと読む?
「補習」は、「ほしゅう」と読みます。
「ほ」は「ぼ」に似ており、次に「しゅう」となります。
このように、2つの音から成り立つ言葉です。
読み方を知ることで、正確に意思疎通を図ることができます。
「補習」という言葉の使い方や例文を解説!
「補習」という言葉は、学校や教育機関でよく使われます。
例えば、「数学の補習を受けて、苦手な計算問題に取り組むことができました」というように使われます。
また、「補習授業には毎週水曜日の午後に参加しています」といった具体的な日時や頻度を表現することもあります。
使い方や文脈によって、ニュアンスが異なることに注意しましょう。
「補習」という言葉の成り立ちや由来について解説
「補習」という言葉は、漢字2文字で表され、それぞれの意味を持っています。
「補」はもともと「欠けている箇所を埋める」という意味があり、「習」は「学ぶ」という意味です。
この言葉が結びついて「補習」となり、学校の授業で理解が難しい箇所を学ぶことを意味するようになりました。
補習の本来の目的である、知識や理解の補完という意味が込められています。
「補習」という言葉の歴史
「補習」という言葉は古くから存在しており、学校教育の一環として行われてきました。
日本では江戸時代から補習が行われ、学問を深めるための場として重要な役割を果たしてきました。
明治時代になると、洋式学校の普及と共に補習の需要も高まり、多くの学生が補習を利用するようになりました。
現代でも補習は、学校教育の一環として広く行われており、学生たちの学習をサポートしています。
「補習」という言葉についてまとめ
「補習」という言葉は、学校や教育機関でよく使われ、学生の学習を補完するための教育です。
学校の授業で理解が難しい箇所を補うだけでなく、自己学習の一環としても利用されています。
正しく「補習」を行うことで、学校の授業や個別の学習目標の達成に役立つことが期待されています。
効果的な補習の受け方や活用法を知ることで、自身の学習をより効果的に進めることができるでしょう。