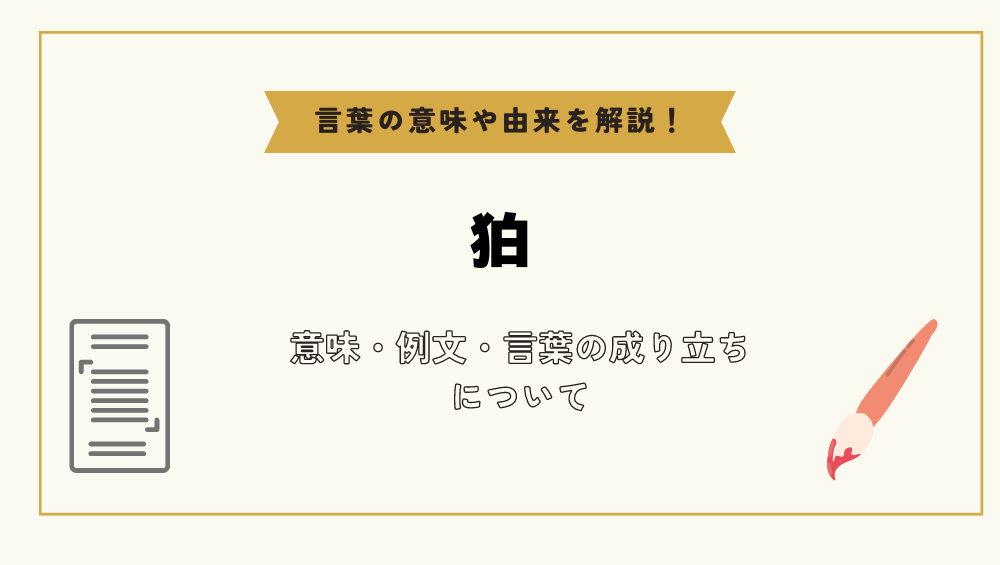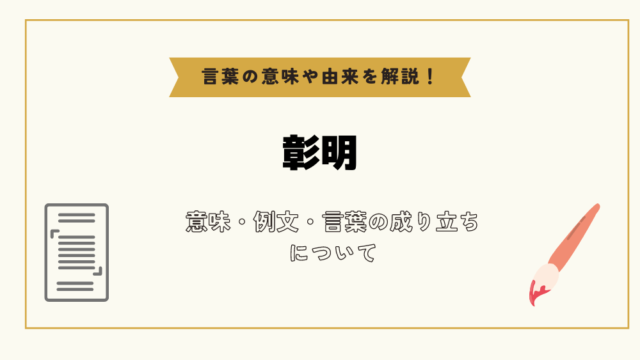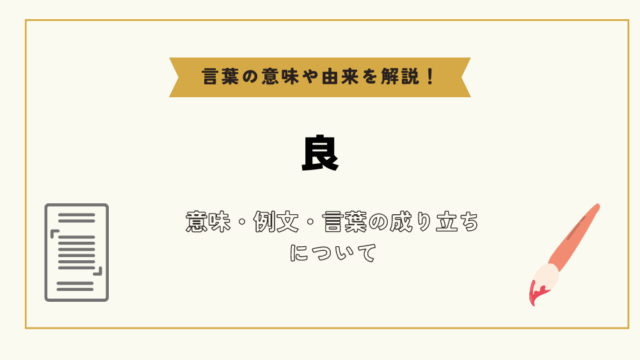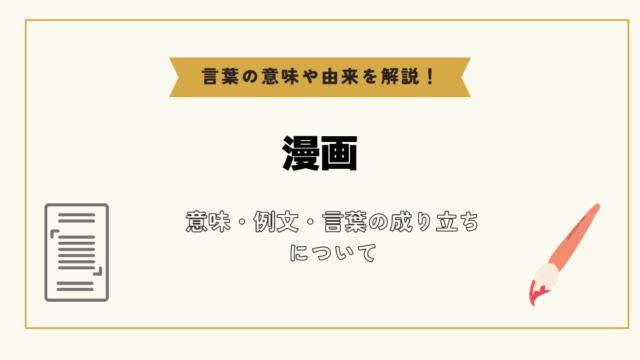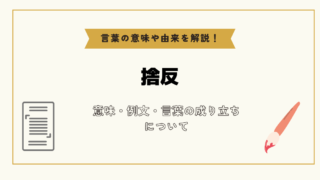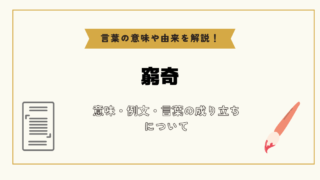Contents
「狛」という言葉の意味を解説!
狛(こま)という言葉は、神社や寺院などの境内に設置されている、獅子のような獣の像を指します。
この像は狛犬(こまいぬ)とも呼ばれ、玄関や門の両側に置かれていることが一般的です。
狛は、厄除けや魔除けの役割を果たすと信じられており、その姿勢や表情から威厳と力強さを感じることができます。
「狛」という言葉の読み方はなんと読む?
「狛」という言葉は、「こま」と読みます。
日本語の平仮名による読み方ですので、簡単に覚えることができます。
狛犬(こまいぬ)という表現でも、同じく「こまいぬ」と読むことになります。
「狛」という言葉の使い方や例文を解説!
「狛」という言葉は、主に神社や寺院の境内における獅子の像を指しますが、一般的な会話でも使用することができます。
例えば、「狛犬の見立てに工夫を凝らす」という言い回しでは、物事を守り抜くために頑張る様子を表現しています。
「狛」という言葉の成り立ちや由来について解説
「狛」という言葉は、古事記や日本書紀にも登場する響きの伝統的な意味を持っています。
その由来については諸説ありますが、獅子のような姿勢から神聖な存在とされ、神力を具現化する役割を果たすと考えられています。
「狛」という言葉の歴史
「狛」という言葉は、古代から存在しており、主に宗教的な場所で見られるものとして受け継がれてきました。
特に狛犬は、守護神としての役割を果たすと信じられており、日本の伝統文化において重要な存在とされてきました。
「狛」という言葉についてまとめ
「狛」という言葉は、神社や寺院などの境内に設置されている獅子のような像を指します。
この像は狛犬とも呼ばれ、厄除けや魔除けの役割を果たすとされています。
読み方は「こま」であり、日本の伝統文化において重要な存在です。