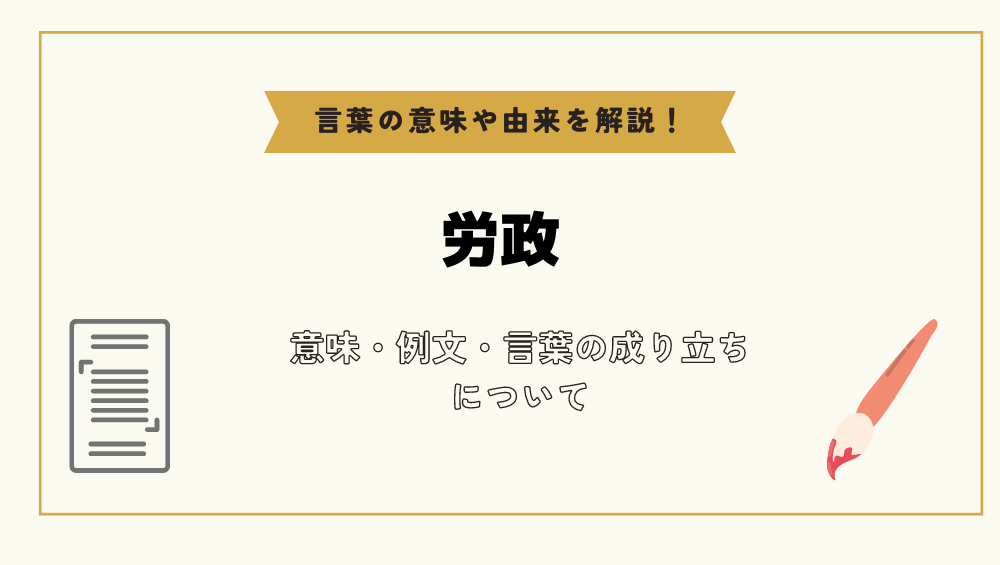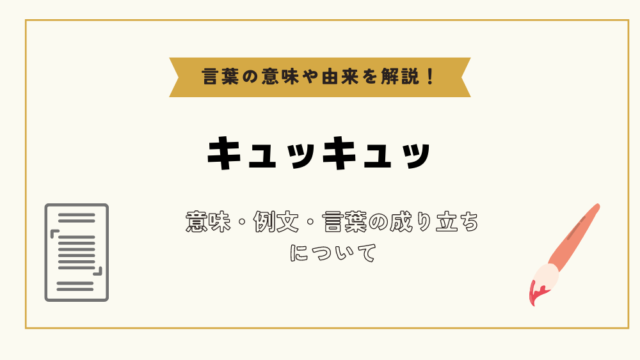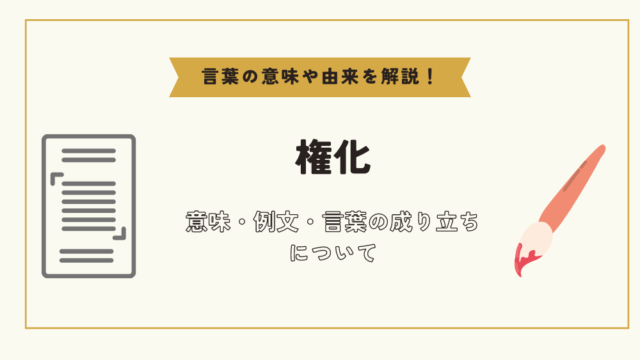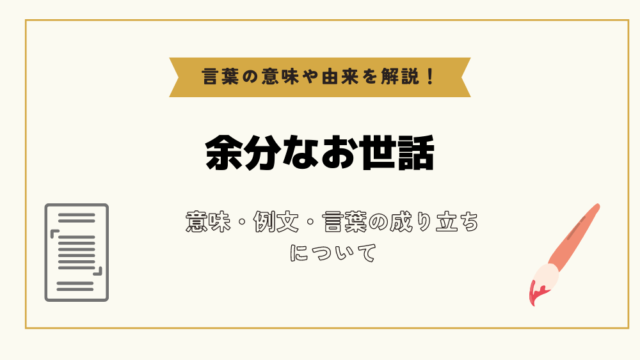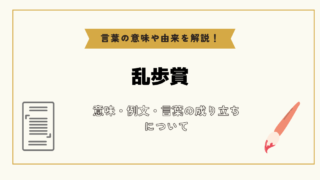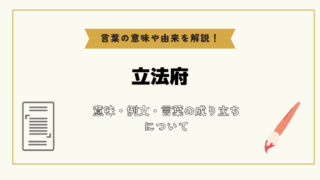Contents
「労政」という言葉の意味を解説!
労政(ろうせい)とは、労働者の福祉と労働環境を管理するための政策や制度を指します。
この言葉は、労働に関わる法律や規則を作ることや、労働条件の改善、社会保障の整備など、労働者の利益を守るための政府の取り組みを表現します。
労政は、労働者の権利や安全、健康を守り、適正な労働環境を確保することを目的としています。また、労政は労働者を支援し、社会的なバランスを維持するための政策も含まれます。
労政は、労働法や労働組合、労働相関の制度の整備などが関わっており、労働者の権利や福祉を守るために不可欠な存在と言えます。
「労政」という言葉の読み方はなんと読む?
「労政」という言葉は、「ろうせい」と読みます。
これは、日本語の読み方で一般的な発音です。
「労政」という言葉の使い方や例文を解説!
「労政」という言葉は、政府や企業が労働者の権利や福祉を守るための政策や制度を指すことが一般的です。
例文1:我が国では、労政策の一環として労働基準法が制定され、労働者の最低賃金や労働時間の規制が行われています。
例文2:この企業は、労政に対する取り組みが優れており、労働者の待遇や労働環境が非常に良いと評価されています。
「労政」という言葉の成り立ちや由来について解説
「労政」という言葉は、仏教の教えに由来しています。
仏教では、働くことや労働者の福祉を重んじ、社会的なバランスを大切にする思想があります。
そのため、日本で労政という言葉が使われるようになったのは、江戸時代以降の近代化の時期です。労働者の権利が制度化されるにつれて、労政という言葉も広まっていきました。
労政は、現代の社会においても労働者の福祉を守るための重要な概念として位置づけられており、労働政策の一環として取り組まれています。
「労政」という言葉の歴史
「労政」という言葉は、日本の社会の発展とともに歴史を重ねてきました。
江戸時代には、農民や町人の労働力が重要視されてきましたが、労働者の権利や福祉についてはあまり注目されていませんでした。
明治時代以降、西洋の労働政策や労働運動の影響を受けて、労政に関する法律や制度の整備が進められました。
現代では、労働基準法をはじめとする労働政策が整備され、労働者の権利や福祉を保護するための法的な枠組みが整備されています。
「労政」という言葉についてまとめ
労政は、労働者の福祉と労働環境を管理するための政策や制度を指す言葉です。
労働者の権利や安全、健康を守り、適正な労働環境を確保することが目的とされています。
労政の施策としては、労働法の整備や労働組合の活動が重要な役割を果たしています。
労政は、労働者の利益を守りながら社会的なバランスを維持し、健全な労働環境を実現するための重要な政策です。