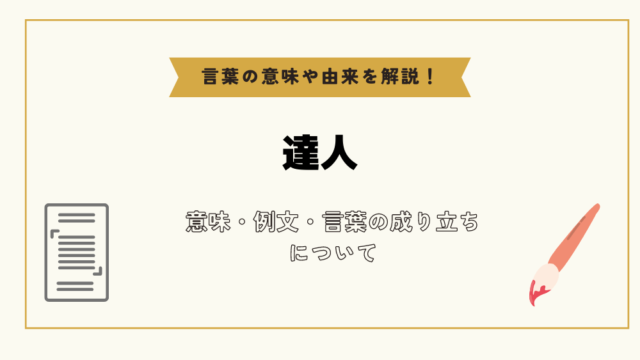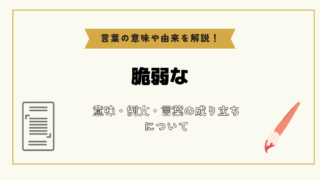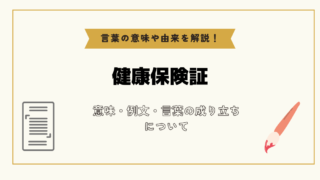Contents
「緩和ケア」という言葉の意味を解説!
「緩和ケア」とは、重病や末期疾患を患っている患者さんに対して、痛みや苦痛を軽減し、心身の負担を軽くする医療やケアのことを指します。
緩和ケアは、患者さんがその病状による苦悩を最小限に抑え、生活の質を向上させることを目指しています。
症状緩和や心理的なサポート、家族のサポートなどが含まれ、患者さんが生活をしやすくするために様々な支援が行われます。
緩和ケアは、医療の中でも特にチームで取り組まれることが多く、医師、看護師、薬剤師、臨床心理士など、さまざまな専門職が連携して行われます。
患者さんと家族のニーズに合わせたケアが提供されることが重要です。
「緩和ケア」という言葉の読み方はなんと読む?
「緩和ケア」という言葉は、「かんわケア」と読みます。
「緩和」は「かんわ」と読み、医療やケアによって症状を軽減することを意味します。
この言葉は日本だけでなく、世界的にも使われています。
「緩和ケア」という言葉の使い方や例文を解説!
「緩和ケア」という言葉は、医療やケアの現場で広く使われています。
例えば、緩和ケアの専門家が患者さんの痛みの緩和を担当したり、緩和ケアチームが家族への支援や心理的なケアを提供したりすることがあります。
また、実際の病院や施設の名前にも「緩和ケアセンター」や「緩和ケア病棟」といった名称が使われています。
「緩和ケア」という言葉の成り立ちや由来について解説
「緩和ケア」という言葉は、英語の「palliative care」を日本語に訳したものです。
「palliative」はラテン語の「pallium(マント)」に由来し、心身の痛みや苦痛をやわらげることを意味します。
これが「緩和」の語源となっています。
日本では1980年代に導入され、現在はがん疾患だけでなく、末期の肝疾患や心臓病など他の疾患にも適用されるようになっています。
「緩和ケア」という言葉の歴史
「緩和ケア」という言葉は、1950年代からアメリカ合衆国で使われるようになりました。
当初は、末期がん患者の痛みを軽減するために行われる治療やケアに限定されていましたが、次第に概念が広がり、より幅広い状態や疾患に対しても適用されるようになりました。
現在では、国や地域によって緩和ケアの枠組みや提供方法が異なるものの、その重要性が広く認識されています。
「緩和ケア」という言葉についてまとめ
「緩和ケア」という言葉は、患者さんが重病や末期疾患による苦痛から解放され、心身の負担を軽くする医療やケアのことを指します。
この言葉は、「かんわケア」と読みます。
病院や施設の名前にも使われることがあります。
緩和ケアの概念はアメリカで生まれ、次第に世界中に広がりました。
現在では、多くの国で提供されている大切な医療やケアの一つです。