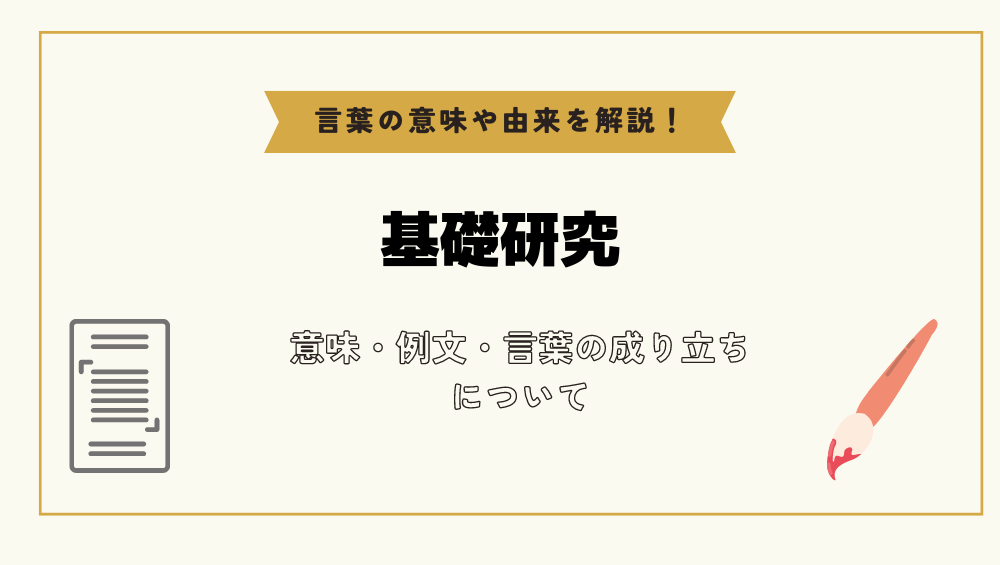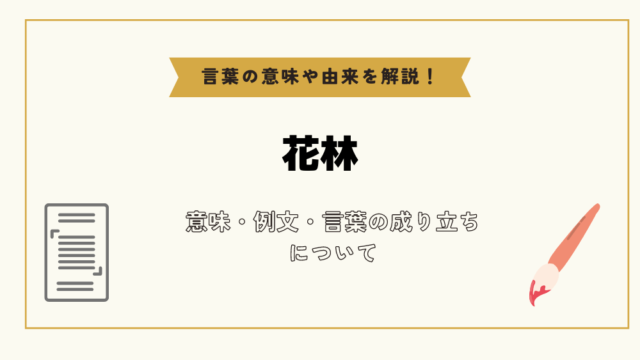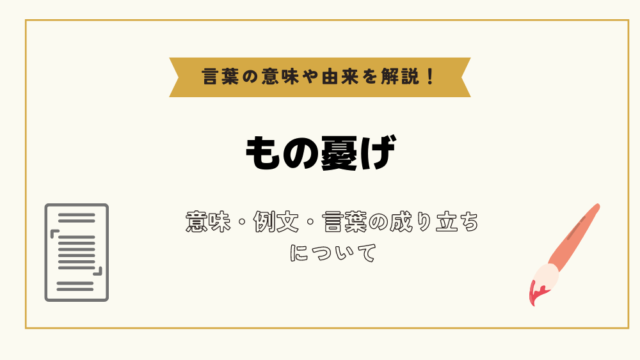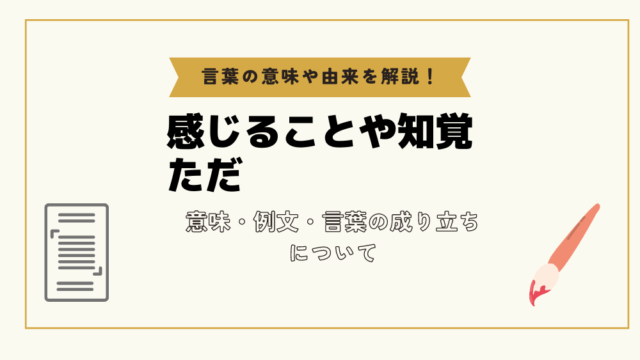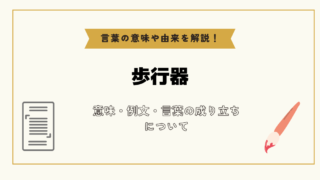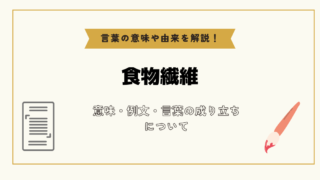Contents
「基礎研究」という言葉の意味を解説!
基礎研究とは、学問や科学技術の分野において、新たな知識や理論、概念などを探求するための研究のことを指します。具体的には、既存の知識を積み重ねたり、新たな仮説を立てたりすることで、その分野の基盤を築くための研究活動を指します。
基礎研究の目的は、応用に直結する新たな発見や技術の開発などではなく、あくまで学問や科学技術の進展を図ることです。そのため、結果的には応用研究や実用化されることもありますが、基礎研究自体は純粋な学術的な興味や探究心から行われるものです。
基礎研究は学術研究や大学などの研究機関で行われることが一般的ですが、特に科学技術分野では産業界との連携も進んでおり、新たな発見や知識の応用によって社会の発展に貢献することを目指しています。
「基礎研究」という言葉の読み方はなんと読む?
「基礎研究」という言葉は、「きそけんきゅう」と読みます。これは、それぞれの漢字の読みを組み合わせたものです。
「基礎」という漢字は、「きそ」と読み、基本や根本、土台などの意味があります。「研究」という漢字は、「けんきゅう」と読み、学問や科学の研究活動を指します。
基礎研究は、学問や科学技術の分野での研究を意味しており、その分野の基盤を築くための探究を行うことを表しています。
「基礎研究」という言葉の使い方や例文を解説!
「基礎研究」という言葉は、学問や科学技術の分野で使用されることが多いです。例えば、ある学術論文や研究プロジェクトのテーマが「基礎研究」となっている場合、その研究の目的は新しい知識や理論の発見、さらなる基盤の構築であることが想定されます。
また、企業などでも基礎研究が行われることがあります。例えば、ある技術的な開発のためには、まずその分野の基礎研究が必要であると考えられる場合、それに関連する研究活動を行うことがあります。
「基礎研究」の使い方や例文は、実際の文脈によって異なるため、具体的な場面での使い方を確認することが重要です。
「基礎研究」という言葉の成り立ちや由来について解説
「基礎研究」という言葉の成り立ちや由来について具体的な記録はありませんが、学問や科学技術が発展する中で、新たな知識や理論の発見、基盤の構築の重要性が認識されるようになったことが背景にあると考えられます。
基礎研究は、学問や科学技術の進展を図るために重要な研究活動であり、その成果が応用研究や技術開発につながることも多いです。そのため、学問や科学技術の分野での研究は、「基礎研究」という言葉で広く認識されるようになりました。
現代の社会では、基礎研究と応用研究のバランスや連携が重要視されており、学術研究や産業界との連携が進むなかで、より有益な研究活動を行うことが求められています。
「基礎研究」という言葉の歴史
「基礎研究」という言葉の歴史について具体的な記録はありませんが、学問や科学技術の分野での研究は古くから行われてきました。古代ギリシャや中国などの古代文明においても、哲学や自然科学の研究が行われ、その知識や理論が後世に受け継がれてきました。
近代以降になると、科学技術の急速な進展や学問の発展によって、基礎研究の重要性がさらに認識されるようになりました。19世紀のヨーロッパやアメリカなどでは、大学や研究機関での科学研究が活発化し、学術論文や専門書が増えていきました。
そして、現代でも基礎研究は学術研究や技術開発の基盤となっており、学問や科学技術の進展に大きな貢献をしています。
「基礎研究」という言葉についてまとめ
「基礎研究」という言葉は、学問や科学技術の分野で使用される重要な用語です。基礎研究は、新たな知識や理論、概念などを探求するための研究であり、その分野の基盤を築くことを目指しています。
基礎研究は、学問や科学技術の進展を図るために行われる重要な研究活動であり、その成果は応用研究や技術開発につながることもあります。
基礎研究の歴史や由来については詳しい記録はありませんが、学問や科学技術の発展とともにその重要性が認識されるようになったと考えられます。
現代の社会では、基礎研究と応用研究のバランスや連携が求められており、学術研究や産業界との連携が進むなかで、より有益な研究活動を行うことが重要です。