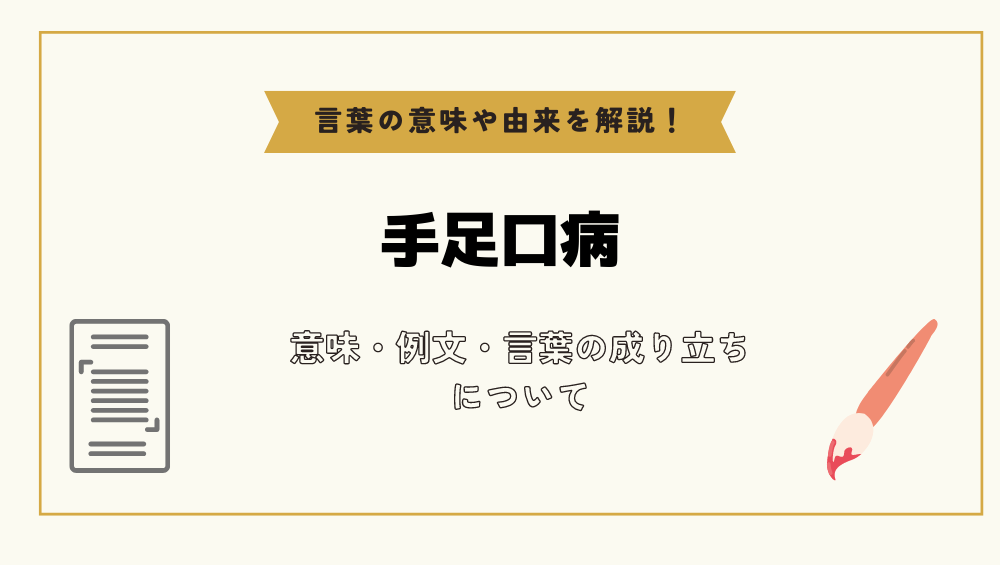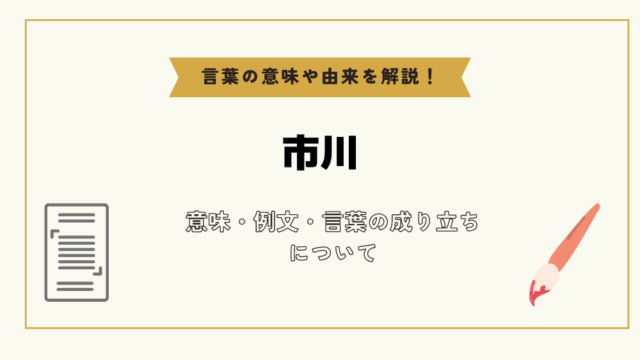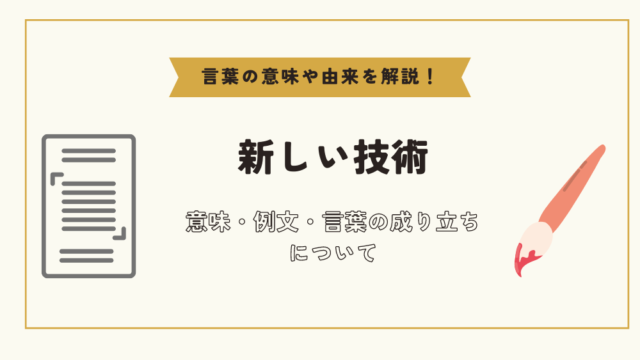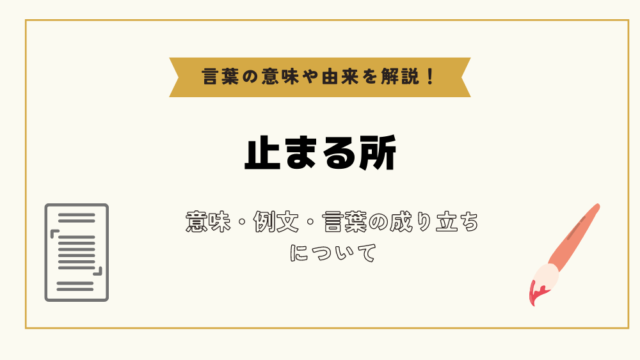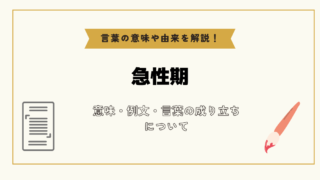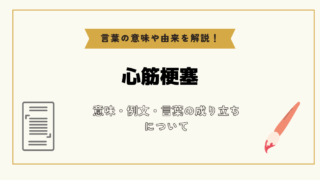Contents
「手足口病」という言葉の意味を解説!
「手足口病」とは、ウイルス感染によって引き起こされる感染症の一つです。
この病気は、主に乳幼児や幼児に発症しやすく、手や足、口の中などに発疹や口内炎が現れる症状が特徴的です。
「手足口病」の読み方はなんと読む?
「手足口病」は、「てあしくちびょう」と読みます。
この読み方は、日本の標準的な読み方です。
「手足口病」という言葉の使い方や例文を解説!
「手足口病」という言葉は、主に医療分野や子育て関係の文脈で使用されます。
たとえば、「今日の診察で、子供が手足口病と診断されました」というように使うことができます。
「手足口病」という言葉の成り立ちや由来について解説
「手足口病」という言葉は、その症状の特徴から名付けられました。
この病気では、手のひらや足の裏、さらには口の中に発疹や口内炎が現れることがあります。
そのため、このような名称が付けられたと考えられています。
「手足口病」という言葉の歴史
「手足口病」は、1969年に初めて報告されました。
その後、世界各地で感染が広がり、特にアジア地域では発症件数が増加しています。
現在でも、定期的に感染が報告され、予防や対策が重要視されています。
「手足口病」という言葉についてまとめ
「手足口病」という言葉は、乳幼児や幼児によく見られる感染症であり、手や足、口の中に発疹や口内炎が現れます。
読み方は「てあしくちびょう」と言い、医療分野や子育て関係で使用されることがあります。
この病気は1969年に報告され、現在も感染が広がっているため予防が重要です。