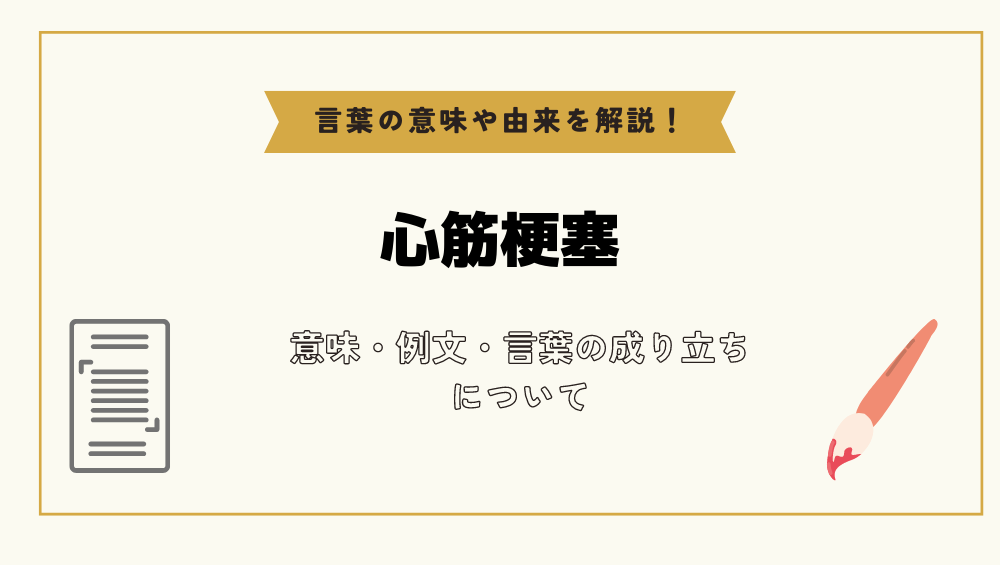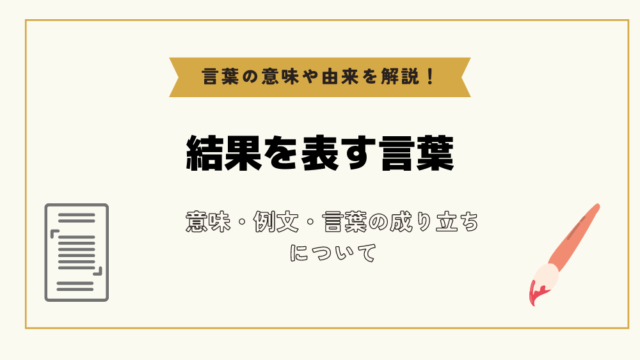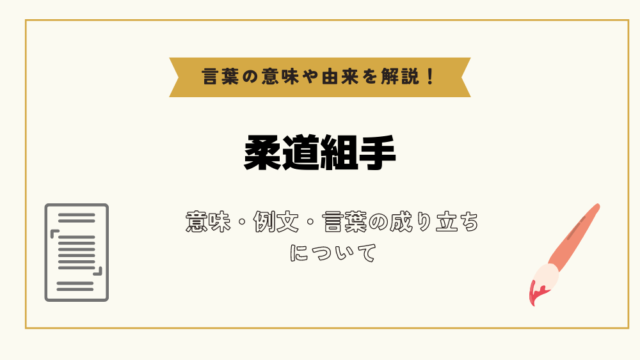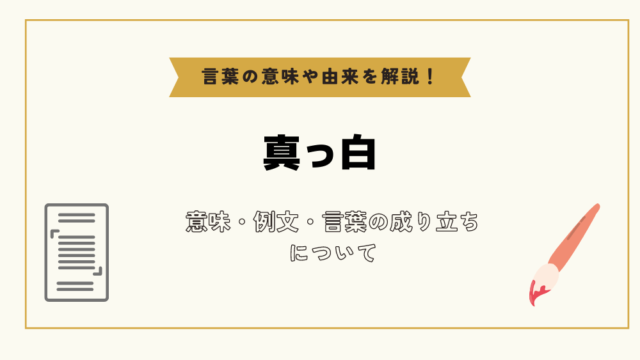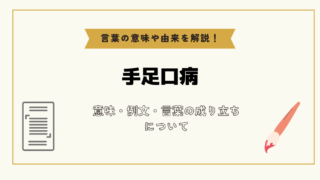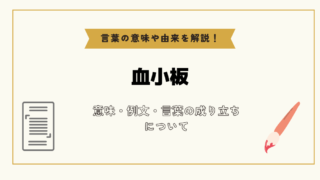Contents
「心筋梗塞」という言葉の意味を解説!
心筋梗塞は、心臓の筋肉である心筋に血液が行き届かなくなる病気です。
心筋は酸素や栄養を血液により供給されていますが、冠動脈が詰まってしまうことで血流が阻害され、心筋が酸素不足になることが原因です。
この状態が続くと心筋が障害を受け、場合によっては死亡してしまうこともあります。
「心筋梗塞」の読み方はなんと読む?
「心筋梗塞」は、「しんきんこうそく」と読みます。
日本人にとって馴染みのある病名ですが、読み方は少し難しいかもしれません。
しかし、この読み方を知ることで医師や専門家とのコミュニケーションがスムーズになるでしょう。
「心筋梗塞」という言葉の使い方や例文を解説!
「心筋梗塞」という言葉は、医学の分野でよく使われています。
例えば、「彼は心筋梗塞で倒れた」といった風に使われます。
また、「心筋梗塞の早期発見が重要です」といったように、予防や早期治療の重要性を伝える際にも使われます。
心筋梗塞は重篤な病気ですので、正しい使い方を覚えておきましょう。
「心筋梗塞」という言葉の成り立ちや由来について解説
「心筋梗塞」という言葉は、心筋(しんきん)という心臓の筋肉が梗塞(こうそく)という状態になることを表しています。
心筋が血液の流れが滞り、酸素と栄養を受け取れなくなる状態を指します。
梗塞とは、一般的に血液の流れが止まることを指し、心筋梗塞もその一例です。
「心筋梗塞」という言葉の歴史
「心筋梗塞」という言葉は、医学の分野で用いられてきた比較的新しい言葉です。
心臓病や心肺蘇生法の研究が進む中で、心筋梗塞の正確な診断と適切な治療の重要性が明らかになってきました。
そのため、近年では心筋梗塞への関心が高まり、その治療法や予防についての研究も積極的に行われています。
「心筋梗塞」という言葉についてまとめ
心筋梗塞は、心臓の筋肉である心筋に血液が行き届かなくなる病気です。
その結果、心筋が障害を受け、重篤な状態に進行する可能性があります。
心筋梗塞は重要な医学用語であり、正しい読み方や使い方を覚えることが必要です。
早期の発見や適切な治療、予防が重要であり、医療の進歩によってその対策も進んでいます。
心筋梗塞について正しく理解し、健康管理に役立てましょう。