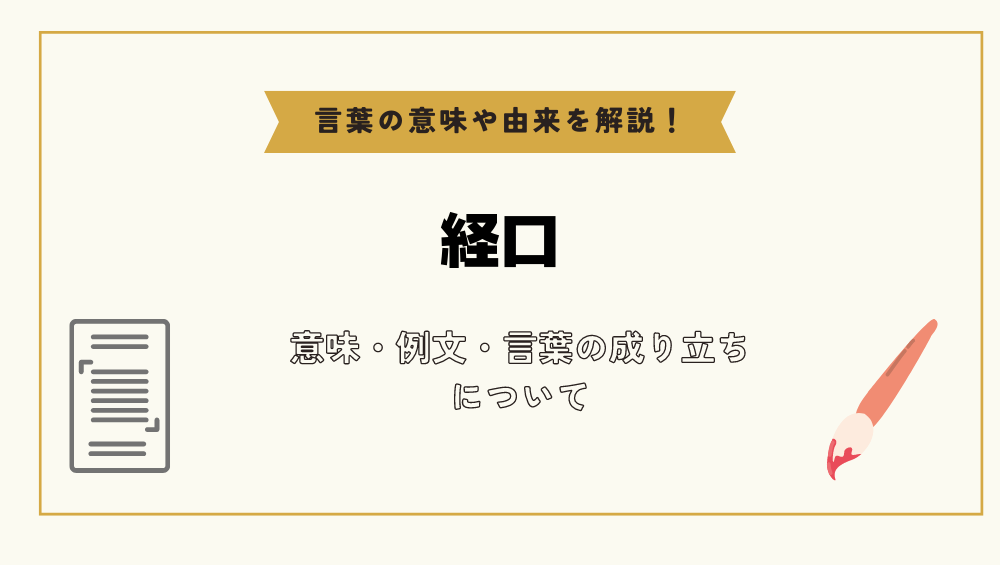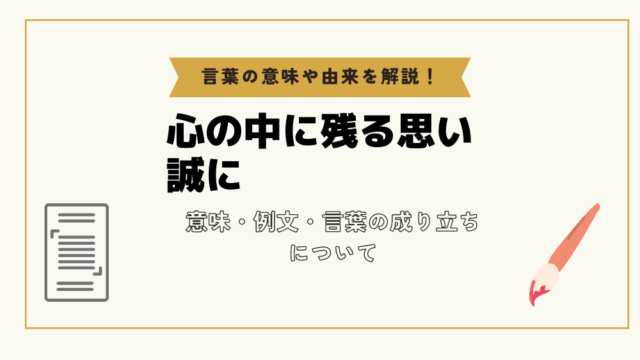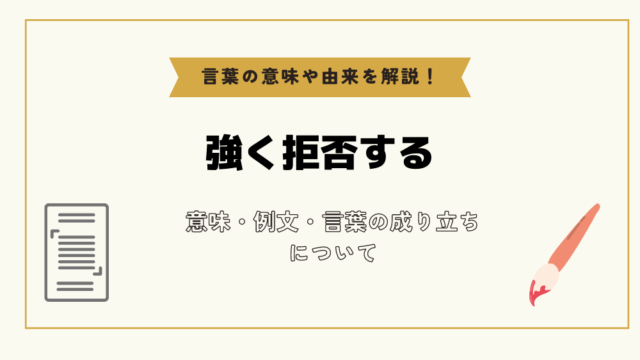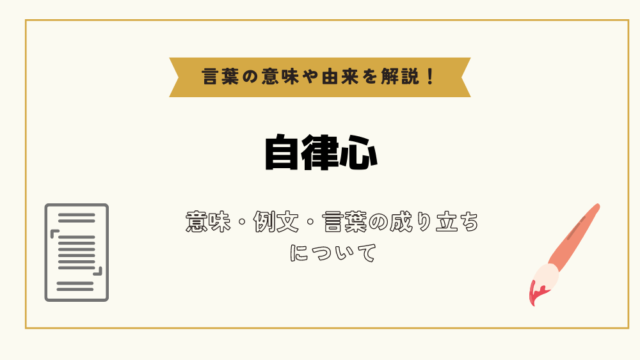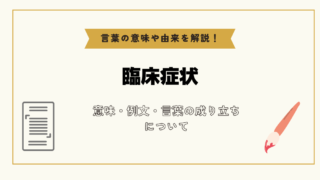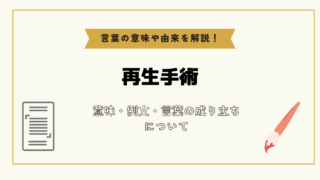経口(けいこう)という言葉の意味を解説!
経口とは、医療や臨床の分野でよく使われる言葉です。この言葉は、「口から摂取する」という意味を持っています。具体的には、薬や栄養補助食品などを飲み込むことや、経口摂取療法としての食事や水分摂取を指します。
例えば、医師から「この薬は経口で摂取してください。」と指示された場合、その薬は錠剤やカプセルの形で用意されていて、患者さんはそれらを水や飲み物と一緒に飲み込むことになります。
経口という言葉は、医療現場だけでなく一般的にも使われています。たとえば、ダイエット方法などで「経口摂取する食品を工夫する」というような使い方もあります。
経口と読まれる
経口という言葉は、そのまま「けいこう」と読みます。漢字の経は「みちびく」「idoru」という読みもありますが、経口という場合は「けいこう」となります。経身(けいしん)や経過(けいか)などと同じく、「けい」の音読みで始まります。
経口の使い方や例文を解説!
経口という言葉は、医療や臨床の場面でよく使われる言葉です。主に「薬を口から摂取する」という意味で使われます。
例えば、病院の薬剤師から「この薬は経口で摂取してください。」と指示された場合、それは患者さんが薬を飲み込むことを意味します。また、食事や水分の摂取方法についても「経口」の言葉を使います。
例えば、「入院中の患者さんは、経口での水分補給がおすすめです。」といったように使われます。経口で摂取することは、体内に必要な栄養素や水分を補給するために非常に大切な手段です。
経口の成り立ちや由来について解説
経口という言葉は、漢字の経と口から成り立っています。経は、「通じる」「通る」という意味を持ち、口は「飲み込む」という意味を持ちます。経口という言葉は、そのまま「口から通じる」という意味を持っています。
この言葉の由来については明確な情報はありませんが、おそらく医療の分野で薬物の摂取方法を表現する際に使われたことが始まりと考えられます。
経口の歴史
経口という言葉は、医療の分野で長い歴史を持っています。日本で医学が発展する以前から、中国やインドなどの東洋医学においても経口摂取が行われていました。
薬物は、昔から飲むことで体内に取り込むことが一般的でした。経口摂取は手軽かつ効果的な方法であり、医療の分野で広く用いられてきました。
近代的な医療の発展とともに、薬物の形状や摂取方法も多様化してきましたが、経口摂取は今でも最も一般的な方法として認知されています。
経口のまとめ
経口は、「口から摂取する」という意味を持つ言葉です。医療の分野で特によく使われ、薬や栄養補助食品などを飲み込む方法を指します。
経口は「けいこう」と読みます。この言葉は、通じる・通る経と、口から飲み込む口から成り立っています。
経口の言葉は、医療や臨床だけでなく一般的な生活でも使われており、体内に栄養や薬物を取り入れるために欠かせない方法とされています。