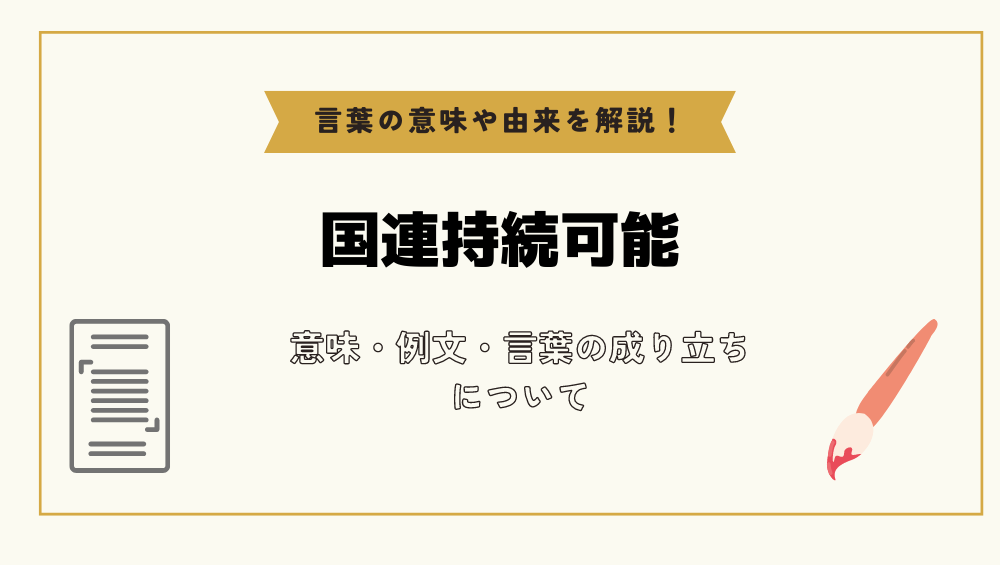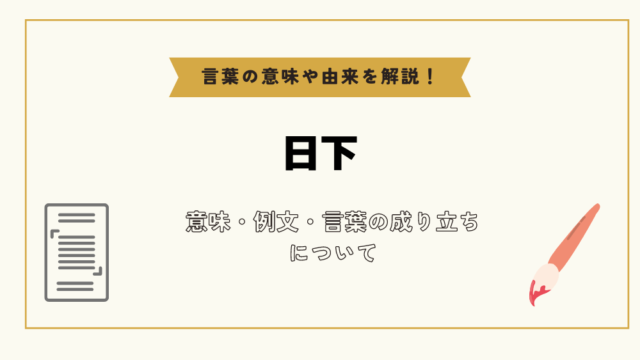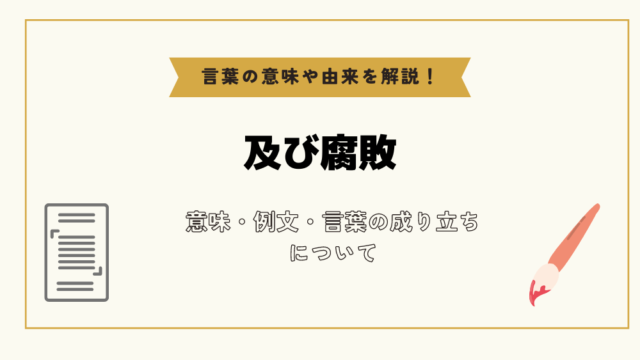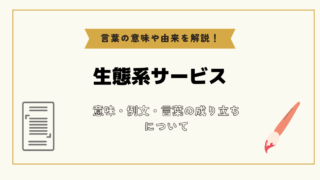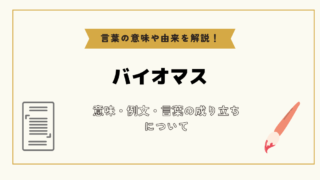Contents
「国連持続可能」という言葉の意味を解説!
「国連持続可能」という言葉は、国際連合(United Nations)が提唱する持続可能な発展を目指す概念のことを指します。
持続可能な発展とは、現在の世代のニーズを満たすだけでなく、将来の世代のニーズも満たすための社会、経済、環境のバランスを取ることを意味します。
具体的には、経済成長と環境保護、社会的な公正などの目標を達成するための枠組みを指しており、国連が世界の国々と協力し、持続可能な未来を築くことを目指しています。
「国連持続可能」という言葉の読み方はなんと読む?
「国連持続可能」という言葉は、「こくれんじぞくかのう」と読みます。
国連は「こくれん」と読み、持続可能は「じぞくかのう」と読むのです。
「国連持続可能」は、国際的な問題に対する解決策を提供し、世界中の人々が協力して持続可能な未来を実現することを意味します。
この言葉には、グローバルな視点と共同作業の精神が込められています。
「国連持続可能」という言葉の使い方や例文を解説!
「国連持続可能」という言葉は、持続可能な発展を目指す取り組みや活動が行われる際に使用されます。
例えば、国連が開催する会議やイベント、プロジェクトの目標や趣旨を表すキーワードとして使われます。
例文:国連持続可能な開発サミットには、世界各国からの代表者が参加し、地球環境の保護や貧困の削減に向けた具体的なアクションプランを立案します。
「国連持続可能」という言葉の成り立ちや由来について解説
「国連持続可能」という言葉の成り立ちは、国際連合が1992年に開催した「地球サミット」で採択された「アジェンダ21」に根差しています。
アジェンダ21は、環境と開発の問題に対する包括的な行動計画であり、持続可能な未来のための具体的なグローバルな取り組みが提案されました。
アジェンダ21の考え方や理念が広まり、その後も国連を中心に様々な国際的な会議や枠組みが生まれ、持続可能な発展への取り組みが進んできました。
こうして「国連持続可能」という言葉が生まれ、世界中で使われるようになりました。
「国連持続可能」という言葉の歴史
「国連持続可能」という言葉の歴史は、1992年の地球サミットでの採択が最初です。
その後、2000年にはミレニアム開発目標が採択され、更に2015年には持続可能な開発目標(SDGs)が採択されました。
SDGsは、2030年までに持続可能な未来を達成するための17の目標からなる枠組みであり、国連が世界の国々と連携して取り組む具体的な行動計画です。
こうした歴史的な出来事を経て、「国連持続可能」という言葉はさらに広く知られるようになりました。
「国連持続可能」という言葉についてまとめ
「国連持続可能」という言葉は、国際連合が提唱する持続可能な発展を目指す概念を表します。
現在の世代のニーズと将来の世代のニーズを満たすためのバランスを取ることが重要であり、経済成長、環境保護、社会的な公正などの目標を追求するための枠組みです。
「国連持続可能」は、国際的な問題に対する解決策を提供し、世界中の人々が協力して持続可能な未来を実現するためのキーワードです。
その歴史や成り立ちからも、その重要性や影響力がうかがえます。