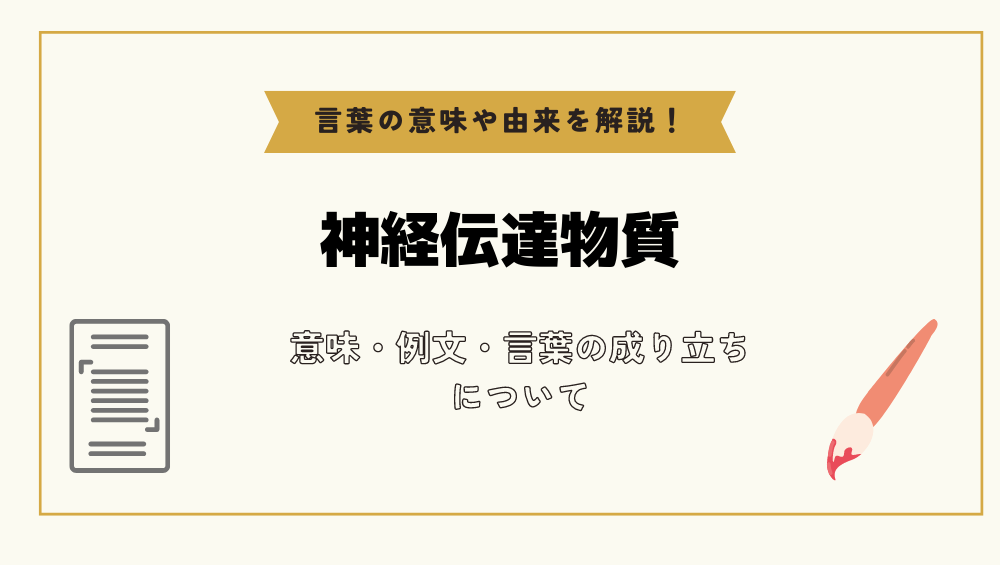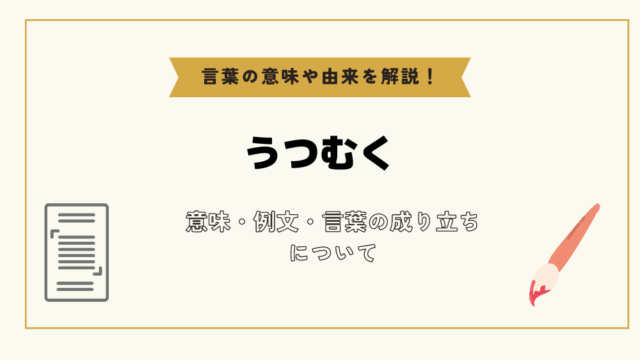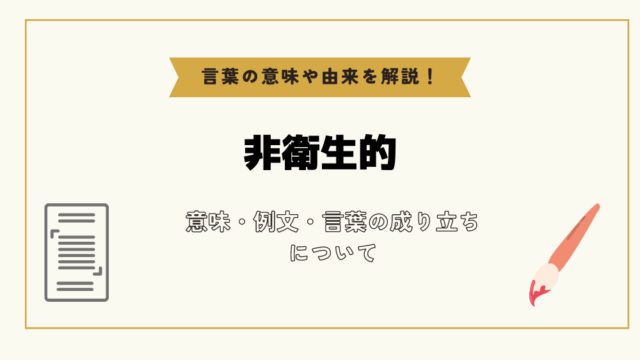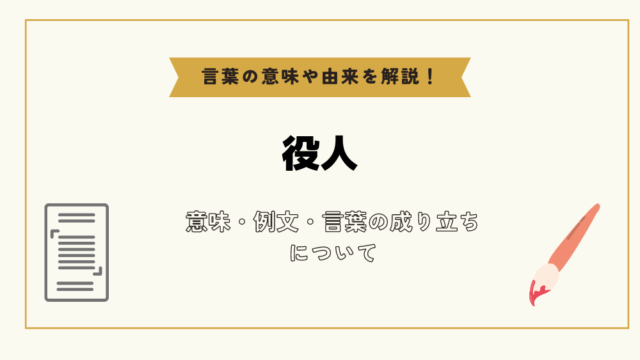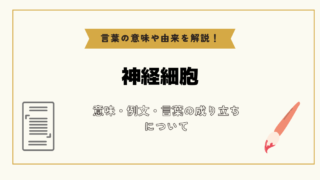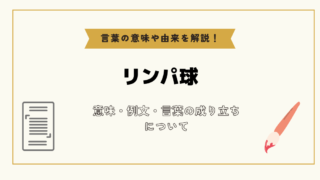Contents
「神経伝達物質」という言葉の意味を解説!
神経伝達物質(しんけいでんたつぶっしつ)とは、神経細胞間で情報を伝えるために働く化学物質のことを指します。神経伝達物質は、体内の様々な神経回路で使用され、神経系の正常な機能に不可欠とされています。
「神経伝達物質」の読み方はなんと読む?
「神経伝達物質」は、日本語の発音に基づいて「しんけいでんたつぶっしつ」と読みます。もちろん、欧米の方々は異なる発音で表現することもありますが、日本ではこの読み方が一般的です。
「神経伝達物質」という言葉の使い方や例文を解説!
「神経伝達物質」という言葉は、主に医学や生物学の文脈で使われます。たとえば、「神経伝達物質のバランスが崩れることで、うつ病の症状が現れる」といった具体的な文脈で使用されます。また、「神経伝達物質の働きを促す薬剤が開発された」といった使い方もあります。
「神経伝達物質」という言葉の成り立ちや由来について解説
「神経伝達物質」という言葉は、神経と伝達物質という言葉の組み合わせから成り立ちます。神経は身体の情報伝達に関与する組織を指し、伝達物質は情報を伝えるための物質を指します。つまり、「神経伝達物質」とは、神経を介して情報を伝えるための物質を指す言葉なのです。
「神経伝達物質」という言葉の歴史
「神経伝達物質」という言葉は、20世紀初頭にドイツの生理学者オットー・ロイトハイムによって提唱されました。彼は神経伝達物質の存在とその働きについて研究し、その功績からノーベル生理学・医学賞を受賞しました。その後、神経伝達物質の研究が進み、現在では多くの神経伝達物質が特定されています。
「神経伝達物質」という言葉についてまとめ
「神経伝達物質」とは、神経細胞間で情報を伝えるために働く化学物質のことです。その正確な発音は「しんけいでんたつぶっしつ」となります。この言葉は医学や生物学の分野で使用され、神経の正常な機能にとって重要な存在です。20世紀初頭に提唱された「神経伝達物質」の研究は、現在の神経科学の発展に大いに貢献しています。