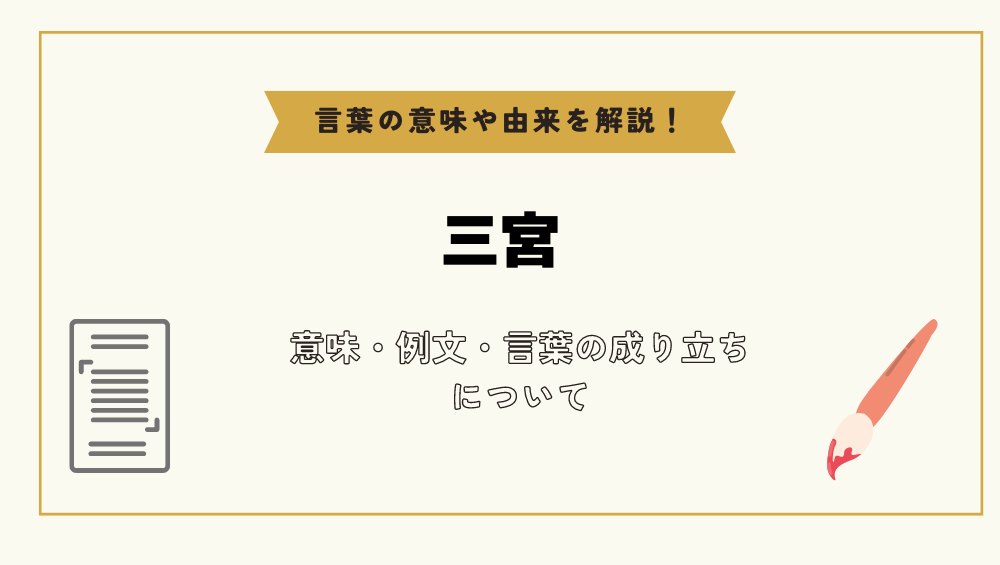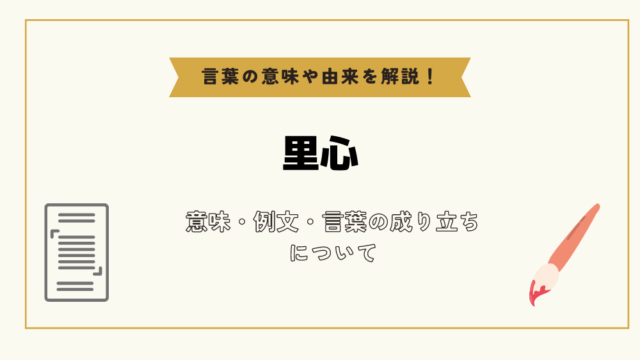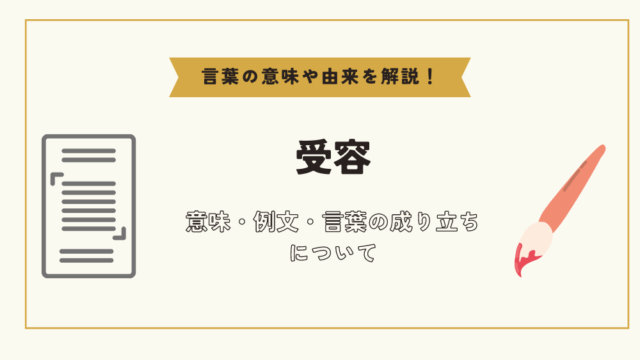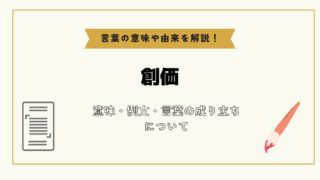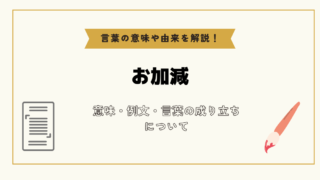Contents
「三宮」という言葉の意味を解説!
「三宮」という言葉の意味は、兵庫県神戸市の地名であることが一般的です。
「三宮」という地名は、その起源について諸説ありますが、主なものは三つの神社(西宮神社、東宮神社、中宮神社)に由来しているとされています。
三宮という地名は、一般には神社の名前に由来する地名であることが知られています。
。
「三宮」の読み方はなんと読む?
「三宮」の読み方は、「さんのみや」と読むことが一般的です。
神戸市の人々は、この読み方を使って地名として呼び合っています。
「三宮」という地名は、読み方によっては他の言葉と似ているため、正しい読み方に注意が必要です。
。
「三宮」という言葉の使い方や例文を解説!
「三宮」という言葉は、神戸市内でよく使用される地名ですが、その他にもさまざまな使い方があります。
例えば、兵庫県外の人々が神戸市を訪れる際に、「三宮の中心地で待ち合わせしましょう」と言うことがあります。
また、神戸市内の人々が自慢の地域を話す際には、「うちのお店は三宮で人気なんですよ」と言うこともあります。
「三宮」という言葉の成り立ちや由来について解説
「三宮」という言葉の成り立ちや由来については、いくつかの説があります。
一つは、神戸市の発展に関係する3つの神社に由来しているという説です。
他にも、三宮という地名は、古代において宮という言葉が三回繰り返されたことによってできたという説や、宮が三つ集まった場所という意味であるという説もあります。
「三宮」という言葉の歴史
「三宮」という言葉の歴史は、神戸市の歴史と深く関わっています。
もともと神戸市は、古代から栄える場所として知られていましたが、明治時代になるとさらなる発展を遂げました。
「三宮」という地名は、神戸市が発展していく中で付けられたと言われています。
その後、三宮は神戸市の主要な商業地域になり、現在まで栄え続けています。
「三宮」という言葉についてまとめ
「三宮」という言葉は、兵庫県神戸市の地名として広く知られています。
この名前の由来は、三つの神社に由来するとされています。
また、「三宮」という言葉は、神戸市内での待ち合わせや自慢の地域の紹介など、さまざまな場面で使用されます。
「三宮」という地名は、神戸市の歴史とも深く結びついており、地域の象徴となっています。
。