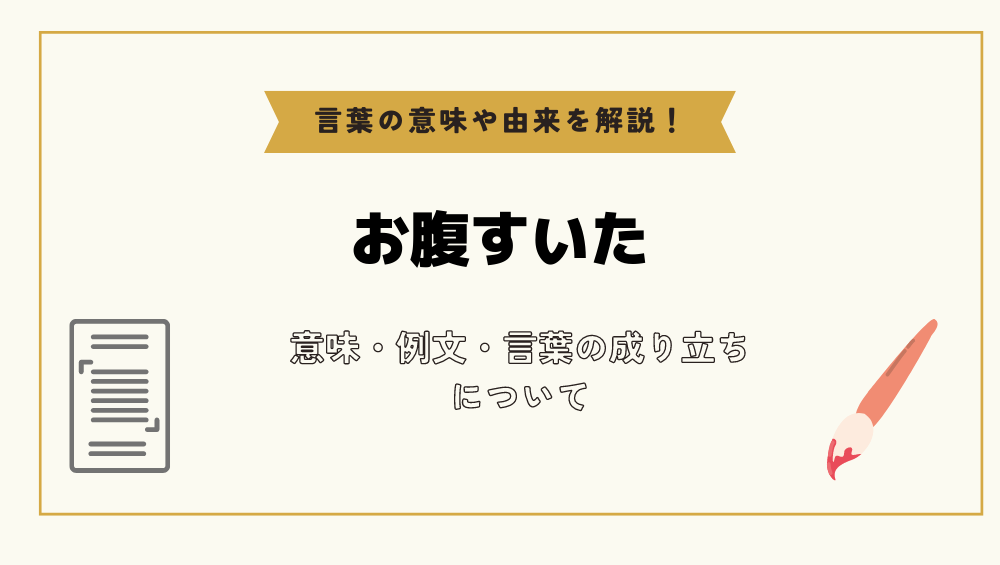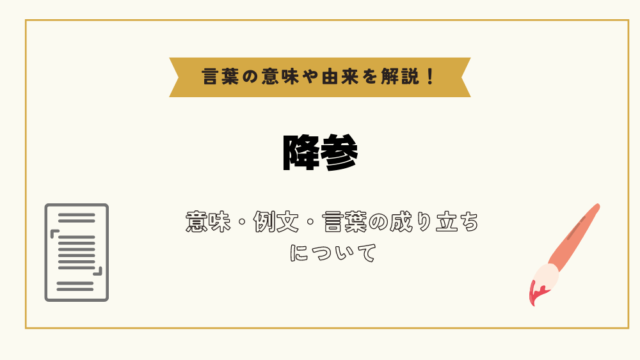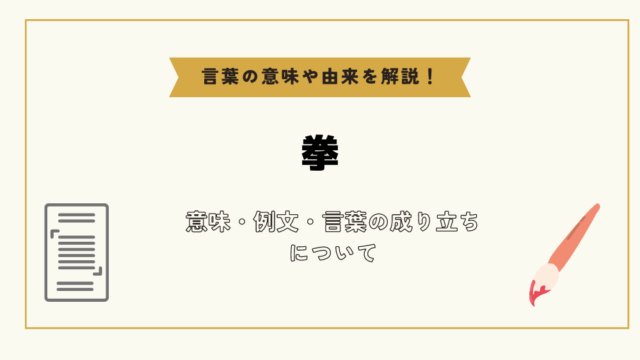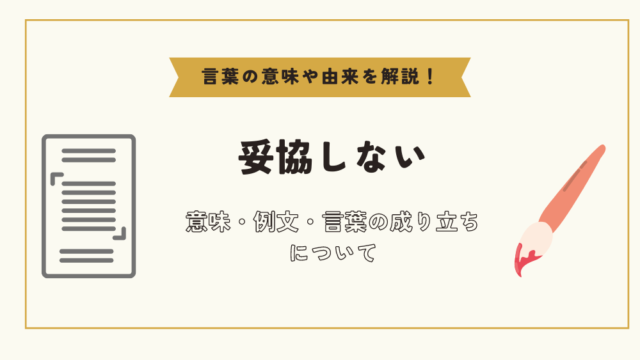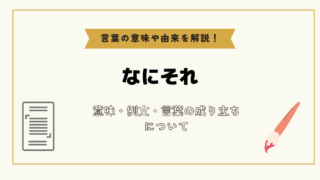Contents
「お腹すいた」という言葉の意味を解説!
「お腹すいた」という言葉は、直訳すると「お腹が空いた」という意味です。
食事の前や長時間の絶食後など、空腹を感じた時に使われる表現です。
「お腹すいた」という言葉は、日本語の会話や文章でよく使われており、非常にポピュラーな表現です。
「お腹すいた」という言葉の読み方はなんと読む?
「お腹すいた」という言葉は、ふつうに「おなかすいた」と読みます。
日本人にとっては非常に身近な表現であり、ほとんどの人がこの発音に慣れ親しんでいます。
「お腹すいた」という言葉の使い方や例文を解説!
「お腹すいた」という言葉の使い方はとてもシンプルです。
普通は、空腹を感じた時に「お腹すいた」と言います。
例えば、「もうすぐ夕食だけど、お腹すいたから少し食べようかな」とか、「お昼食べてから時間が経ったけど、お腹すいたからおやつを食べよう」というような使い方が一般的です。
「お腹すいた」という言葉の成り立ちや由来について解説
「お腹すいた」という言葉は、日本語の中でも古くから使われています。
具体的な由来や成り立ちについては特に明確な情報はありませんが、食事が人々の生活に欠かせない要素であることから、おそらく非常に古い時代から利用されてきたものと考えられます。
「お腹すいた」という言葉の歴史
「お腹すいた」という言葉の歴史については、正確な年代や起源は不明です。
しかし、食事や食べ物が人々の生活に不可欠であることから、おそらく非常に古い時代から存在していたものと考えられます。
また、近代になってからも、この表現は一貫して使われ続けており、非常に定着しています。
「お腹すいた」という言葉についてまとめ
「お腹すいた」という言葉は、日本語の中でもよく使われる表現です。
その意味は「お腹が空いた」ということで、食事の前や長時間の絶食後など、空腹を感じた時に使われます。
ほとんどの日本人が「お腹すいた」という表現になじみがあり、あまり意識することなく使用しています。
食事が人々の生活に欠かせない要素であることから、古くから存在しており、現代でも広く使われています。