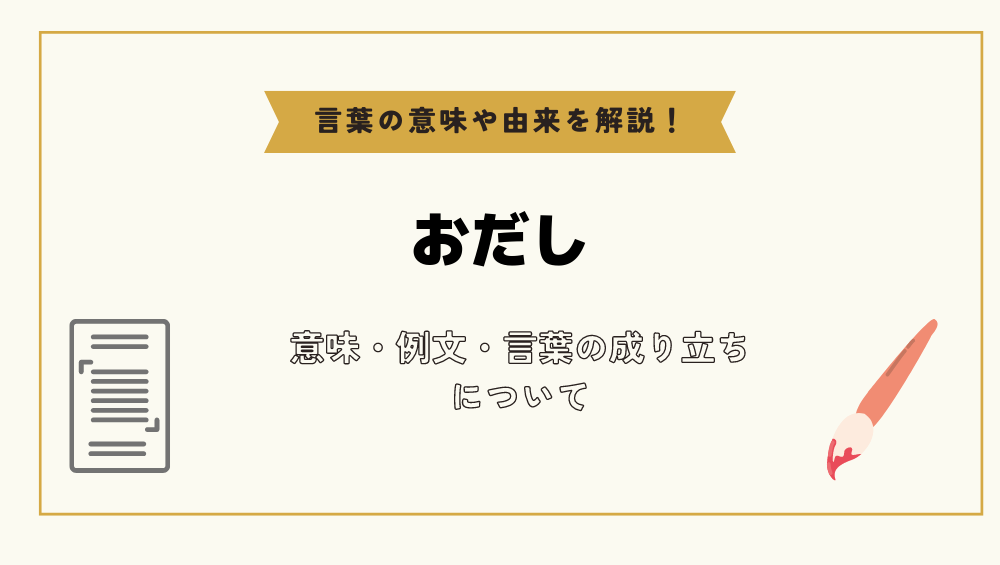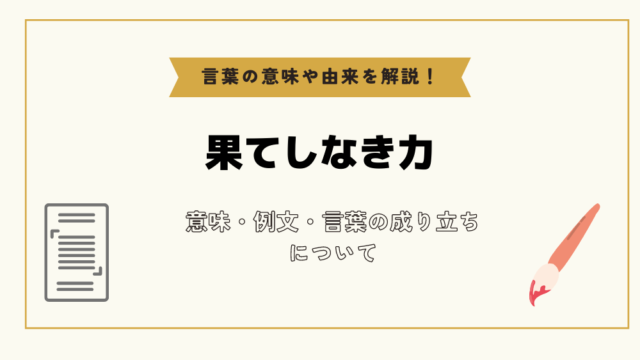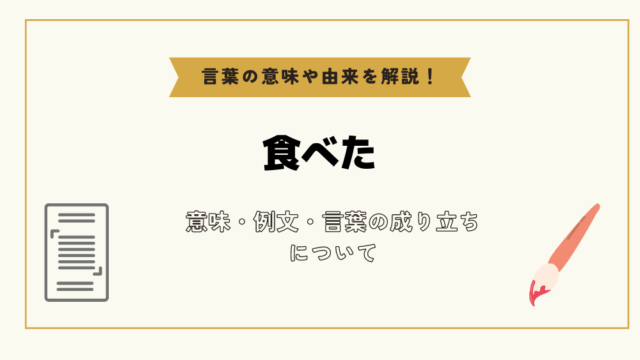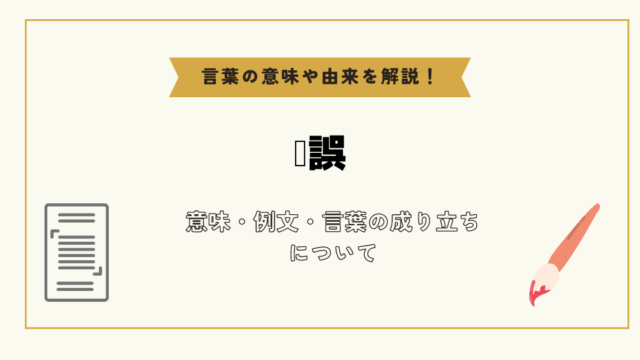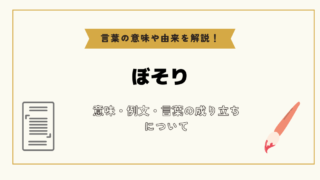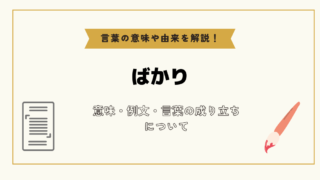Contents
「おだし」という言葉の意味を解説!
「おだし」とは、日本料理において欠かせないだしを指す言葉です。だしは、魚やかつお節、昆布、干ししいたけなどから取ることができます。だしは、料理に深みやコクを与えるだけでなく、味を引き立てる役割も果たします。日本料理の基本的な調味料であり、和食の味を決める重要な要素です。
「おだし」という言葉の読み方はなんと読む?
「おだし」という言葉は、「お」、「だ」、「し」の3つの文字で表されます。読み方は、「お」が「o」の音、「だ」が「da」の音、「し」が「shi」の音になります。全体を合わせて「おだし(odashi)」と発音します。
「おだし」という言葉の使い方や例文を解説!
「おだし」という言葉は、日本料理を話題にする際によく使われます。料理のレシピや食材の選び方などで、「おだしを取る」という表現が用いられます。例えば、「お味噌汁を作るためにおだしをとります」というように使われます。また、「おだしを取る」とは、鍋や煮物などに使うためのだしを作る行為を指すこともあります。
「おだし」という言葉の成り立ちや由来について解説
「おだし」という言葉の成り立ちや由来は、古くから続く日本の食文化に関連しています。だしの作り方や使い方は、日本各地で異なる特色を持ちながら、受け継がれてきました。調理法や地域によって異なる「おだし」の成り立ちや由来については、専門の料理人や研究家がさまざまな角度から研究を重ねています。
「おだし」という言葉の歴史
「おだし」という言葉の歴史は古く、日本の食文化の発展とともに変化してきました。昔から海産物が豊富な日本では、魚介類を活用した料理が発達し、その中心に「おだし」が存在していました。歴史を遡ると、奈良時代や平安時代の料理書にも「だし」に関する記述があり、日本人の食生活に深く根付いてきたことが分かります。
「おだし」という言葉についてまとめ
「おだし」という言葉は、日本料理において非常に重要な存在です。だしは、料理に深みやコクを与えるだけでなく、味を引き立てる役割も果たします。日本料理の基本的な調味料であり、和食の味を決める重要な要素と言えます。また、「おだし」の成り立ちや由来には、日本の食文化の歴史が息づいています。