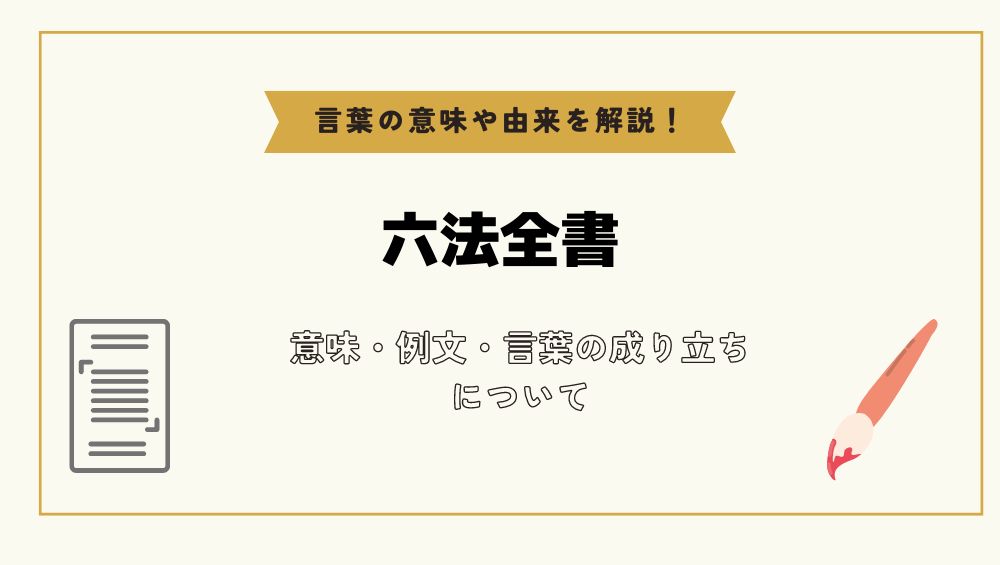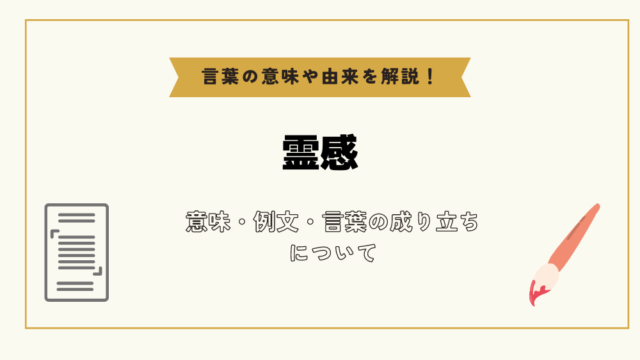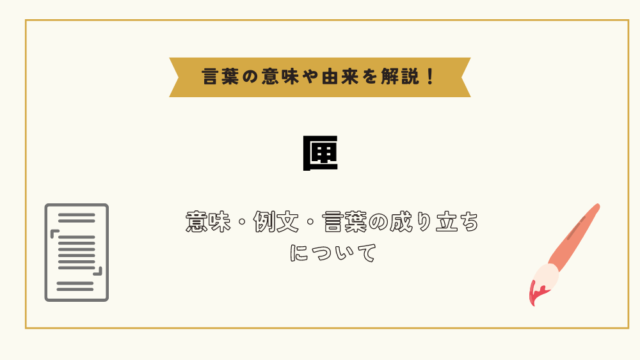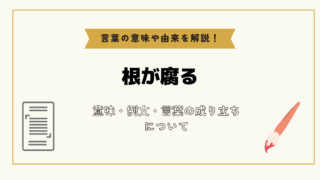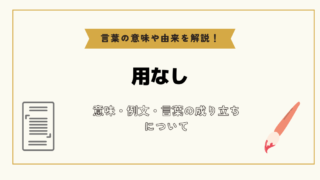Contents
「六法全書」という言葉の意味を解説!
「六法全書」という言葉は、日本の法律関連の書籍を指す言葉です。
具体的には、刑法、民法、商法、労働法、行政法、そして国家公務員法の6つの法律を網羅した法律書のことを指します。
これらの法律は、日本の法律文化の基礎となる重要な法典であり、法律関係者や法学生にとって必携の書として知られています。
「六法全書」の読み方はなんと読む?
「六法全書」は、ろくほうぜんしょと読みます。
日本の法律関連の書籍を指す言葉であるため、法律に興味を持つ方や法律関係者にとっては、身近でなじみ深い言葉となっています。
「六法全書」という言葉の使い方や例文を解説!
「六法全書」は法律関連の書籍を指す言葉ですが、一般的には特に法律知識に通じていない方には馴染みが薄いかもしれません。
使い方としては、「六法全書」には刑法や民法など、6つの法律が網羅されていることがわかります。
例文としては、「法律問題に関して詳しい解説が六法全書にありますので、是非参考にしてください」といった風に使うことができます。
「六法全書」という言葉の成り立ちや由来について解説
「六法全書」という言葉は、元々は明治時代の法律書の一つである『明治大日本帝国憲法鉄道事業規則六法全書』が起源とされています。
この書籍は、当時の鉄道事業に関連する法律を6つにまとめたものであり、後に他の法律分野でも同様の形式の書籍が作られるようになりました。
そのため、一般的に「六法全書」という言葉は法律全般を指すようになりました。
「六法全書」という言葉の歴史
「六法全書」という言葉は、明治時代の初めにまで遡ることができます。
明治時代に入ると、日本では多くの法律が制定され、それに伴って法律関連の書籍が作られるようになりました。
その中でも、特に重要な法律を網羅した書籍が「六法全書」と呼ばれるようになり、日本の法律文化において重要な位置を占めるようになりました。
「六法全書」という言葉についてまとめ
「六法全書」という言葉は、日本の法律関連の書籍を指す言葉です。
刑法、民法、商法、労働法、行政法、国家公務員法の6つの法律が網羅されており、法律関係者や法学生にとっては必携の書となっています。
明治時代から始まった「六法全書」という言葉は、日本の法律文化において重要な位置を持つようになりました。