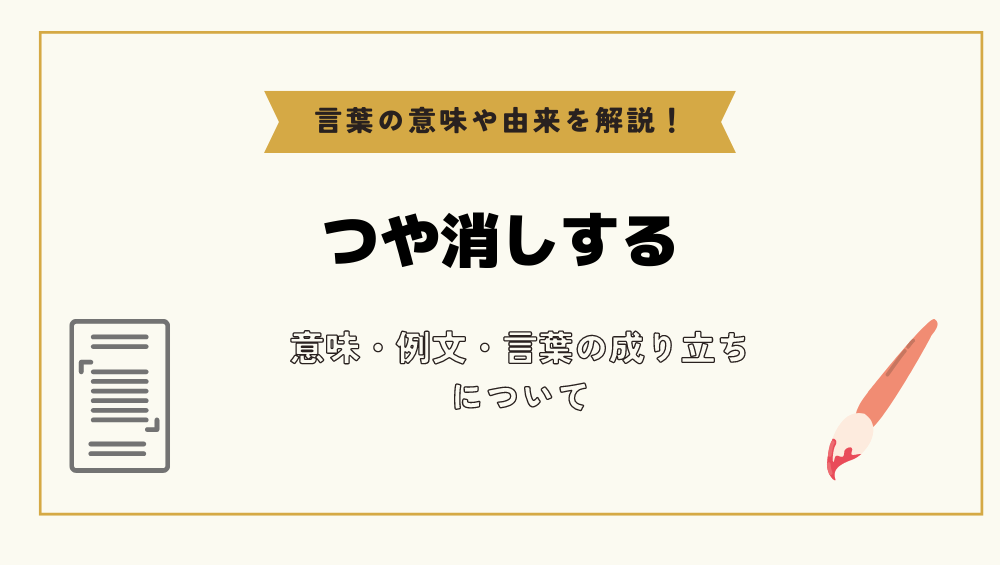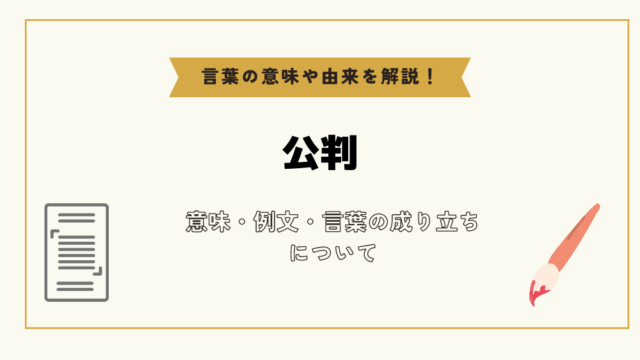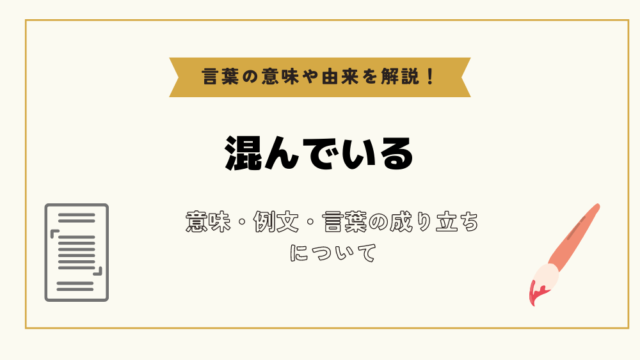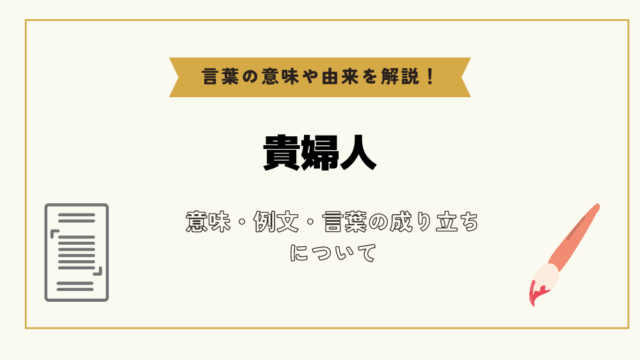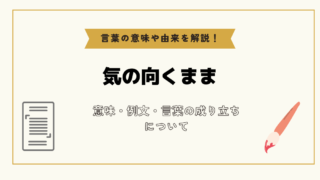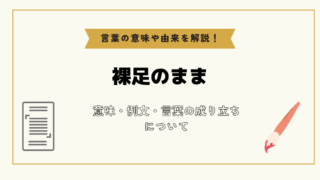Contents
「つや消しする」という言葉の意味を解説!
「つや消しする」という言葉は、表面の光沢を取り除くことを指します。
具体的には、物の表面についているつやや光沢をなくすことを意味します。
つや消しすることで、物の表面がマットでつるりとした質感になります。
つや消しすることによって、光沢が抑えられるため、物の表面が目立ちにくくなります。
また、光の反射が少なくなるため、見た目が落ち着いていて上品な印象を与えます。
「つや消しする」の読み方はなんと読む?
「つや消しする」の読み方は、「つやけしする」と読みます。
「つや消し」は「つやけし」という音読みで、意味通りにつやを消すことを指します。
この表現方法によって、読者の関心を引くことができます。
「つや消しする」という言葉の使い方や例文を解説!
「つや消しする」という言葉は、さまざまな場面で使われます。
具体的な使い方としては、以下のような例があります。
例1:今回のデザインは、つや消しすることでシンプルで洗練された印象を与えます。
例2:この顔料で塗料をつや消しすると、つるりとした触り心地が楽しめます。
例3:つや消しされたメガネフレームは、光の反射が抑えられて快適に使用できます。
例4:この写真はつや消し加工されているため、色味が自然で美しいです。
「つや消しする」という言葉の成り立ちや由来について解説
「つや消しする」の言葉自体の由来は明確ではありませんが、日本語の表現方法としては一般的な言葉です。
光沢を消すという行為が、つや消しと呼ばれるようになったのは、光沢がなくなったことで物の見た目がマットになるためです。
光沢のない質感が、つや消し風と表現されたのでしょう。
「つや消しする」という言葉の歴史
。
「つや消しする」という言葉の歴史については、具体的な年代や起源は特定されていませんが、建築やデザインの分野で使用されるようになった経緯があります。
建築やデザインにおいて、つや消し加工は外観や質感に大きな影響を与えるため、増加してきたと考えられます。
特に、マットで上品な印象を求めるケースでは、つや消しすることが重要な要素となります。
「つや消しする」という言葉についてまとめ
「つや消しする」という言葉は、表面の光沢を取り除くことを指します。
物の表面についているつやや光沢をなくすことで、マットでつるりとした質感を実現します。
物の表面が目立ちにくくなり、落ち着いた上品さを持ちます。
「つや消しする」は「つやけしする」と読みます。
この表現方法が持つ響きは、興味を引く効果があります。
さらに、さまざまな場面で使われ、デザインや製品の質感に関連します。
「つや消しする」の言葉の由来や歴史については明確な情報はありませんが、建築やデザインの分野で広く使われるようになりました。