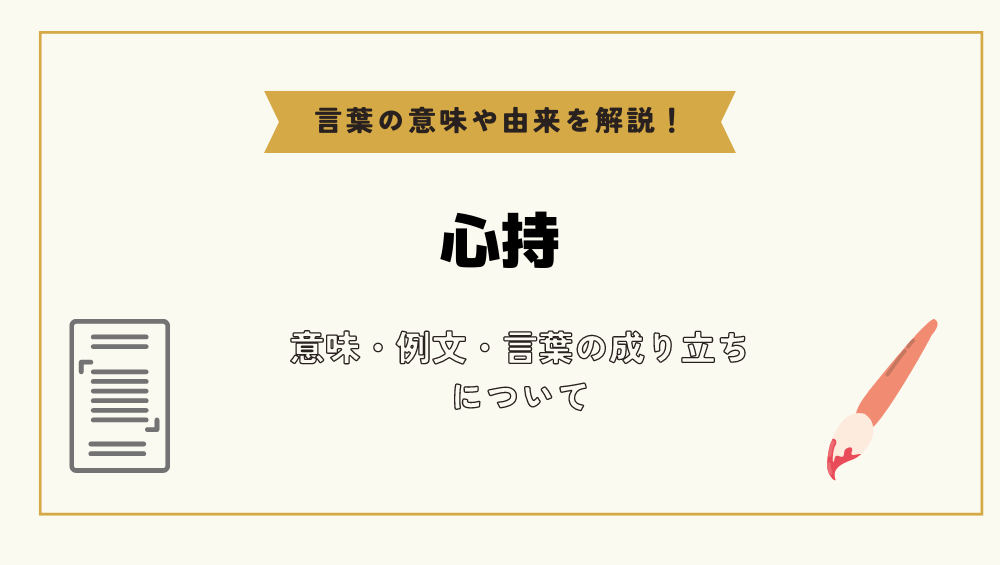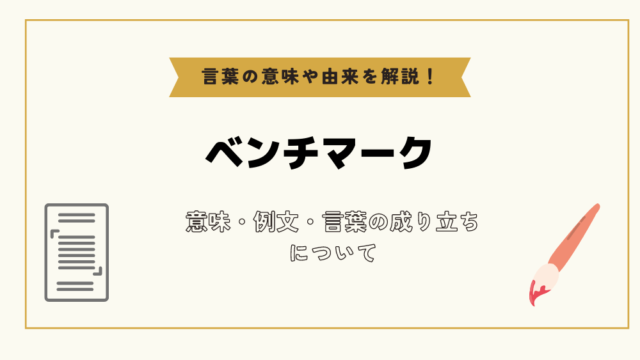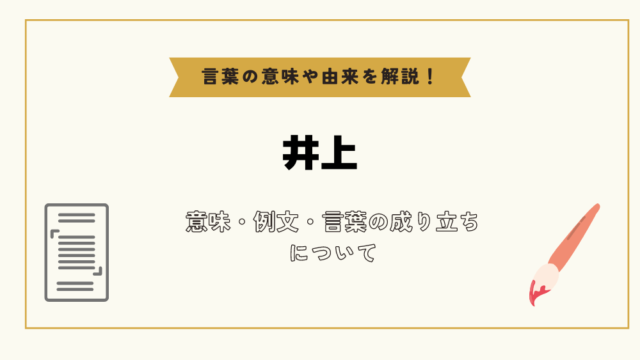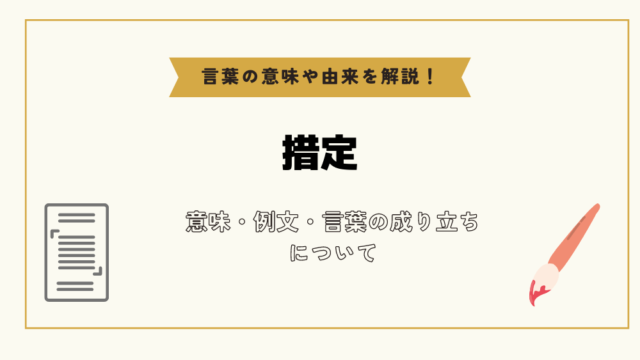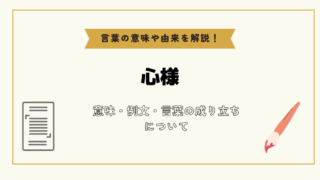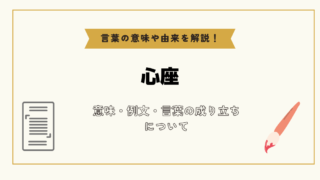Contents
「心持」という言葉の意味を解説!
「心持(こころもち)」という言葉は、物事を捉える心の状態や態度を表します。
心持ちとも書かれます。
この言葉は日本語において広く使われており、気持ちや感じ方を表現する際によく用いられます。
人の心の内面を表す言葉とされ、情緒や思考を含んだ状態を表現するのに適しています。
「心持」という言葉の読み方はなんと読む?
「心持」という言葉は、「こころもち」と読みます。
「心」は「こころ」と読み、「持」は「もち」と読みます。
言葉の中にある「こころもち」の部分が「心持」を読むため、注意が必要です。
日本語には読み方が難しい言葉も多々ありますが、正しい読み方には慣れが必要です。
「心持」という言葉の使い方や例文を解説!
「心持」という言葉は、自分の心の状態や感じ方を表現する際に使われます。
例えば、仕事が順調であることを表現する場合には「心持ちがいい」と言えますし、逆に厳しい状況にある場合には「心持ちが悪い」と言えます。
また、「心持ちが落ち着く」と言えば、心が穏やかな状態を指しています。
さまざまな状況や感情に対して、心持ちを使った表現が用いられます。
「心持」という言葉の成り立ちや由来について解説
「心持」という言葉は、日本語の中で長い歴史を持つ言葉です。
その由来や成り立ちを具体的に特定することは難しいですが、日本の文化や思想と深いつながりを持つ言葉として注目されています。
心の内面や感情を表現することに重きを置いた日本人の感性から生まれた言葉と言えるでしょう。
「心持」という言葉の歴史
「心持」という言葉は、古くから存在している言葉であり、日本の文学や歴史書にも登場します。
古今和歌集や万葉集などの古典的な文献にも、「心持ち」という表現が見られます。
日本人の感受性や情緒を重んじる文化が根付いているため、心の内面を表現する言葉として多用されてきたのです。
「心持」という言葉についてまとめ
「心持」という言葉は、心の状態や感じ方を表現する日本語の重要な単語です。
自分の気持ちや思考を表現する際に活用することができます。
この言葉には日本の文化や思想が根付いており、心の内面を大切にする日本人の感性を象徴しています。
正しい読み方や使い方を理解し、日常会話や文章で活用してみましょう。