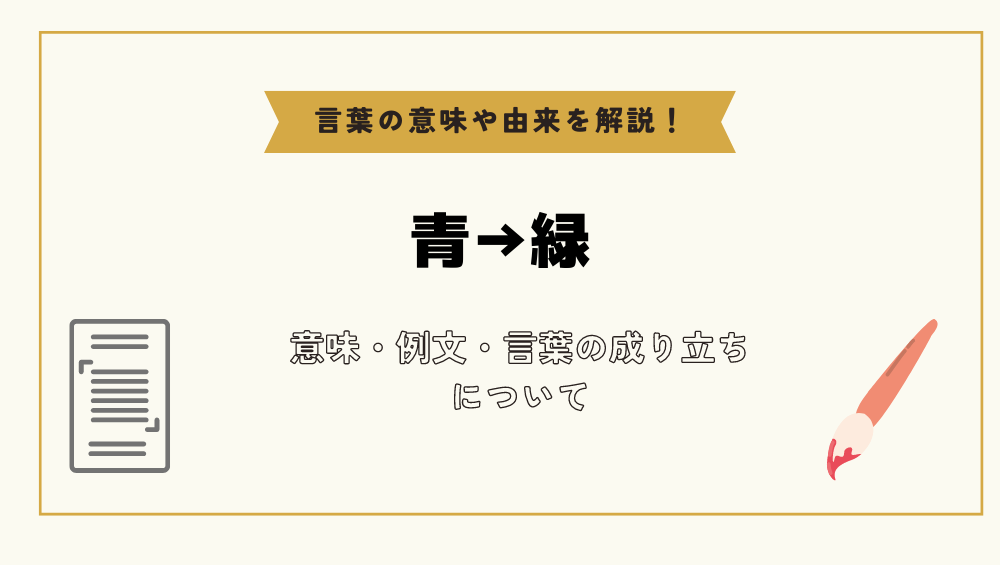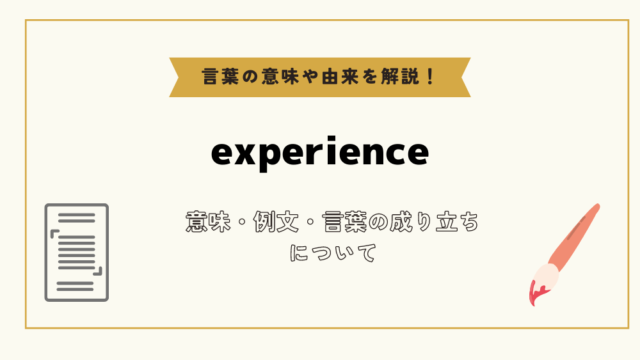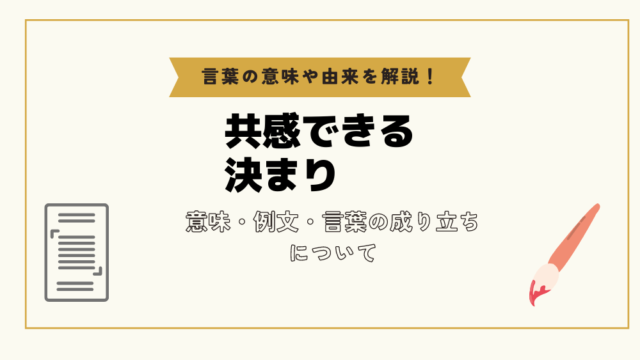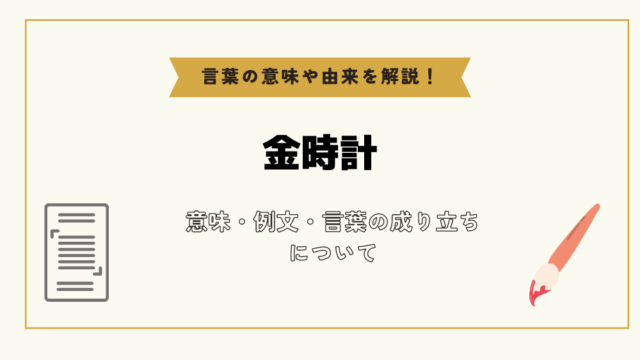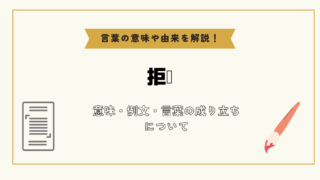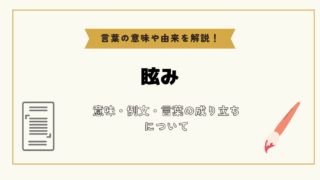Contents
「青→緑」という言葉の意味を解説!
「青→緑」という言葉は、色彩の変化を表す表現です。
通常、青色が次第に緑色へと変化していく様子を指します。
青色と緑色は、光の波長が異なるため、視覚的にもっとも認識がしやすい色として知られています。
この色の変化は、自然界や花卉、季節の変わり目などで見ることができます。
人々はこの美しい色の変化を、自然や美的感覚においても重要な要素として認識しています。
「青→緑」という言葉の読み方はなんと読む?
「青→緑」という言葉の読み方は、「あおからみどり」と読みます。
色彩の変化を示す表現であるため、このように読むことが一般的です。
「あ」の音から始まる「あお」という言葉が、次第に「みどり」という音に変化していくイメージがあります。
「青→緑」という言葉の使い方や例文を解説!
「青→緑」という言葉は、色彩の変化を示すために用いられます。
例えば、春の訪れを表現する際には、「冬の寒さから次第に青→緑の暖かさへ変わっていく」といった表現が使われます。
また、絵画やデザインなどでも、「色調が青→緑に移り変わる」といった表現がされることがあります。
このように、「青→緑」は色の変化を感じさせるための表現方法として幅広く活用されています。
「青→緑」という言葉の成り立ちや由来について解説
「青→緑」という言葉の成り立ちは、色の変化を示す表現方法として自然発生的に広がってきたものです。
青色と緑色は、実際の光の波長の違いから生じる色の変化ですが、人々はその美しさや特徴を重視し、色の変化を表現する際に「青→緑」という言葉を使用するようになりました。
この言葉は、自然の美しさや色彩の変化に対する人々の感性を反映しています。
「青→緑」という言葉の歴史
「青→緑」という言葉は、歴史のなかで広まってきた表現方法です。
古代文学や伝統的な文化においても、「青→緑」の色彩の変化は詠まれてきました。
また、近代においても、絵画やデザインなどの表現において「青→緑」の色調の変化が重視されてきました。
これらの文化的背景や芸術作品の影響により、「青→緑」という言葉は広く認知され、私たちの言葉遣いに定着していきました。
「青→緑」という言葉についてまとめ
「青→緑」という言葉は、色彩の変化を表す表現方法です。
青色から緑色へと色調が変わっていく様子を描写する際に用いられ、自然や美的感覚において重要な要素として認識されています。
この言葉は、色の変化を感じさせる表現方法として広く使われる一方で、古代から現代までの文学や芸術作品においても重要なテーマとなっている言葉です。