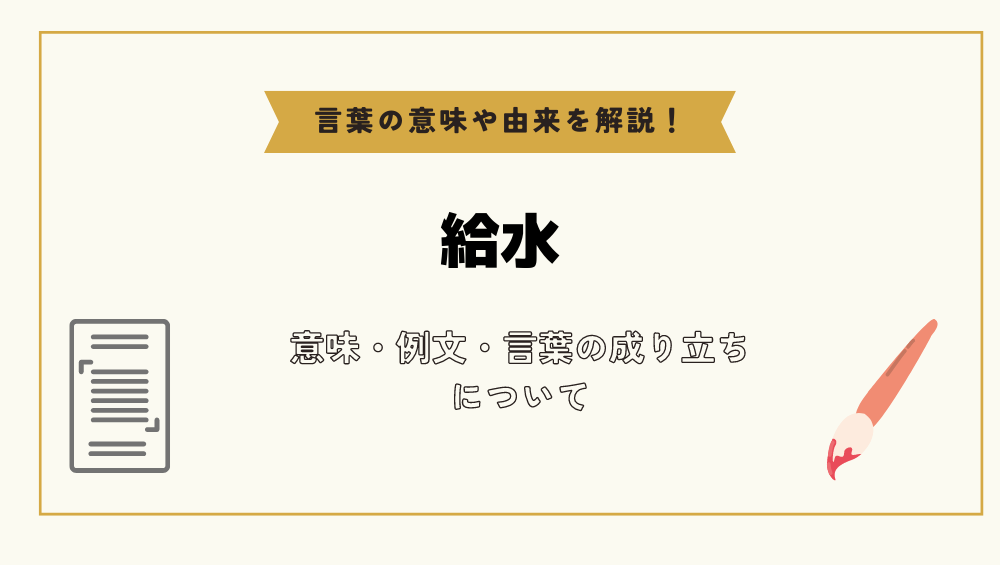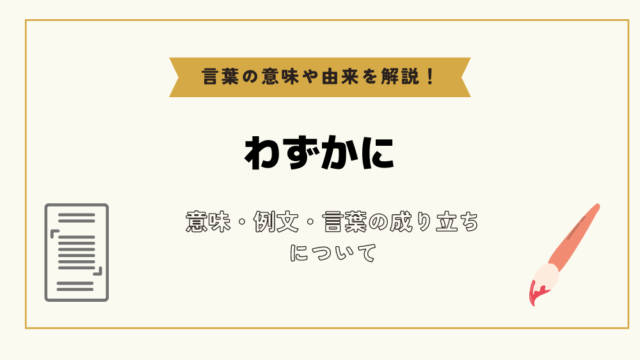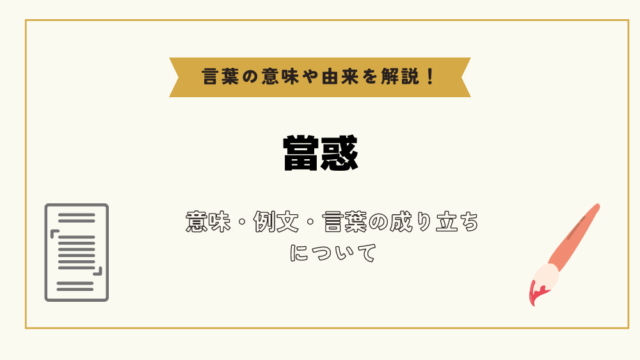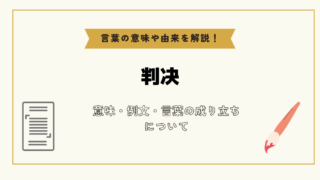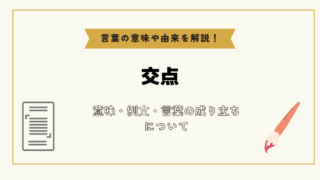Contents
「給水」という言葉の意味を解説!
。
「給水」という言葉は、水を供給することを意味します。
その名の通り、水道やポンプなどを使って、人々や施設に水を提供する行為を指します。
私たちの生活において、給水は非常に重要な役割を果たしています。
給水がなければ、飲み水や生活用水、産業用水などが必要な場面で問題が生じます。
また、給水は災害時や緊急事態においても欠かせない要素です。
給水は私たちの生活を支える大切な存在なのです。
「給水」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「給水」という言葉は、「きゅうすい」と読みます。
この読み方は、漢字の「給」が「きゅう」という音で、「水」が「すい」という音で表されているためです。
日本語にはさまざまな読み方がありますが、給水の読み方は比較的一般的なものです。
ですので、多くの人がこの読み方を理解しています。
「給水」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「給水」という言葉は、以下のような使い方をします。
例えば、「給水設備が整った建物」という文では、建物には水道などの設備が整備されており、水を給水できる状態であることを表します。
また、「給水区域の拡大」という文では、特定の地域における水道の供給範囲が拡大されることを意味します。
このように、「給水」は水を供給する行為やその結果を表現する際に使われる言葉です。
「給水」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「給水」という言葉は、日本語の古い時代から存在しています。
「給」の漢字は、「斂(きく)」や「及(およ)ぶ」といった意味を持ち、「水」はそのまま水を意味します。
つまり、「給水」は、古くから水を供給する行為を表す言葉として使用されてきたのです。
水は人々の生活に欠かせないものであり、その重要性が認識されるにつれて、「給水」の言葉も一般的になっていったと考えられます。
「給水」という言葉の歴史
。
「給水」という言葉の歴史は、古代から続いています。
日本においては、奈良時代に都城の平安京(現在の京都)に水道施設が整備され、「給水」が行われるようになりました。
江戸時代に入ると、江戸城や大名屋敷などでも水道が整備され、給水が行われました。
現代においては、水道法の制定などを通じて給水の基準が整備され、より安全で信頼性の高い給水が行われるようになりました。
長い歴史の中で、給水は私たちの生活の一部となり、不可欠な存在となっているのです。
「給水」という言葉についてまとめ
。
「給水」という言葉は、水を供給することを意味します。
私たちの生活において不可欠な存在であり、水道やポンプなどを通じて水を提供する行為を指します。
日本語においては、「きゅうすい」と読みます。
さまざまな場面で使われる言葉であり、例えば給水設備や給水区域の拡大などを表現することができます。
古代から続く歴史もあり、私たちにとってなじみ深い言葉です。