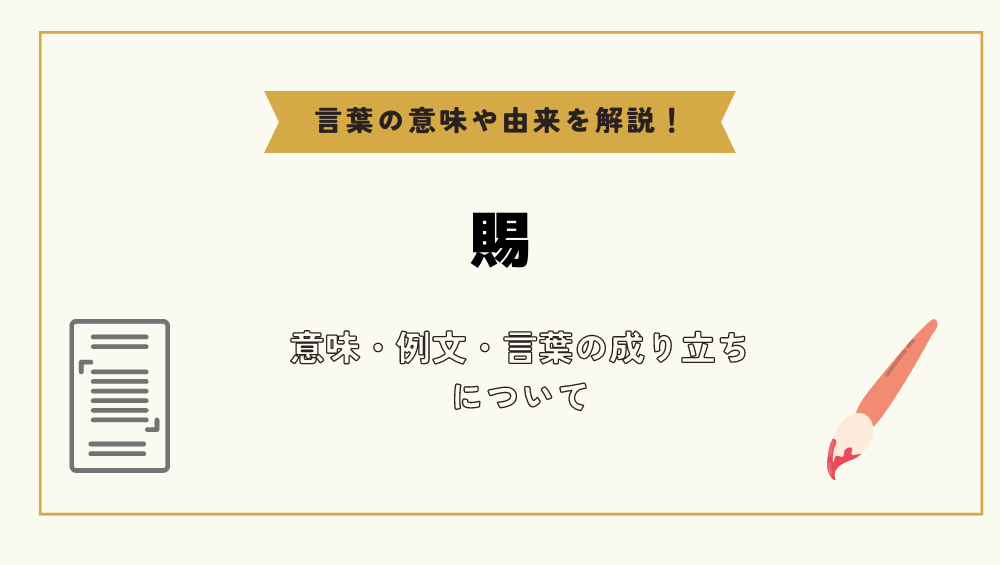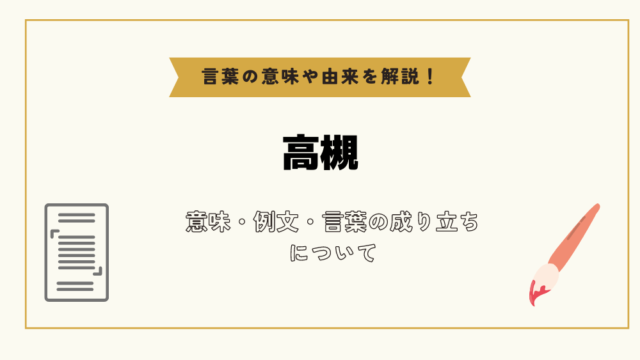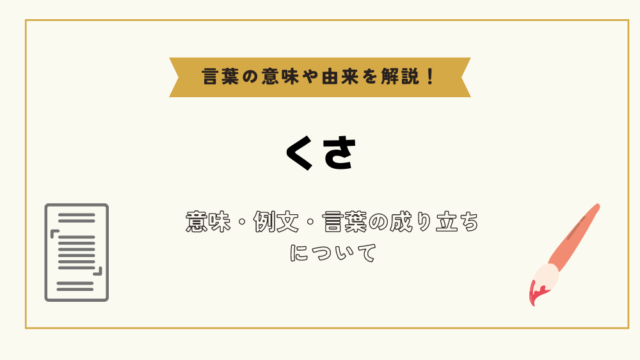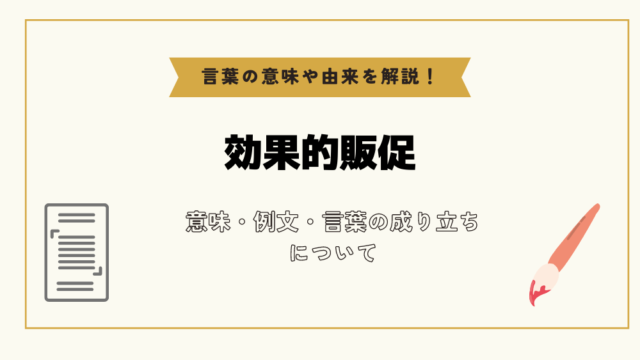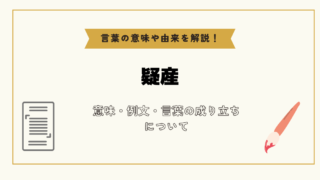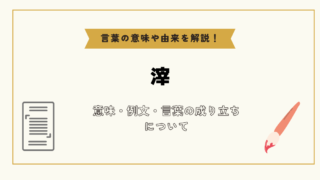Contents
「賜」という言葉の意味を解説!
「賜(たまわる)」は、何かを与えられる・授けられるという意味を持ちます。
この言葉は、尊敬や感謝の念を込めて何かをいただく場合に使用されます。
例えば、上司からのプレゼントや恩人からの助けを頂いた場合、そして神からの祝福なども「賜」という表現を使って表されることがあります。
「賜」の読み方はなんと読む?
「賜」の読み方は、おおむね「たまわる」と読みます。
また、真ん中の「マ」は「ま」とも読まれることがありますが、一般的には「たまわる」と読むのが一般的です。
なお、敬語での使用や文語文などでは、「与(あた)えられる」という意味で使われることもあるため、文脈によっては異なる読み方になることもあります。
「賜」という言葉の使い方や例文を解説!
「賜」という言葉は、おおむね堅い表現ですが、礼儀正しい場面や目上の人からの贈り物を述べる際など、特別な場面に使われることが多いです。
例えば、「上司からサプライズでプレゼントを賜りました」「ご厚意に甘えて、この仕事を賜ります」「神のご加護を賜り、無事に帰還しました」などと使うことができます。
「賜」という言葉の成り立ちや由来について解説
「賜」という言葉は、古くから日本語に存在する言葉であり、漢字表記されるようになったのは比較的最近のことです。
この漢字の成り立ちは、「貝(かい)」と「者(もの)」の組み合わせです。
貝は豊かさや価値を表し、者は人やものを指す意味があります。
つまり、「貝からものを授かる」という意味合いがあると言われています。
「賜」という言葉の歴史
「賜」という言葉の歴史は、日本語の起源に関わる歴史でもあります。
古代の日本では、貝で貿易が行われ、人々は価値のある貝を求めていました。
そのため、「貝からものを授かる」という表現がすることから、「賜」という言葉が生まれたと考えられています。
現代の日本語でも、この言葉は古き良き日本の歴史や文化を思い起こさせてくれます。
「賜」という言葉についてまとめ
「賜」は、何かを与えられる・授けられるという意味を持つ言葉です。
敬意や感謝の気持ちを込めて使われることがあり、特別な場面で使われることが多い言葉です。
「賜」という漢字の由来は、古代の貝貨物の文化に関わりがあり、歴史的な意味を持っています。
日本語の豊かさや文化を感じさせる言葉であり、人々に感謝の気持ちを伝えたいときに有効な表現と言えるでしょう。