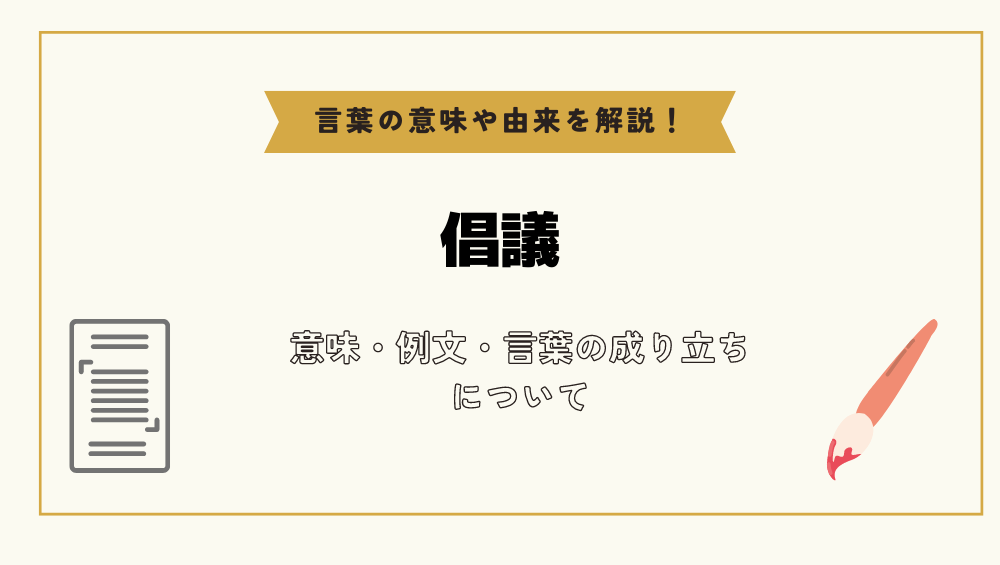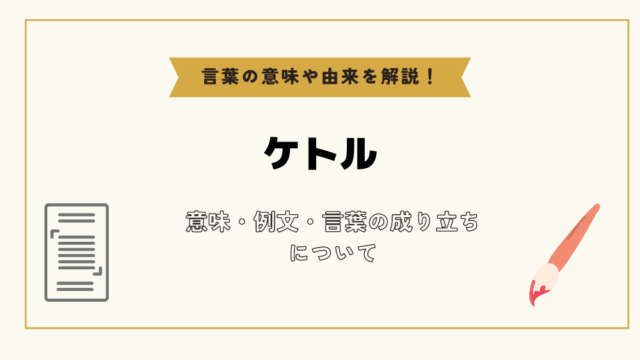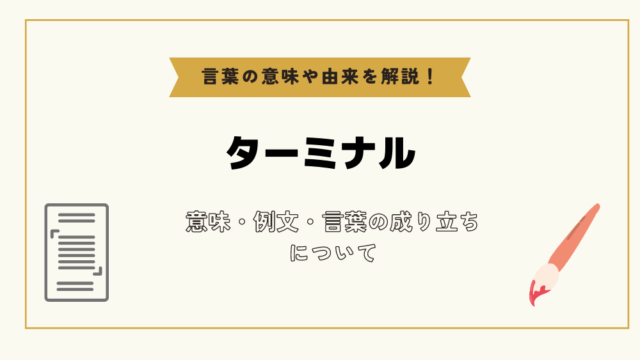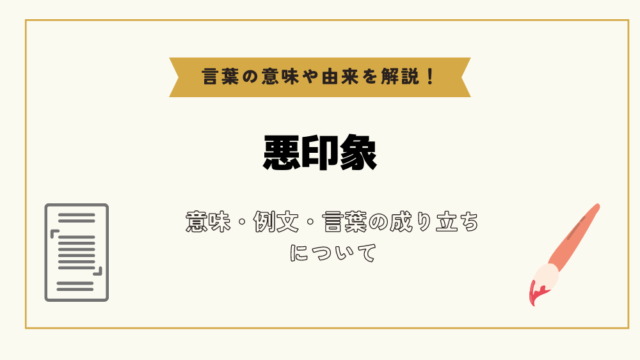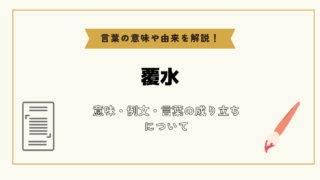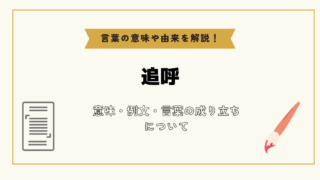Contents
「倡議」という言葉の意味を解説!
倡議という言葉は、何かを提案したり、主張したりすることを指します。
一般的には、特定の問題や改善事項について公に意見を述べることや、改革や運動を始めるために人々を説得する活動を指すことが多いです。
倡議は、社会的な問題を改善するための重要な手段となります。
必要な変革や意見を訴えることで、社会全体の関心を喚起し、解決策を模索することができます。
「倡議」という言葉の読み方はなんと読む?
「倡議」という言葉の読み方は、「しょうぎ」となります。
しょうぎという読み方は、一般的なもので、日本語の発音に沿ったものです。
「しょう」という部分は、「おおやけ」とも読みますが、倡議という言葉では「しょう」と読むことが主流です。
また、「ぎ」という部分は、「ぎ」と鼻濁音で発音しましょう。
「倡議」という言葉の使い方や例文を解説!
「倡議」という言葉は、公的な場での意見や提案によく使われます。
例えば、市民団体が環境問題に関して倡議を行ったり、政治家が法案を倡議したりすることがあります。
以下は、例文です。
。
– 市民団体が、海岸の清掃活動と環境保護について倡議を行いました。
。
– 議員が新しい教育改革案を倡議し、注目されています。
。
– 学生たちが、授業料値上げに反対するための倡議活動を行っています。
「倡議」という言葉の成り立ちや由来について解説
「倡議」という言葉の成り立ちや由来については、明確な起源はわかっておりませんが、中国から日本に伝わった言葉とされています。
「倡」という漢字は、「提案する」という意味があります。
「議」という漢字は、「討論する」という意味があります。
これらの漢字が組み合わさって、「提案し討論する」という意味の言葉となったのでしょう。
「倡議」という言葉の歴史
「倡議」という言葉の歴史については、詳しい情報がないため、具体的には分かっていません。
しかし、「倡議」という活動自体は、古くから行われてきました。
日本では、江戸時代から明治時代にかけて、新たな政治や社会の価値観を倡議する動きが盛んになりました。
また、戦後の民主主義の成立により、個人や団体が積極的に倡議活動を行うことが一般的になりました。
「倡議」という言葉についてまとめ
「倡議」という言葉は、意見や提案を行うことや特定の問題を改善するための活動を指します。
倡議は、社会をより良くするための重要な手段となります。
そして、倡議は古くから行われてきた活動であり、現代でも各界で広く活発に行われています。