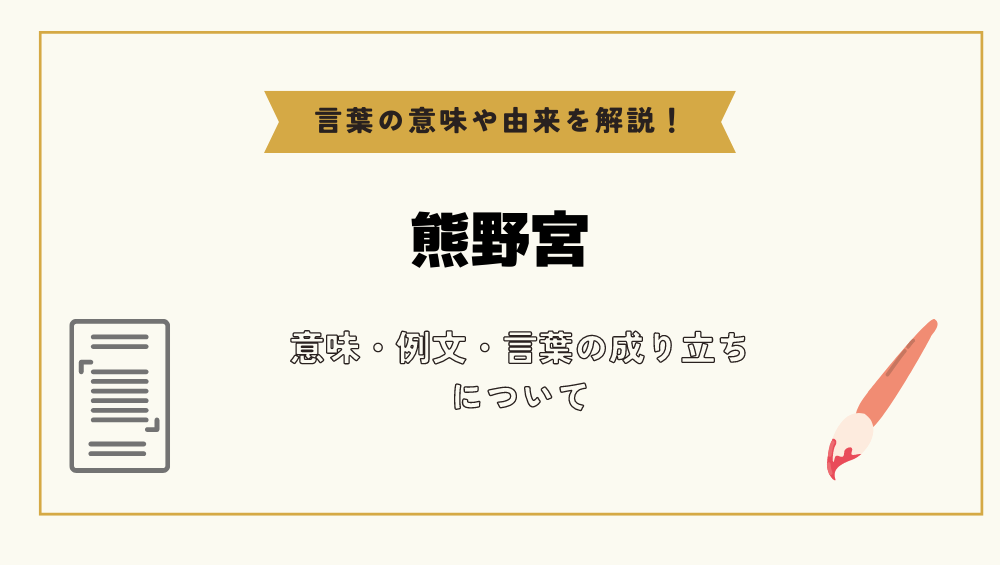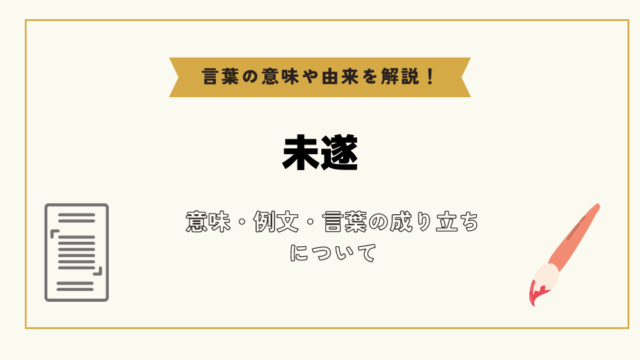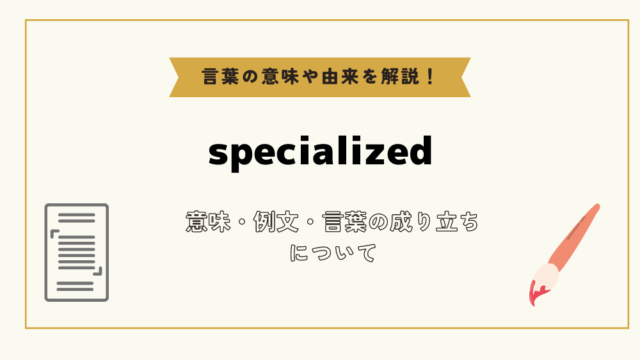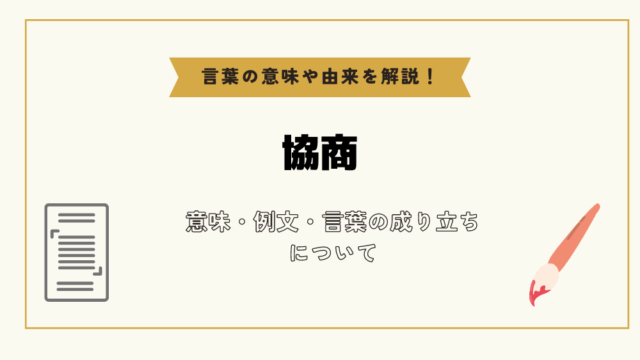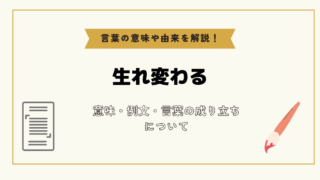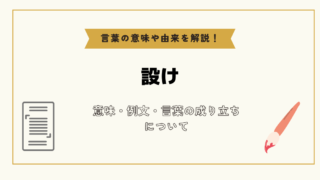Contents
「熊野宮」という言葉の意味を解説!
熊野宮(くまのみや)とは、「熊野信仰」において神を祭る社殿のことを指します。
熊野信仰は、熊野三山(熊野本宮、熊野速玉大社、熊野那智大社)を中心に広まった信仰で、熊野宮はこの三山を指しています。
この信仰は日本最古の信仰とされ、古くから山岳信仰と結びついています。
熊野宮は山間に位置しており、美しい自然に囲まれた神聖な場所とされています。
「熊野宮」の読み方はなんと読む?
「熊野宮」は、「くまのみや」と読みます。
日本語の読み方で、漢字の「熊」は「くま」と読み、「宮」は「みや」と読みます。
この読み方は一般的なものであり、熊野信仰や関連する文献や資料で使われることが多いです。
「熊野宮」という言葉の使い方や例文を解説!
「熊野宮」は、熊野信仰に関連した文脈で使われることが多いです。
たとえば、「私は熊野宮を参拝し、心を清めました」というような使い方があります。
また、「熊野宮の祭りは毎年多くの人が訪れます」というように、祭りや観光地としての熊野宮の存在も表現されることがあります。
「熊野宮」という言葉の成り立ちや由来について解説
「熊野宮」という言葉の成り立ちは、熊野信仰の歴史に由来しています。
熊野信仰は、古くから山岳信仰と結びついていた神聖な信仰であり、霊峰・熊野山を中心に広がりました。
その中で、神々を祭るための社殿である「宮」が建てられるようになり、それが「熊野宮」と呼ばれるようになりました。
熊野宮は、この信仰の中で重要な存在として崇拝され続けています。
「熊野宮」という言葉の歴史
「熊野宮」という言葉の歴史は、古代から受け継がれてきました。
熊野信仰は、縄文時代から存在する山岳信仰と、古代の神道が混ざり合った形で発展してきました。
その中で、熊野宮が建てられ、熊野三山が信仰の中心となりました。
また、歴史の中で多くの修験者や僧侶が熊野宮への参拝や修行を行い、熊野宮は修験道の拠点としても栄えました。
「熊野宮」という言葉についてまとめ
「熊野宮」という言葉は、熊野信仰における神を祭る社殿を指します。
その由来は古代から続く熊野信仰の歴史にあり、山岳信仰と結びついています。
熊野宮は美しい自然に囲まれた場所に位置し、多くの人々が参拝や観光を楽しんでいます。
熊野宮への参拝は心を清める機会ともなり、多くの人々にとって特別な場所となっています。