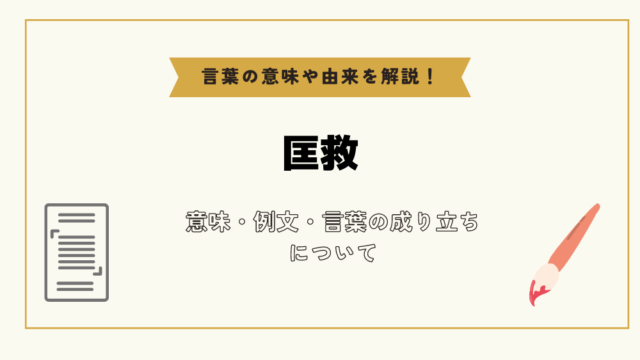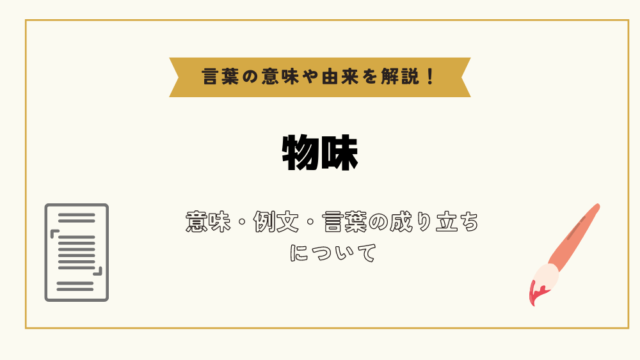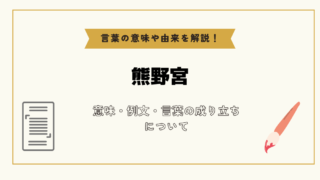Contents
「設け」という言葉の意味を解説!
「設け」という言葉の意味は、ある物や場所を用意したり、創設したりすることを指します。何かをするための準備を整えることや、必要なものを用意することが含まれます。例えば、会議室を設ける、検索機能をウェブサイトに設ける、イベントの会場を設けるなど、特定の目的に向けて必要なものを準備する際に使われる言葉です。
「設け」という言葉の読み方はなんと読む?
「設け」という言葉は、「もうける」と読みます。この読み方は「魔法をかける」という意味の「設ける」ではなく、準備や用意をする「設ける」の場合に使われます。読み方に注意して、適切に使いましょう。
「設け」という言葉の使い方や例文を解説!
「設け」という言葉は、特定の物や場所を用意する際に使用されます。例えば、新しいオフィスに会議室を設ける場合、必要な設備や家具を揃え、会議が行える環境を整えます。また、ウェブサイトに検索機能を設ける場合、データベースを構築し、検索結果を表示できるようにします。このように、「設け」は何かを実現するための重要な準備や用意をする際に使われる言葉です。
「設け」という言葉の成り立ちや由来について解説
「設け」という言葉の成り立ちを見ると、漢字の組み合わせからわかる通り、「言書」のひとつであることが分かります。「言書」とは、意味を持つ言葉を表すために使われる漢字の組み合わせを指す言葉です。具体的には、「言(ことば)」と「曰く」(言う)という漢字が組み合わさり、「もうける」という意味になったと言われています。
「設け」という言葉の歴史
「設け」という言葉の歴史を探ると、古くは日本の古典文学にもよく登場する言葉です。平安時代の「源氏物語」や「竹取物語」にも、「設ける」という表現が見られます。江戸時代以降、現代に至るまで、この言葉は日本語の中で広く使われ続けてきました。時代を超えて使われる理由は、物事を実現するために必要な準備や用意という意味が、現代でも重要であるからかもしれません。
「設け」という言葉についてまとめ
「設け」という言葉は、物事を実現するための準備や用意をすることを指します。会議室や検索機能など、特定の物や場所を用意する際に活用される重要な言葉です。漢字の組み合わせからは、言書のひとつであることがうかがえ、古典文学にもよく出てくる言葉として知られています。まさに、「設け」の力で、目標を達成するための準備を整えることができるでしょう。