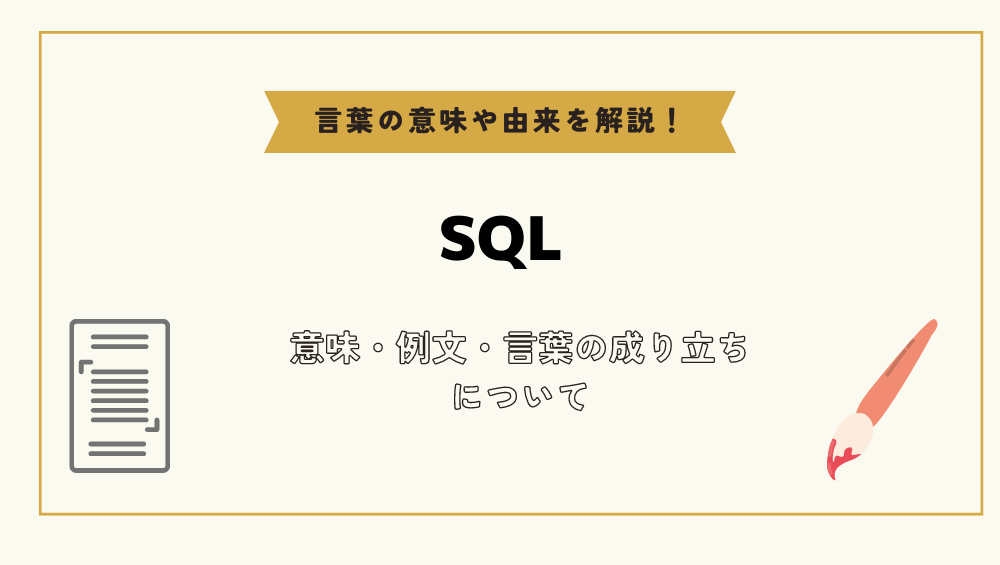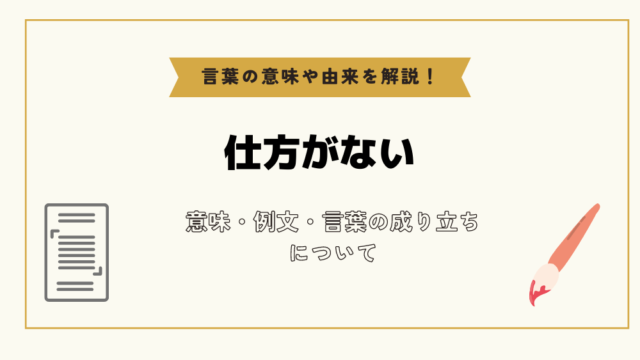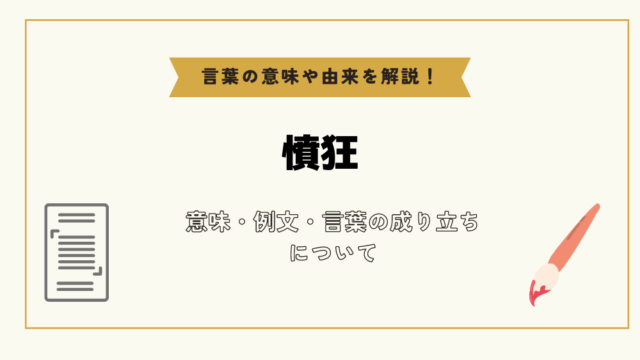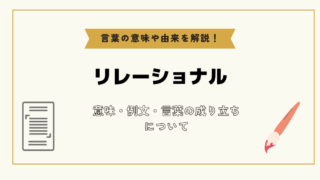Contents
「SQL」という言葉の意味を解説!
「SQL」とは、Structured Query Language(ストラクチャード・クエリ・ランゲージ)の略称です。
データベース管理システム(DBMS)とやり取りするための標準的な言語です。
「SQL」は、データベースに対してクエリ(問い合わせ)を行ったり、新しいデータを追加したり、既存のデータを編集したりするために使用されます。
また、データベースを操作する際に必要なテーブルの作成や削除、インデックスの作成なども「SQL」を使用して行います。
データベースを扱う際には、ほぼ必ず「SQL」が使われるため、プログラマーやシステムエンジニアにとっては必須の知識と言えます。
「SQL」の読み方はなんと読む?
「SQL」は、「エスキューエル」と読みます。
英語の発音では「エスキューエル」に近い音ですが、日本語では「エスキューエル」と呼ばれることが一般的です。
この読み方は、日本国内での一般的な呼称であり、英語圏では「エスキューエル」の他に「シーケル」などの発音も存在します。
しかし、国内では「エスキューエル」が広く認知されているため、このように呼ばれることが多いです。
「SQL」という言葉の使い方や例文を解説!
「SQL」という言葉は、特定の文脈で使用されることが多いです。
例えば、プロジェクトでデータベース操作のタスクがある場合に、「SQLを書く」という表現が使われます。
また、「SQLを実行する」「SQLを記述する」「SQLを理解する」といった使い方も一般的です。
これらの表現は、データベースやテーブルの操作に関する作業に対して使われます。
例えば、以下のような文脈で「SQL」が使用されることがあります。
例文:
。
プロジェクトAでは、新しい顧客データの追加機能を実装するために、SQLを書く必要があります。
システムの要件を理解し、適切なSQLを実行することで、データベースのエラーを解決できます。
「SQL」という言葉の成り立ちや由来について解説
「SQL」の成り立ちや由来についてですが、「SQL」は1970年代にIBMのエドガー・コッドとその同僚によって開発されました。
当時のデータベース言語には問題があり、様々なデータベース管理システムが存在していました。
そのため、データベースの共通語として「SQL」が生まれ、標準化されることとなりました。
「SQL」の由来については、「Structured English Query Language」という言葉の略であると言われていますが、後に「Structured Query Language」に変更されました。
そのため、「SQL」という言葉自体は略称であることに注意が必要です。
「SQL」という言葉の歴史
「SQL」の歴史についてご説明します。
1970年代にIBMのエドガー・コッドとその同僚によって開発された「SQL」は、当初はIBMの研究プロジェクトの一環としてスタートしました。
その後、1979年にはアメリカ国立標準技術研究所(NIST)によって標準化が開始され、1986年には標準規格が発表されました。
これにより、「SQL」は市場で広く普及し、他のデータベース管理システムでも採用されるようになりました。
その後も、「SQL」は様々な改訂や拡張が行われ、現在に至っています。
また、標準規格以外の独自の「SQL」実装も存在し、各企業やデータベース管理システムごとに特徴や機能が異なることもあります。
「SQL」という言葉についてまとめ
「SQL」とは、データベース管理システムとのやり取りに使用される標準的な言語です。
データの問い合わせや編集、テーブルの操作などに使用され、プログラマーやシステムエンジニアにとっては重要なツールとなっています。
この言葉は、日本国内では一般的に「エスキューエル」と呼ばれ、データベースの操作に関連する文脈で使われることが多いです。
由来や歴史を知ることで、「SQL」の意味や働きについてもより理解を深めることができます。