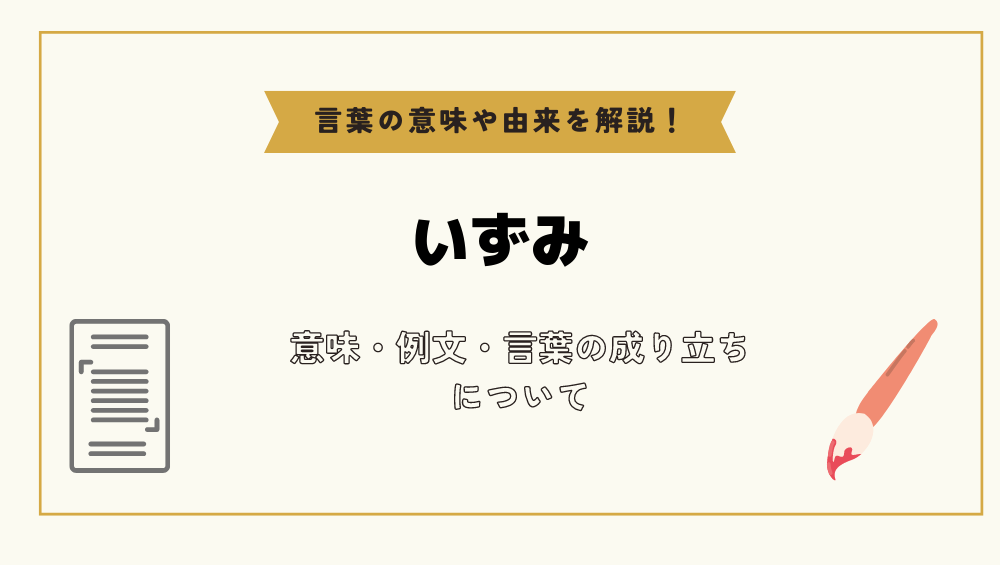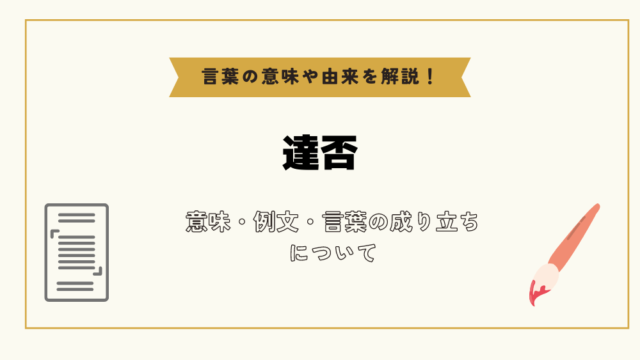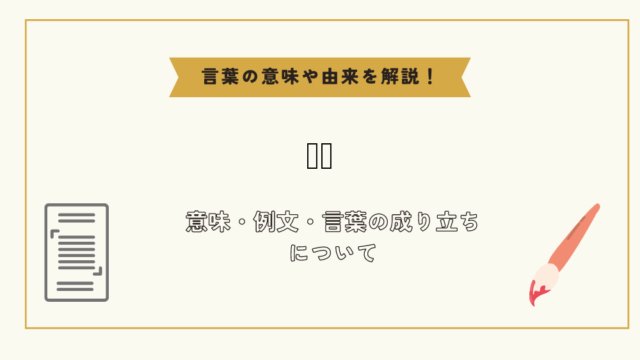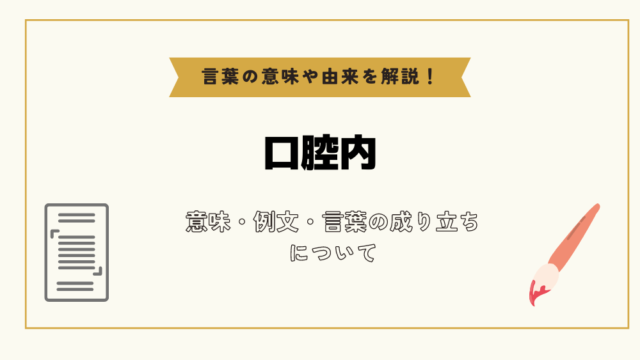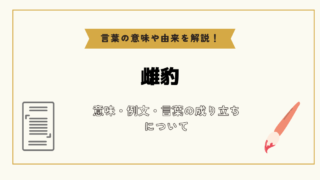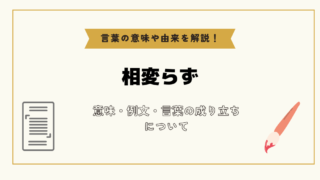Contents
「いずみ」という言葉の意味を解説!
「いずみ」という言葉は、日本語の名詞であり、源を示すと考えられています。
自然の中に存在する水源や泉のことを指し、清らかで澄んだ水が湧き出る場所を意味します。
また、豊かさや恵みの象徴としても用いられることがあります。
水は命の源とも言われるように、人々にとって重要な存在です。
そのため、「いずみ」という言葉には、人々が心安らぐ場所や、新しいエネルギーや希望を得られる場所のイメージも含まれています。
「いずみ」の読み方はなんと読む?
「いずみ」という言葉の読み方は、「いずみ」となります。
漢字の「泉」が当てられているため、そのまま読むことが一般的です。
日本語の音読みとしては、「せん」という読み方も存在しますが、この場合は異なる意味合いを持つことがあります。
例えば「泉」は地下水や湧水を指す場合、音読みの「せん」が使われることが多くなります。
「いずみ」という言葉の使い方や例文を解説!
「いずみ」という言葉は、水源や泉を指す意味合いから、美しい自然の場所や心の安らぐ場所を表す際に使われます。
例えば、「彼女の笑顔は心に癒しのいずみをもたらす」という表現では、彼女の笑顔が心の中に新たなエネルギーや癒しをもたらしてくれる様子を表現しています。
また、「湖の畔に建つ家は、まさに自然のいずみといった佇まい」という文では、湖畔に建つ家が美しい自然に囲まれた場所であることを表現しています。
「いずみ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「いずみ」という言葉は、古くから日本に伝わる言葉です。
「泉」という漢字が使われ、そのまま日本語で読まれています。
日本の風土には豊かな水が存在し、古来から人々の生活に欠かせないものでした。
そのため、自然の水が湧き出る場所を指す「いずみ」という言葉が生まれたのでしょう。
「いずみ」という言葉の歴史
「いずみ」という言葉の歴史は古く、古代の歌や文献にもよく登場します。
日本の歌謡や和歌には、美しい自然や清らかな水を讃える言葉が多く使われてきました。
これらの歌や文献には「いずみ」の言葉が頻繁に登場し、人々の心を豊かにする存在として大切にされてきたことが伝わってきます。
「いずみ」という言葉についてまとめ
「いずみ」という言葉は、水源や泉を指す言葉であり、美しい自然や癒しの場所を表現するのに使われます。
心の中に新たなエネルギーや希望をもたらしてくれる存在としても重要視されています。
また、古代から日本の歌や文献に登場し、人々の心に豊かさをもたらす存在として重要な意味を持ってきた言葉でもあります。
自然の営みや人々の心の安定を表す「いずみ」という存在は、私たちの生活にとって欠かせないものと言えるでしょう。