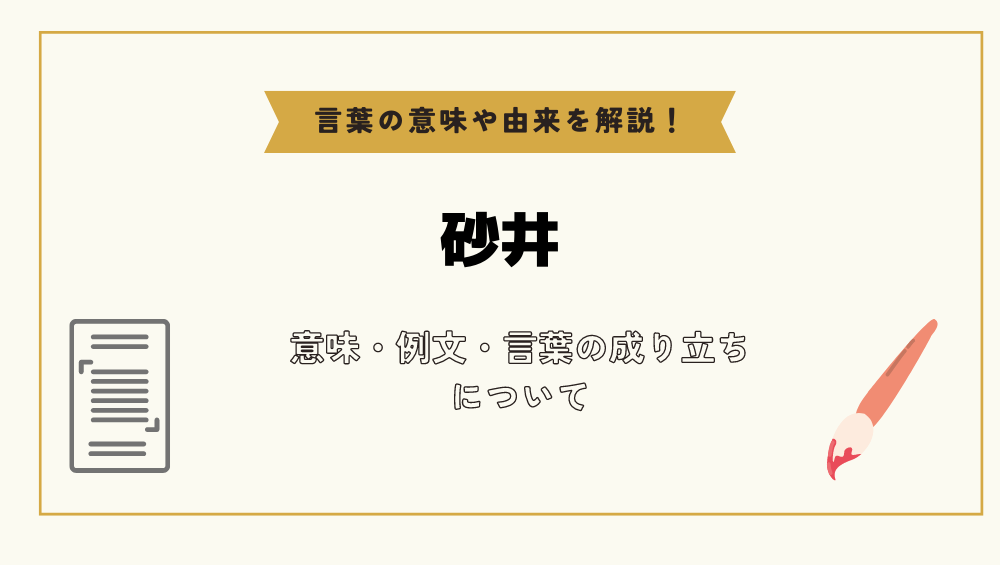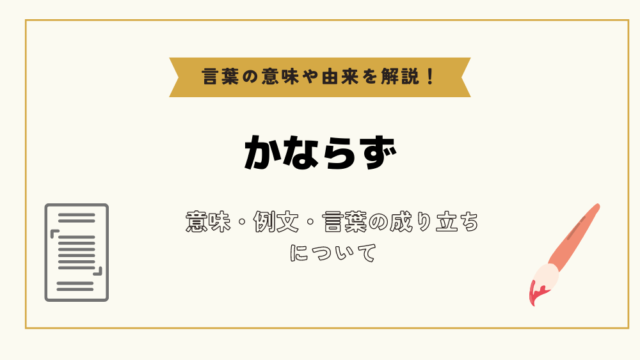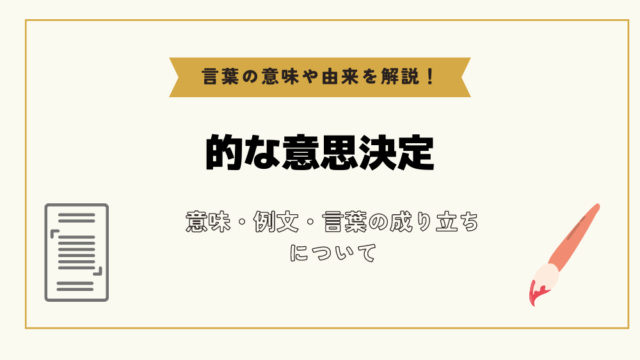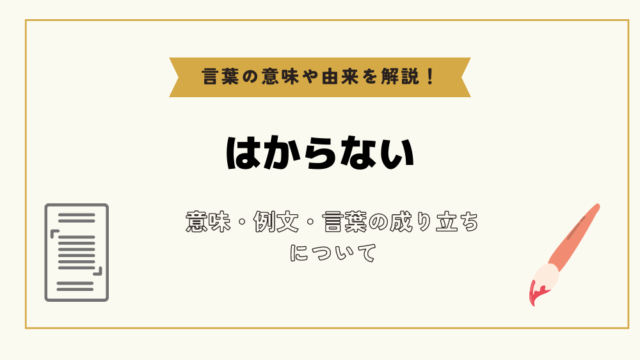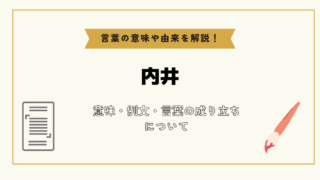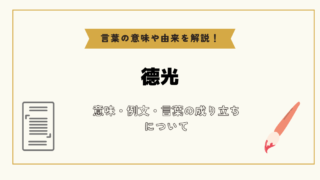Contents
「砂井」という言葉の意味を解説!
「砂井」という言葉は、特定の土地において地下にある砂の水源のことを指します。
砂井は地下の水を供給し、その地域の生活に欠かせない存在です。
砂井は、地面に穴を掘って作られることがあります。
その穴の中に砂や小石が詰められ、その上に土や石が盛られています。
地下には水が溜まり、それが地上に湧き出し、人々の生活に利用されています。
砂井は、古くから農業や生活用水、さらには工業用水としても利用されてきました。
地域によっては、砂井の周辺に集落や町が形成されることもありました。
「砂井」という言葉の読み方はなんと読む?
「砂井」という言葉は、「すない」と読みます。
砂井という漢字表記からも分かる通り、砂がある井戸のことを指しています。
「砂井」という言葉の使い方や例文を解説!
「砂井」という言葉は、特定の地域で地下の水源を指すため、その地の環境や生活に不可欠な単語です。
例えば、農業においては「この地域の作物は砂井の水で育てられている」といったように使います。
また、砂井は生活用水や工業用水としても利用されることがあります。
そのため、例えば「この地では水道が通っていないため、砂井の水を利用しています」といった文脈でも使用されます。
「砂井」という言葉の成り立ちや由来について解説
「砂井」という言葉は、古くからの地下水利用の歴史に由来しています。
日本の農耕文化は、砂井によって支えられてきたと言っても過言ではありません。
砂井は、特定の地域の風土や地下の地層と密接に関わりがあります。
そのため、「砂井」という言葉は地域ごとに異なる特徴や用途が存在していると言えます。
「砂井」という言葉の歴史
「砂井」という言葉の歴史は古く、日本の農耕文化と深く関わっています。
江戸時代には、砂井を利用した田畑が広がり、地域ごとに独自の水利システムが築かれました。
現代でも、砂井は地域の水資源として重要な役割を果たしています。
地下の砂井から湧き出る清水は、多くの人々に恵みをもたらしています。
「砂井」という言葉についてまとめ
「砂井」という言葉は、特定の地域において地下の水源を指す言葉です。
農業や生活用水、工業用水として利用されることがあり、その地の人々にとって欠かせない存在です。
地域ごとに砂井の特徴や使われ方が異なるため、「砂井」という言葉は地方色豊かな単語とも言えます。
その由来や歴史を知ることで、より砂井の重要性や魅力に気づくことができるでしょう。