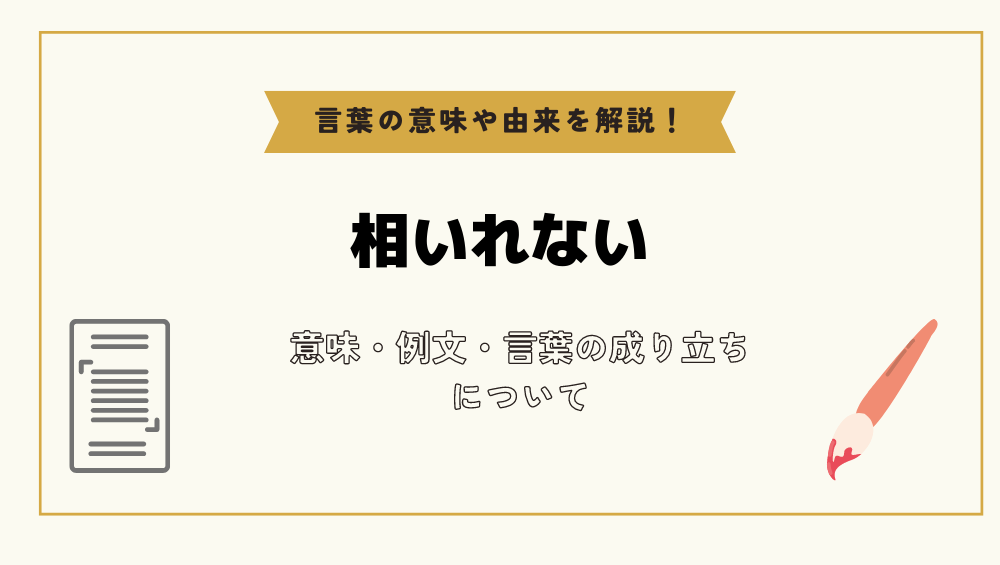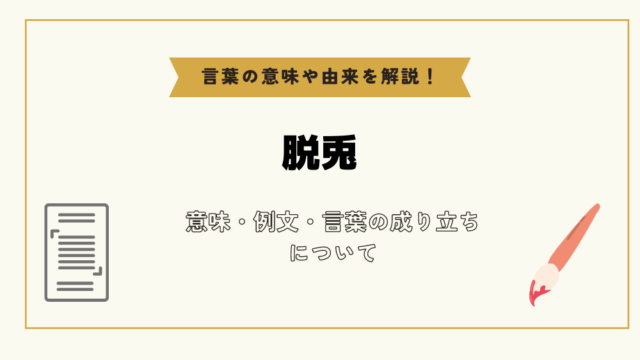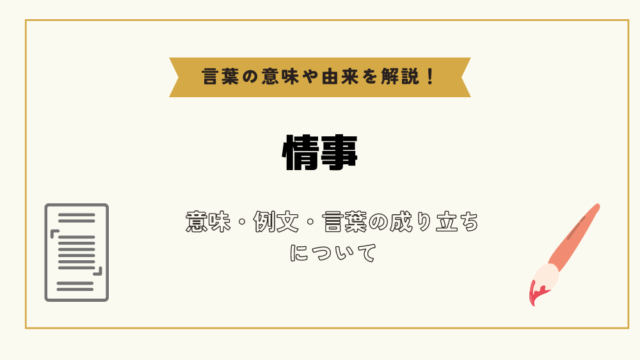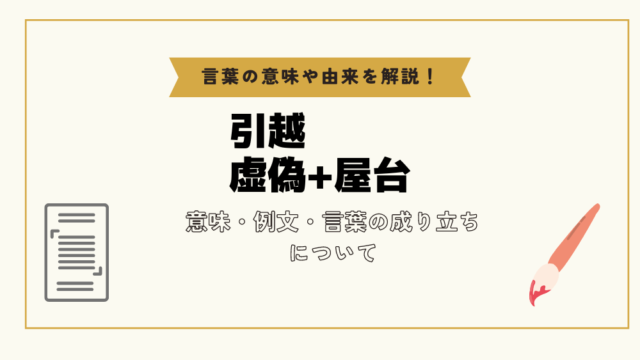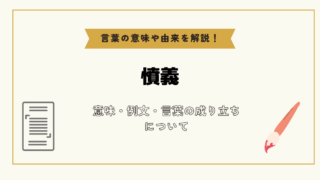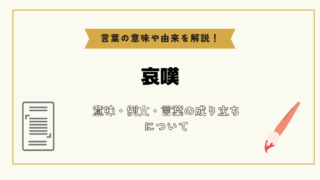Contents
「相いれない」という言葉の意味を解説!
「相いれない」とは、互いに合わないことや調和しないことを意味します。
異なる性格や意見を持った人同士がうまく関わることができず、争いや対立が起こるような状況を示します。
この言葉は、人間関係や団体内の対立など、さまざまな場面で使用されます。
「相いれない」の読み方はなんと読む?
「相いれない」は、「あいれない」と読みます。
このように、語の一部分を切り取って読む「短歌読み」の形式を取っています。
この読み方は、日本の古典文学や歌舞伎などにもよく見られる特徴的な読み方です。
「相いれない」という言葉の使い方や例文を解説!
「相いれない」は、異なる意見や性格の持ち主同士がうまく調和できずに争いが生じる状況を表現する言葉です。
例えば、「彼らは考え方が全く違うので、話し合いが進まず、相いれない状態になってしまった」といったように使います。
この言葉を使うことで、対立や意見の不一致が明確に表現され、相手との関係に問題があることが伝わります。
「相いれない」という言葉の成り立ちや由来について解説
「相いれない」という言葉は、古くから日本語に存在します。
この言葉は、相手との関係が上手くいかないことを表す言葉として、日本の文化や歴史の中で生まれました。
また、この言葉は人間の関係に限らず、自然の中にも見られることがあります。
例えば、動物や植物の種類によっては、共存することが難しく争いが生じることもあります。
「相いれない」という言葉の歴史
「相いれない」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や民間伝承などにも見られます。
この言葉が初めて使用された時期やその経緯は明確ではありませんが、日本人の持つ繊細な感性や、人間関係における葛藤を表現するために用いられたと考えられます。
現代でも「相いれない」という言葉は広く使用されており、人間関係の難しさや調和の重要性を示す言葉となっています。
「相いれない」という言葉についてまとめ
「相いれない」という言葉は、異なる性格や意見を持つ人同士がうまく調和できずに争いが生じる状況を表現します。
この言葉は、人間関係や団体内の対立など、さまざまな場面で使用されます。
読み方は「あいれない」といいます。
この言葉は古くから日本語に存在し、人間の関係に限らず、自然の中にも見られることがあります。
日本の文化や歴史を通じて伝わってきた言葉であり、現代でもよく使われています。