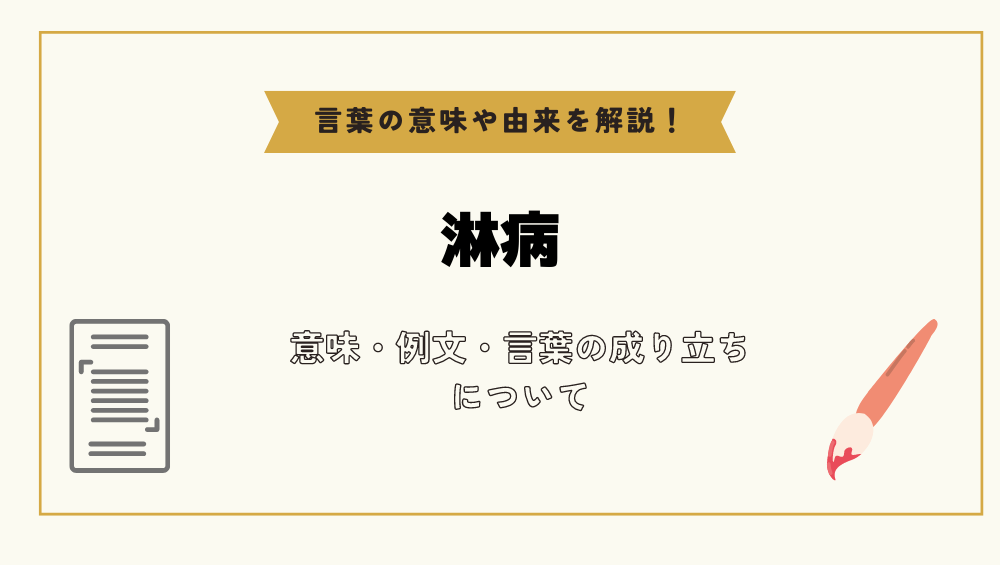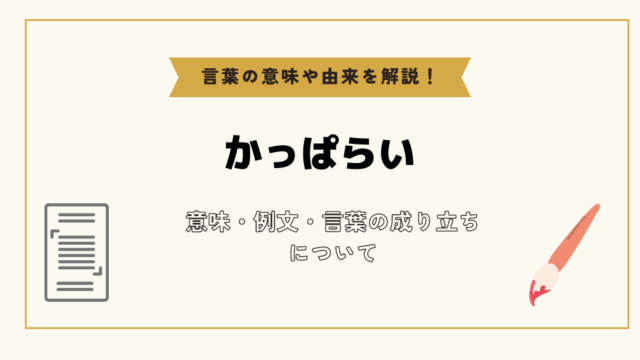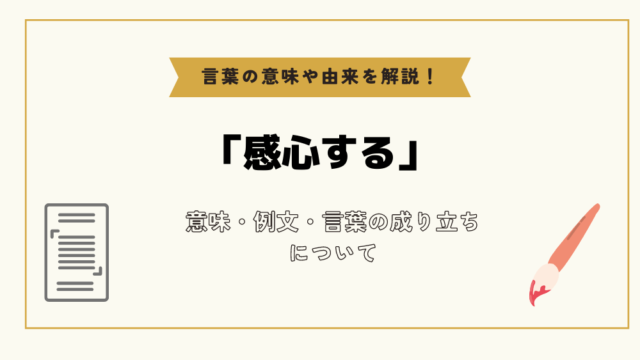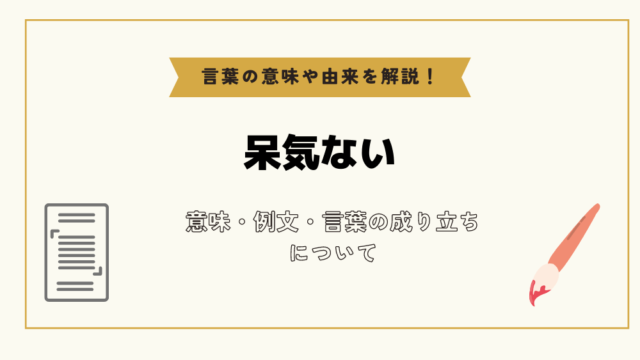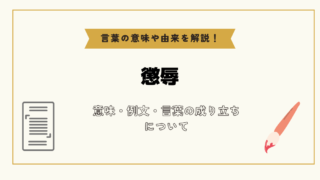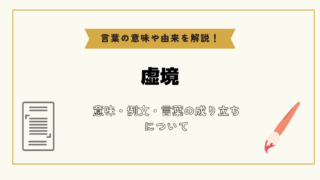Contents
「淋病」という言葉の意味を解説!
「淋病」とは、性感染症の一つであり、主に性行為によって感染する疾患のことを指します。
この病気は、主に尿道や膣に炎症が生じることで特徴付けられます。
淋菌に感染することが原因で、尿道や膀胱などの泌尿器系に炎症を引き起こすのが特徴です。
淋病は感染力が非常に高く、性行為や性器の接触によって感染することが多いため、正しい予防方法と適切な治療が重要です。
感染が疑われる場合は、早めに医師の診察を受けることが必要です。
「淋病」という言葉の読み方はなんと読む?
「淋病」という言葉は、「りんびょう」と読みます。
「淋」は、尿道や膣の炎症を指す言葉であり、「病」は病気を意味します。
日本語の「淋病」という言葉は、中国で発見された病気を指す言葉が起源であり、そのまま日本へと伝わりました。
「淋病」という言葉の使い方や例文を解説!
「淋病」という言葉は、医学的な文脈で使用されることが一般的です。
性感染症の中でも特に尿道や膣の炎症を指すため、医師や保健師などの専門家がこの言葉を使います。
例えば、「淋病に感染してしまったため、早急な治療が必要です」といった風に使われます。
「淋病」という言葉の成り立ちや由来について解説
「淋病」という言葉は、中国の古典医学に由来しています。
元々は、中国で発見された性感染症を指す言葉であり、その後、日本へと伝わりました。
日本では江戸時代になってから広まり、現代に至るまで使用されています。
「淋病」という言葉の歴史
「淋病」という名前が初めて登場したのは、中国の古典医学書である『黄帝内経』です。
この書物によれば、淋菌による尿道や膣の炎症を指す言葉として記載されています。
その後、日本でも江戸時代になってから広まり、現代の医学においてもこの言葉は重要なポジションを占めています。
「淋病」という言葉についてまとめ
「淋病」とは、性感染症の一つであり、尿道や膣の炎症を引き起こす病気です。
この病気は感染力が高く、適切な予防と早期治療が必要です。
読み方は「りんびょう」であり、中国の古典医学に由来しています。
日本でも江戸時代から使われており、現代の医学においても重要な位置づけを持っています。