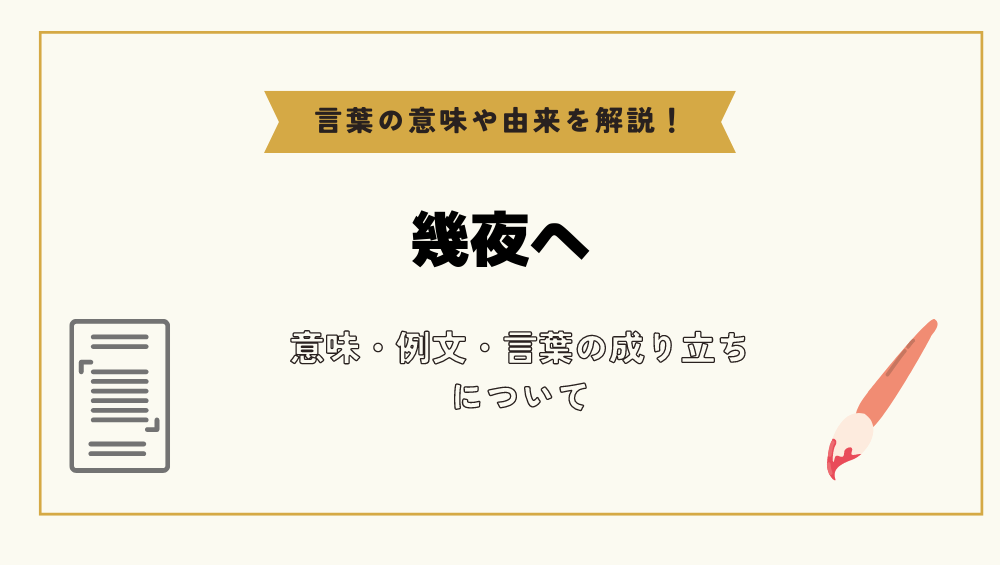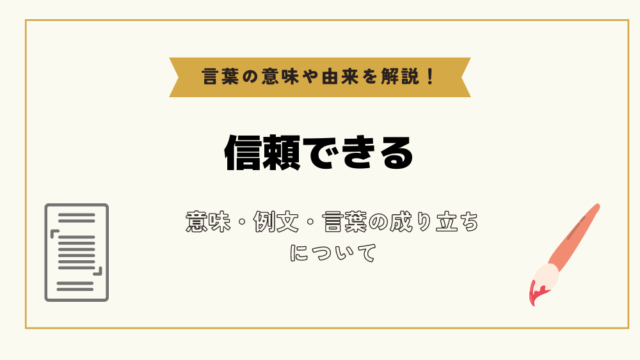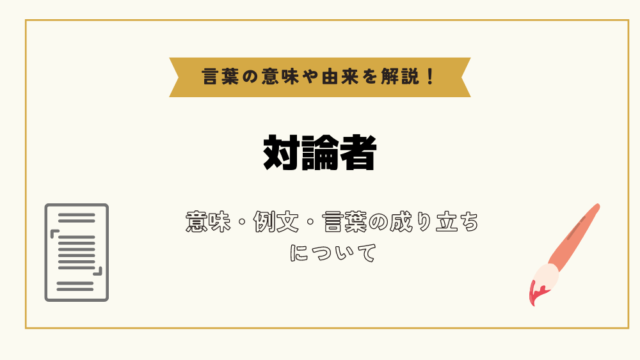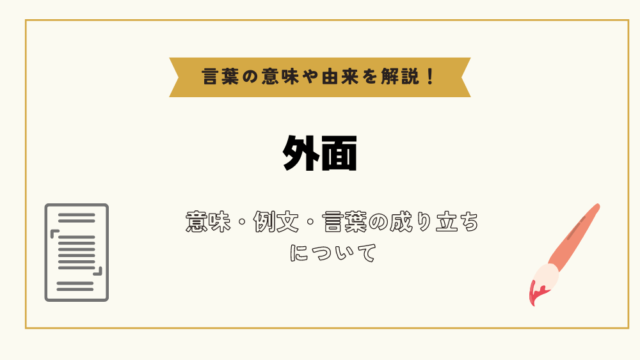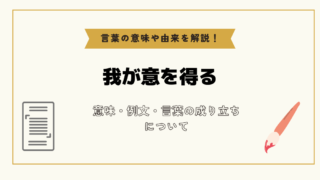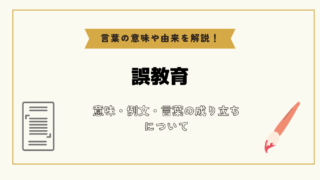Contents
「幾夜へ」という言葉の意味を解説!
「幾夜へ」という言葉は、日本語の古文で使われる表現です。
意味は「何夜に」または「何夜へ」となります。
具体的な夜の数を指定せず、あいまいな表現として使われます。
何かが起こるまでの期間や長い時間が経過する様子を表現したいときに使われることがあります。
「幾夜へ」という言葉の読み方はなんと読む?
「幾夜へ」という言葉は、「いくよへ」と読みます。
古文で使われる表現なので、現代の日常会話ではあまり使われません。
ですが、文学作品や歌などで見かけることがありますので、読み方を知っていると良いでしょう。
「幾夜へ」という言葉の使い方や例文を解説!
「幾夜へ」という言葉は、何かしらの事柄が数日間や何日も続いたり、長い時間が経ったことを表現する際に使われます。
「彼と幾夜へ話し込んだ」や「幾夜へ続く旅の果てに」などのように使います。
この表現を使うことで、時間の経過や出来事の長さを強調することができます。
「幾夜へ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「幾夜へ」という言葉は、古代日本語に由来します。
元々は「幾夜」が使われていましたが、それに「へ」という助詞が付いた形となります。
この助詞「へ」は方向や目的地を表すものであり、時間の経過を指し示す意味も持っています。
そのため、「幾夜へ」という表現が生まれたと考えられます。
「幾夜へ」という言葉の歴史
「幾夜へ」という言葉は、古文学や歌などで頻繁に使用された古い表現です。
古代の人々は、自然や季節の移り変わりなど、時間の概念に敏感でした。
そのため、時間の流れを表現する言葉として「幾夜へ」という表現が使われたのです。
現代の日本語ではあまり使用されなくなりましたが、文学作品などでその響きが生かされることがあります。
「幾夜へ」という言葉についてまとめ
「幾夜へ」という言葉は、古文の中で使われる表現です。
意味は「何夜に」または「何夜へ」となり、特定の日数を示さずに長い期間や時間の経過を表現します。
読み方は「いくよへ」となります。
古代の日本語に由来する表現であり、現代の日常会話ではあまり使用されません。
しかし、文学作品や歌においては見かけることがあります。