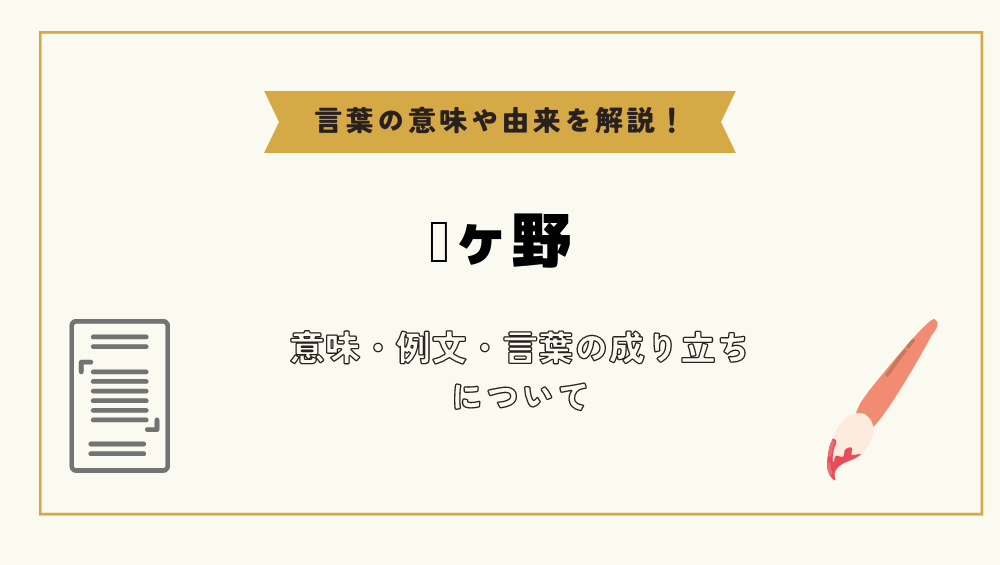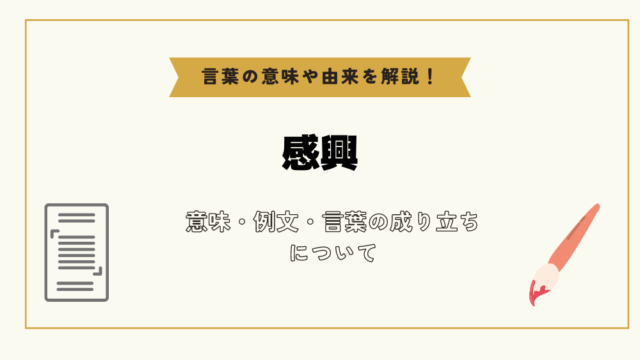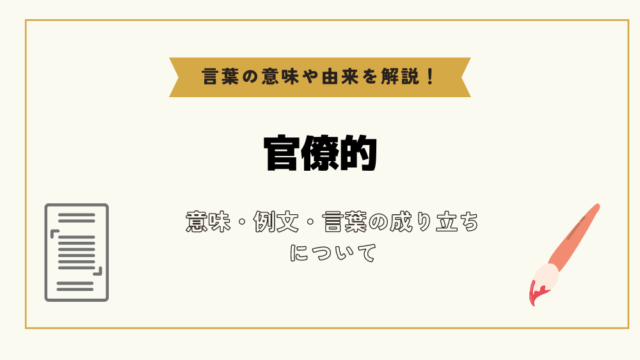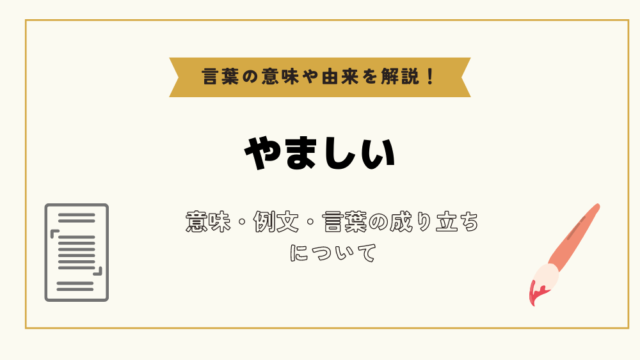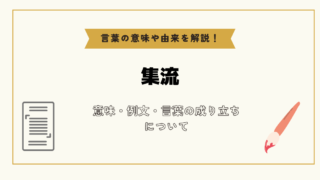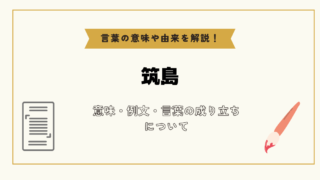Contents
「玅ヶ野」という言葉の意味を解説!
玅ヶ野(かけの)という言葉は、古代日本で使われていた言葉で、「武士や戦士たちが訓練を積む場所」という意味があります。
この場所では、武道や剣術などの修行が行われ、戦闘技術を磨く場として重要な存在でした。
武士たちの鍛錬の場として大切にされていた場所と言えるでしょう。
「玅ヶ野」の読み方はなんと読む?
「玅ヶ野」という言葉は、「かけの」と読みます。
古代日本語や武家の用語として使われたことから、一般的な日本語とは異なる読み方がされています。
「玅ヶ野」という言葉の使い方や例文を解説!
「玅ヶ野」は、古典や歴史資料などで見ることができる言葉です。
例えば、「彼は玅ヶ野で剣の腕を磨いていた」というように、武士や戦士の訓練場所として使われることがあります。
「玅ヶ野」という言葉の成り立ちや由来について解説
「玅ヶ野」は、古代日本の武家や武士の間で使われていた言葉であり、その成り立ちや由来は古代の武道文化に根ざしています。
戦国時代などで活躍した武将たちが、この場所で武術の修行を重ね、技術を磨いていたと言われています。
「玅ヶ野」という言葉の歴史
「玅ヶ野」という言葉は、古代から中世にかけて武家や武士たちの間で広く使われていました。
武士道や武道の精神を形成する際に、この場所が大きな役割を果たしてきた歴史があります。
「玅ヶ野」という言葉についてまとめ
「玅ヶ野」という言葉は、古代日本の武家文化における重要な場所や概念を表す言葉です。
武士や戦士の鍛錬の場として、武道の修行を行う場所として、その存在が歴史的な意義を持っています。
武士道の精神や武道の伝統を受け継ぐ上で、重要な言葉として今日でも語り継がれています。