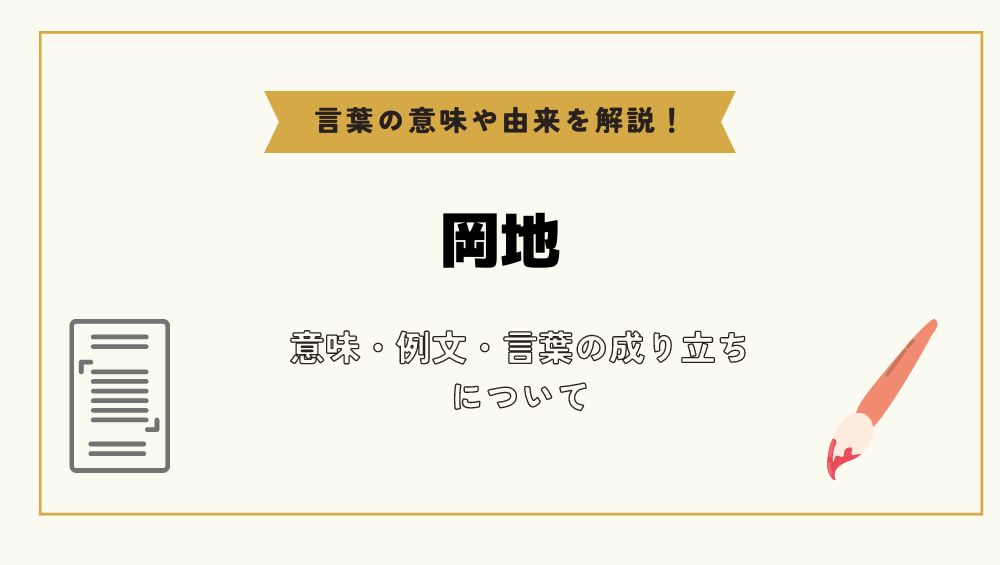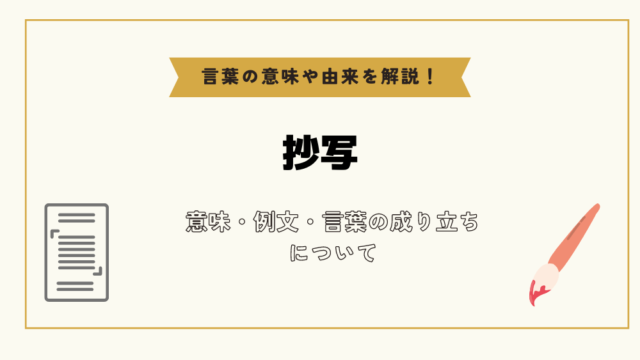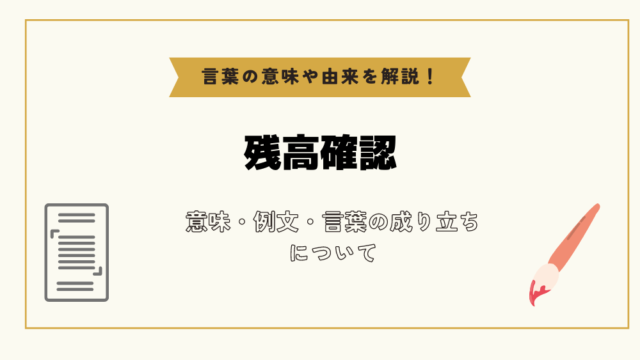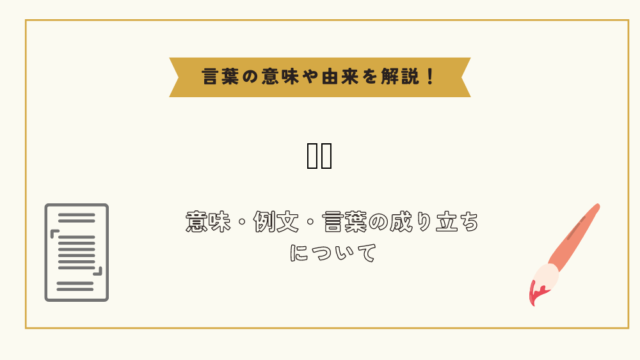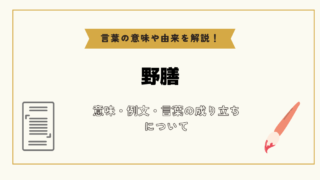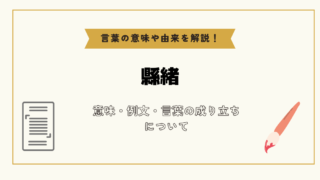Contents
「岡地」という言葉の意味を解説!
「岡地」という言葉は、山や丘の上に広がる平坦な地形を指す言葉です。
つまり、山や丘の斜面を切り開いて作られた畑や田んぼなどの耕地を指すことが多いです。
自然の地形を利用して、農作物を栽培するために整備された場所として「岡地」という言葉が使われています。
山間部や地域によっては、このような「岡地」が景観の一部として観光地となっていることもあります。
「岡地」の読み方はなんと読む?
「岡地」という言葉は、読み方を「おかち」とします。
つまり、「おか」と「ち」という音で読みます。
この読み方は、日本語の基本的な読み方に則しており、誰もが理解しやすい表記となっています。
「岡地」という言葉が使われる際には、正しい読み方で使うことが大切です。
「岡地」という言葉の使い方や例文を解説!
「岡地」という言葉を使った例文をご紹介します。
例えば、「この町は岡地が多く、農業が盛んです」というように使われることがあります。
「岡地」は地域の特徴や景観を表すために、自然の風景に関連した言葉として使われることが多いです。
「岡地」という言葉の成り立ちや由来について解説
「岡地」という言葉は、古くから日本の地域で使われてきた言葉です。
「岡」という文字は、山や丘を表す漢字であり、「地」は地面や土地を意味します。
それらを組み合わせることで、山や丘の土地という意味が含まれる「岡地」という言葉が生まれたと考えられています。
「岡地」という言葉の歴史
「岡地」という言葉は、日本の農耕文化が根付く古代から存在していたと言われています。
山や丘の斜面を利用して作られた畑や田んぼなどは、重要な農地として扱われてきました。
「岡地」は、日本の農業の歴史や地域の風土を表す重要な言葉として、今も使われ続けています。
「岡地」という言葉についてまとめ
「岡地」という言葉は、山や丘の上に広がる平坦な地形を指す言葉であり、農作物を栽培するための耕地として利用されています。
読み方は「おかち」とし、地域の特徴や景観を表す際に使われることが多い言葉です。
古代から日本の農耕文化に根付く言葉であり、今も地域の風土や歴史を感じさせる重要な言葉として使われ続けています。