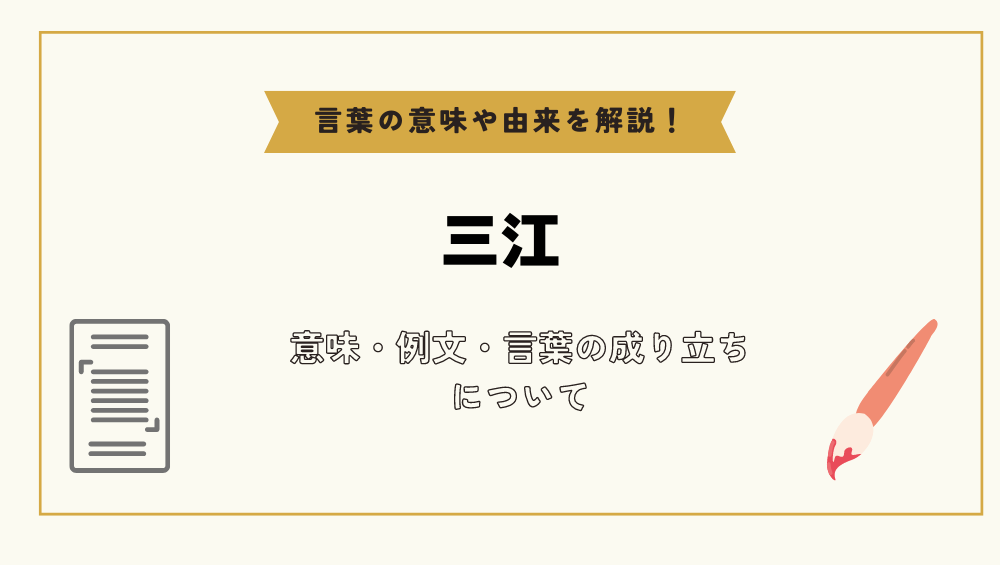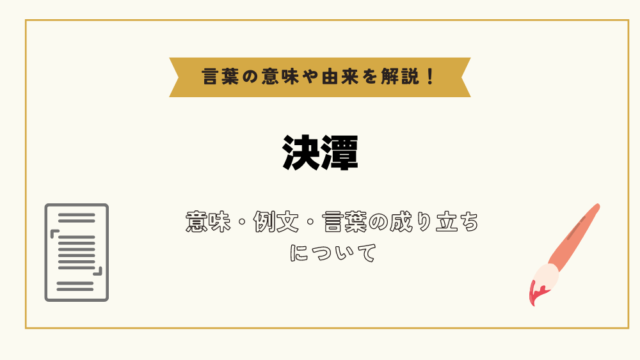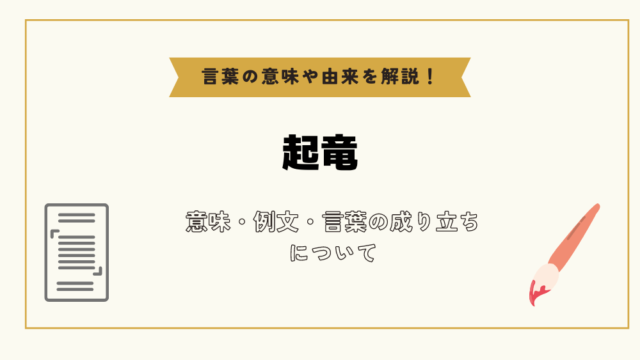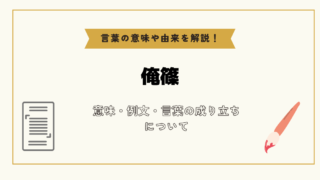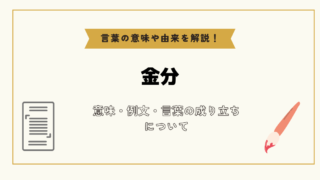Contents
「三江」という言葉の意味を解説!
「三江」とは、3つの川が合流する地域を指す言葉です。
川の流れが交わる点で、水の流れが豊かになる場所を示しています。
三つの川が一つになるという象徴的な意味合いも持っています。
川が合流する地点を指す「三江」という言葉は、水の恵みと豊かさを象徴しています。
。
「三江」という言葉の読み方はなんと読む?
「三江」の読み方は、「さんこう」と読みます。
3つの川が交わる場所という意味があります。
日本語の発音で覚えておくと、スムーズに使いこなせるでしょう。
「三江」という言葉は、しっかりと「さんこう」と読むのが正しい読み方です。
。
「三江」という言葉の使い方や例文を解説!
「三江」の使い方は、地域の地名として用いられることが多いです。
また、3つの要素が合流する場合や、3つの概念が一つにまとまる状況を表現する際にも使われます。
例えば、「三江地域で開催されるイベントに参加しました」というように使うことができます。
。
「三江」という言葉の成り立ちや由来について解説
「三江」という言葉は、古くから日本の地名として使われてきました。
3つの川が交わる景色は美しく、人々の目に留まりやすかったことが由来とされています。
この言葉は、自然の美しさや豊かさを表現する際に用いられてきた歴史があります。
。
「三江」という言葉の歴史
「三江」という言葉は、令和時代を迎えてもなお日本の風土として残されています。
古代から続く言葉であり、日本人の自然への敬意や感謝の気持ちを表現するために用いられています。
歴史ある「三江」という言葉は、日本文化の一部として根付いています。
。
「三江」という言葉についてまとめ
「三江」という言葉は、3つの川が合流する場所を指す言葉であり、水の恵みや豊かさを象徴しています。
日本の地名や自然の美しさを表現する際に使われ、古代から続く歴史があります。
「三江」という言葉は、自然と人々の繋がりや豊かさを感じさせる言葉として、日本の風土に根付いています。
。