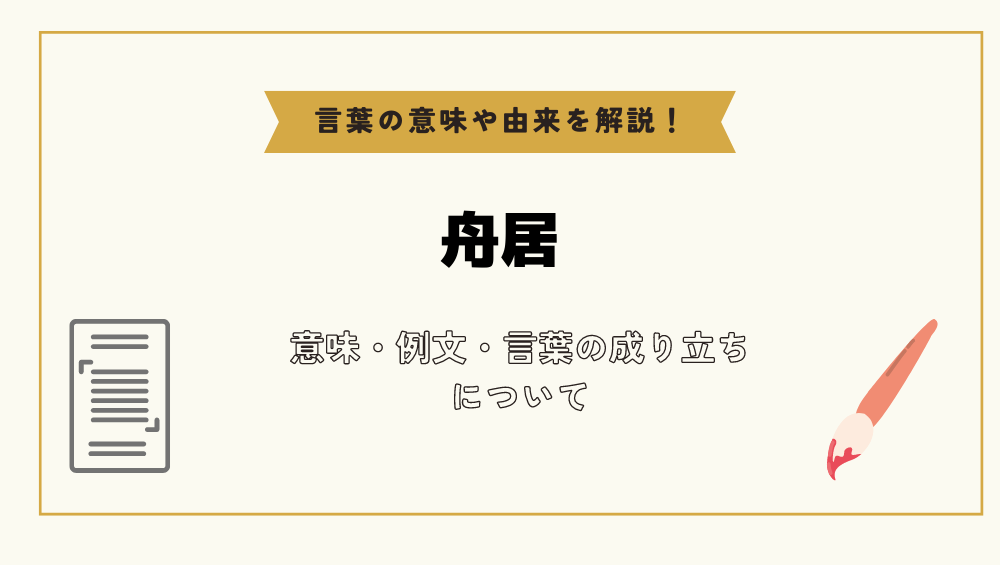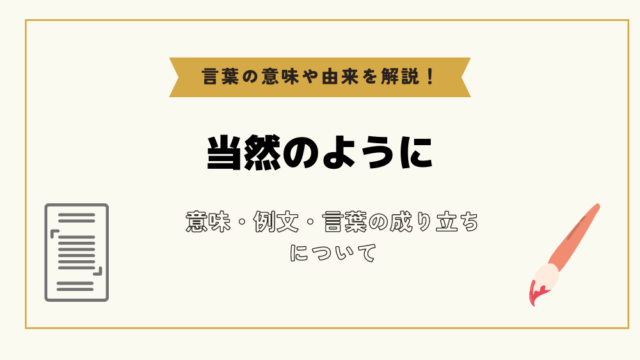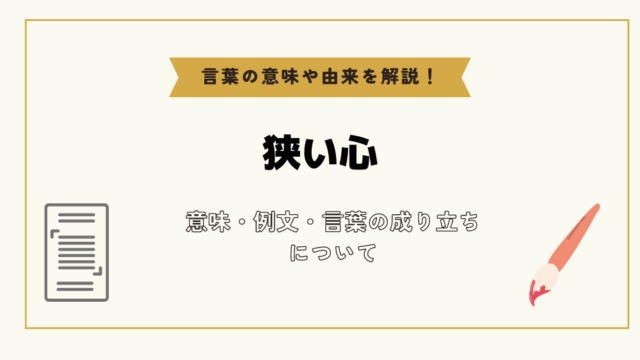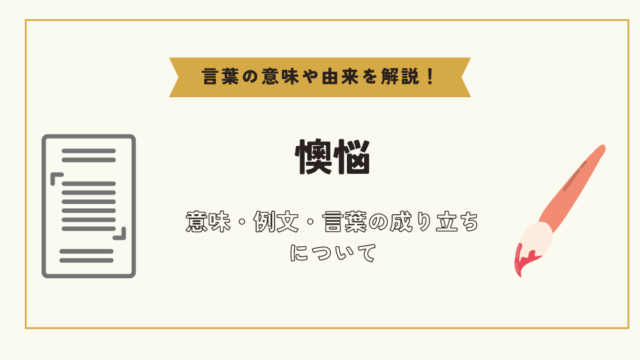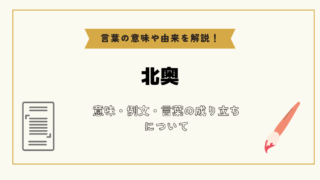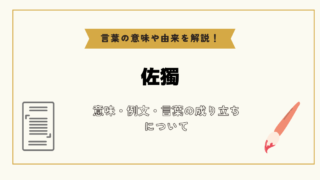Contents
「舟居」という言葉の意味を解説!
「舟居」という言葉は、舟に乗って泊まることを指す言葉です。
古来から船が交通手段として重要だった時代、舟居は旅の一環として欠かせないものでした。
今でも観光地などで舟居ができる場所が残っています。
舟居は、船に泊まることを楽しむ贅沢な体験です。
。
「舟居」の読み方はなんと読む?
「舟居」は、「ふない」と読みます。
舟の「ふね」と泊まる「い」が合わさった言葉です。
日本語の美しい響きが感じられる言葉ですね。
「舟居」という言葉は、舟に泊まるという意味を持っています。
。
「舟居」という言葉の使い方や例文を解説!
「舟居」は、例えば「湖畔で舟居を楽しむ」という風に使われます。
舟居ができる場所や手配方法など、舟居に関する情報が含まれる文脈で使われることが多いです。
「舟居」は、舟に泊まることを指す言葉として使われます。
。
「舟居」という言葉の成り立ちや由来について解説
「舟居」という言葉は、古代から舟を使った交通や旅行が盛んだったことから生まれた言葉です。
舟が生活に欠かせない存在だった時代、舟での宿泊が「舟居」と呼ばれるようになりました。
「舟居」という言葉の由来は、舟を使った旅行の習慣にあります。
。
「舟居」という言葉の歴史
「舟居」という言葉は、古代から日本の風土や文化に根付いてきました。
舟での旅行が一般的だった時代には、舟居も一般的な行為でした。
現代でも、観光地などで舟居が体験できる場所が残っています。
「舟居」は、古代から日本の文化に深く根付いた歴史があります。
。
「舟居」という言葉についてまとめ
「舟居」は、舟に泊まることを指す言葉であり、古代から日本の風土や文化に根付いた言葉です。
観光地などで舟居ができる場所が残っているため、舟居を通じて古き良き日本の風情を感じることができます。
「舟居」という言葉は、舟に泊まる古来からの風習として、今も続いています。
舟居を楽しんで、古代の風情を感じてみてはいかがでしょうか。