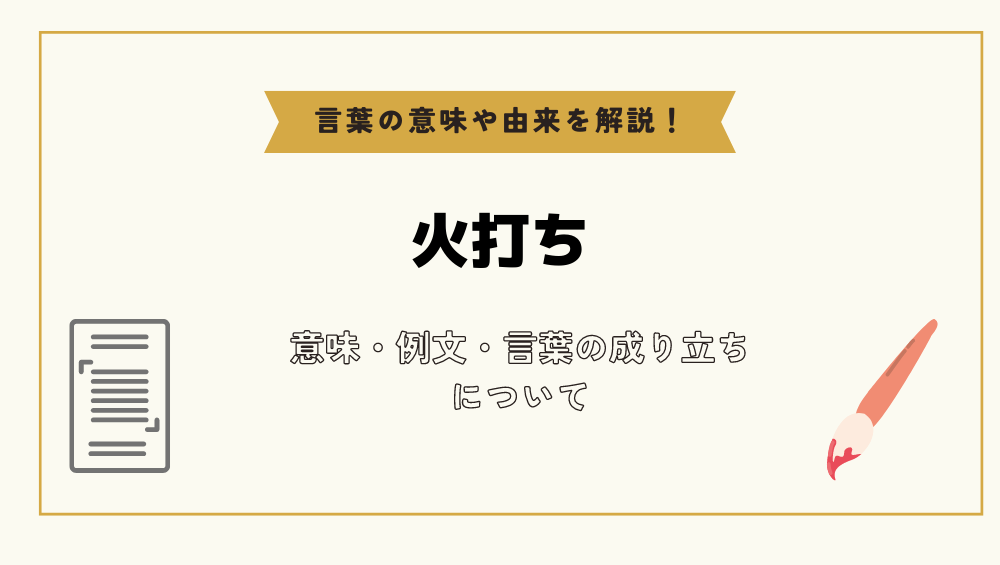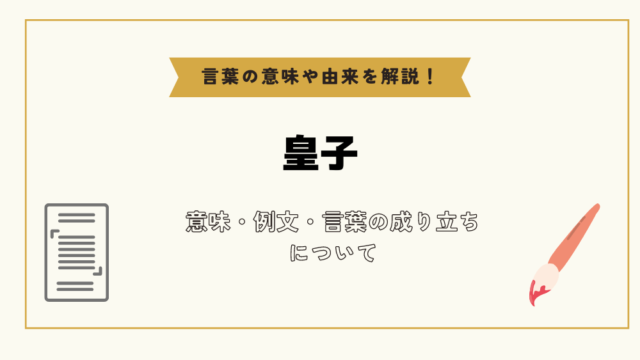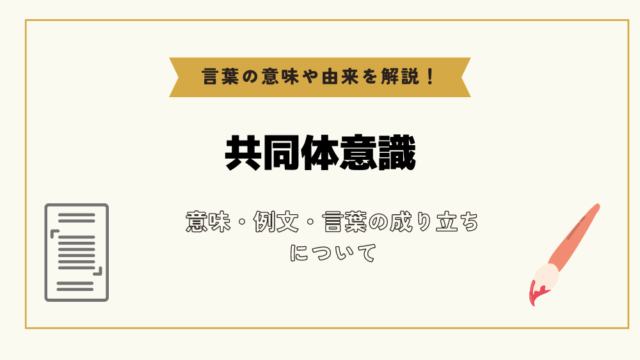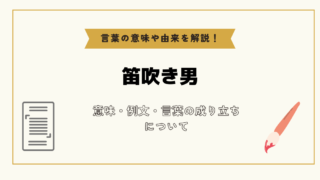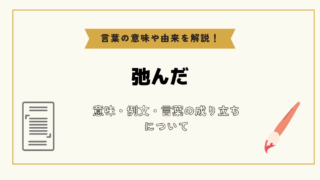Contents
「火打ち」という言葉の意味を解説!
火打ちとは、火を打つことで火をつけることを指します。
古くから火は人類にとって生活に欠かせないものであり、火打ちができることはとても重要な技術でした。
火打ちの方法は時代とともに進化してきましたが、その意味は今もなお大切にされています。
「火打ち」の読み方はなんと読む?
「火打ち」は「ひうち」と読みます。
日本語の中には、漢字の音読みと訓読みがありますが、「火打ち」は訓読みになります。
漢字の意味を考えながら正しく読み方を覚えると理解が深まること間違いありません。
「火打ち」という言葉の使い方や例文を解説!
「火打ち」は主に、火を打つことに関連する言葉として使われます。
例えば、「山で火を打ったら、火がつかなかった」というように、火打ちの技術が必要な場面で使われることがあります。
身近な日常生活でも、火打ちの技術は意外と役立つこともあるかもしれませんね。
「火打ち」という言葉の成り立ちや由来について解説
「火打ち」という言葉は、古代から日本の暮らしに深く関わる技術として存在してきました。
火打ちは、石や鉄などの材料を使っており、その技術は古い時代から伝わるものです。
そのため、日本の歴史とともに「火打ち」の技術や言葉も変化してきたと言えるでしょう。
「火打ち」という言葉の歴史
「火打ち」の歴史は古代から続いており、火をつける技術として重要視されてきました。
縄文時代や弥生時代には、石で火を打ち起こす技術が使われていました。
江戸時代に入ると、鉄や火打ち石を使用した火打ち道具が登場し、火の取り扱いがより安全になっていきました。
「火打ち」という言葉についてまとめ
「火打ち」という言葉は、古くから日本の文化や歴史と深く結びついています。
火をつけるという基本的な技術の一つであり、今もなおその重要性は失われていません。
日常生活でも火打ちの技術が役立つことがあるかもしれませんので、ぜひ身近な場面で活用してみてくださいね。