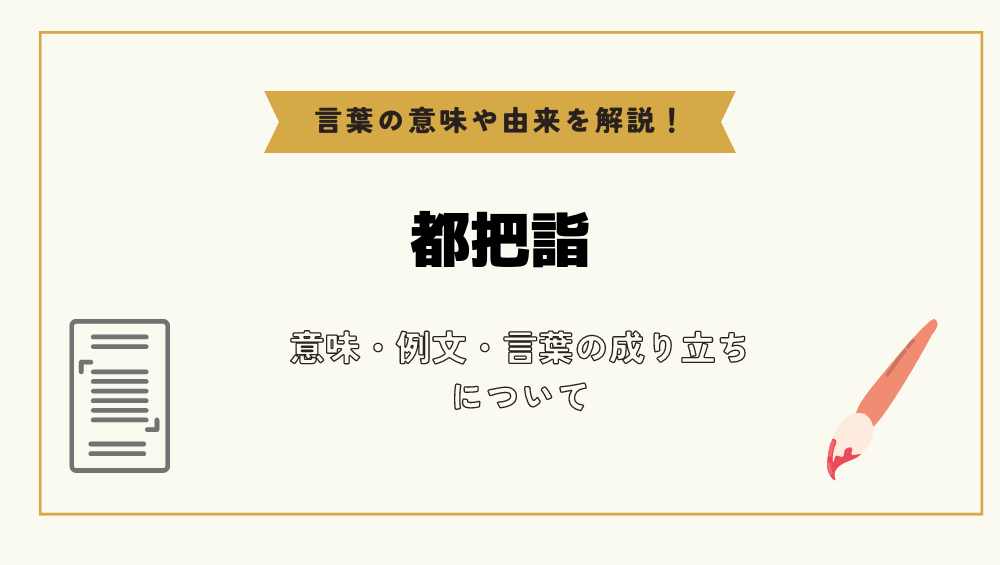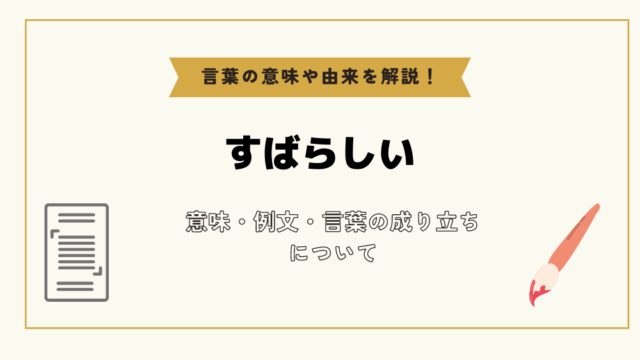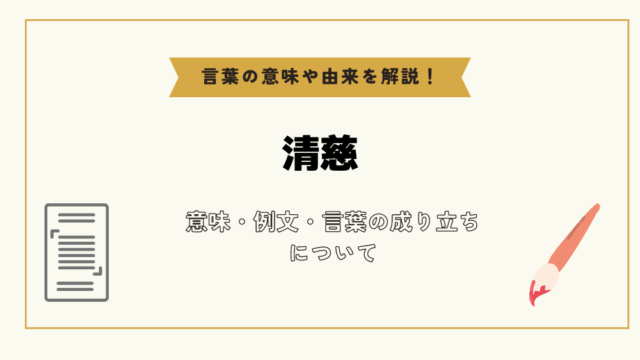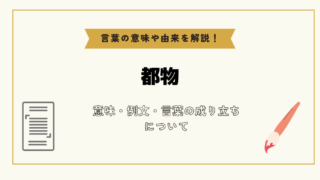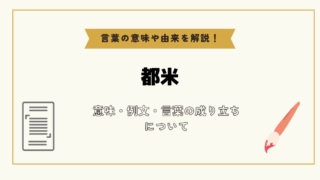Contents
「都把詣」という言葉の意味を解説!
「都把詣」という言葉は、気持ちや思いを改めて、都会や人混みから離れ、穏やかな場所に身を置くことを指します。
日常の煩わしさやストレスから離れ、心を落ち着かせるために、静かな自然の中でリフレッシュすることが大切です。
ストレス社会の中で、心の健康を保つためにも、「都把詣」を実践してみましょう!。
「都把詣」の読み方はなんと読む?
「都把詣」は、「つばさり」と読みます。
この言葉は、昔から日本の文学や詩歌に登場する言葉であり、日本人にとって心を落ち着かせ、自然と調和する大切な行為として親しまれています。
「都把詣」という言葉の使い方や例文を解説!
「都把詣」は、例えば「週末には山中に都把詣をする」という風に使われます。
自然が豊かな場所や静かな神社などへ足を運び、日常の喧騒から離れてリラックスすることが大切です。
「都把詣」という言葉の成り立ちや由来について解説
「都把詣」という言葉は、昔から日本の神道や文学に深く根付いています。
都会の喧騒から離れ、清浄な場所で神仏に祈りを捧げるという行為は、心を洗い清める効果があるとされています。
「都把詣」という言葉の歴史
「都把詣」の歴史は、奈良時代や平安時代から遡ることができます。
日本人の心の安定や内面の成長を目指すために、古くから「都把詣」が行われてきました。
「都把詣」という言葉についてまとめ
「都把詣」は、日本固有の概念であり、現代のストレス社会においても重要な意味を持っています。
自然の中で心を静めることで、心身のバランスを整えることができるため、積極的に取り入れていきたい言葉です。
都会の喧騒から離れ、自分と自然との調和を大切にしていきましょう。
。