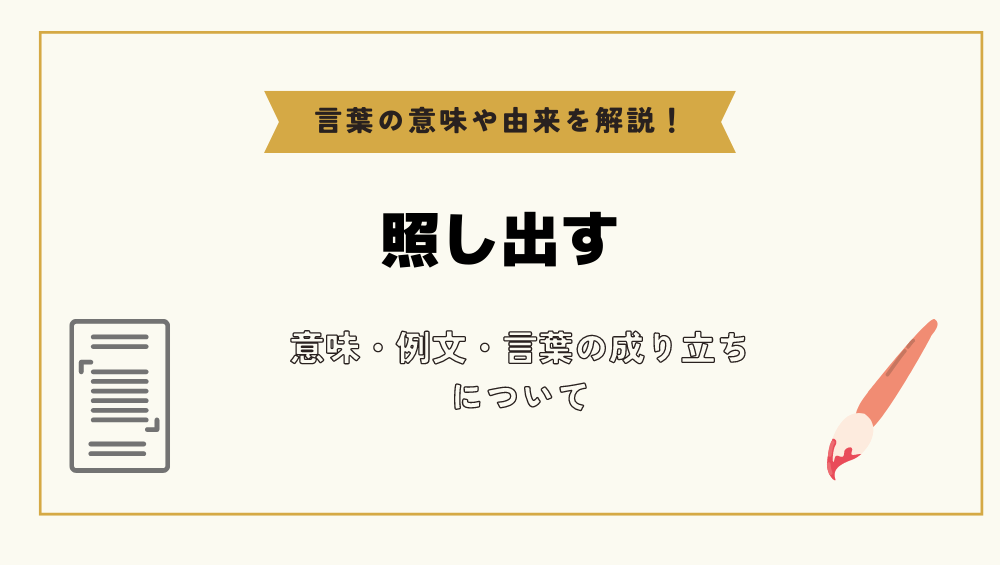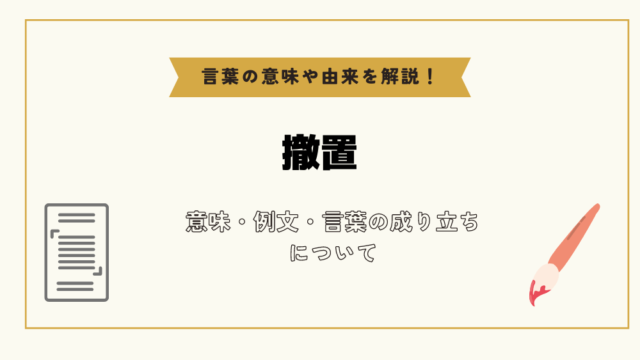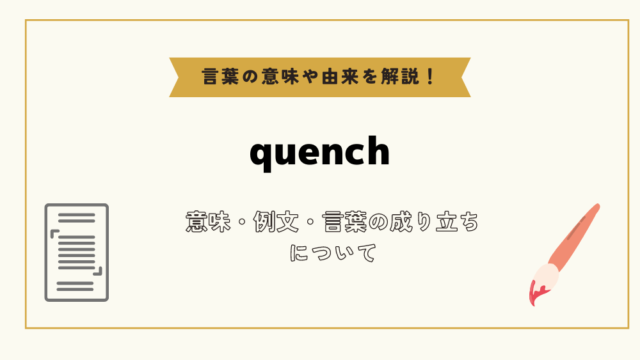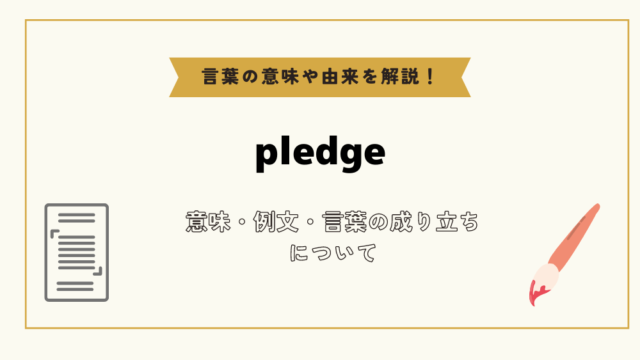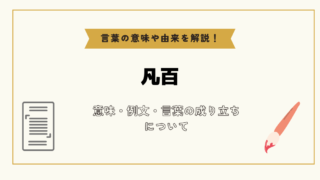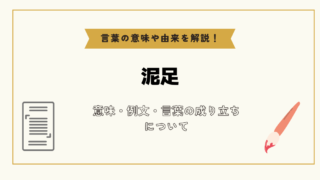Contents
「照し出す」という言葉の意味を解説!
「照し出す」とは、何かが光や熱などを放射して外部に向けて明るさや温かさを示すことを意味します。日光や明かりが強く当たり、その対象が光や熱を放射する様子を表現する言葉です。人や物事がより輝いたり、目立ったりする様子も「照し出す」と表現されることがあります。
光を放射して輝きを示すという意味合いが強く、様々な場面で用いられる表現です。
「照し出す」という言葉の読み方はなんと読む?
「照し出す」という言葉は、「てりだす」と読みます。漢字の「照」は『光をあてる』、『光を当てる』といった意味があり、「出」は『外部に示す』、『透き通って見える』といった意味があります。つまり、「てりだす」は外部に向けて光を放射して輝きを示すという意味となります。
「照し出す」という言葉の使い方や例文を解説!
「太陽が窓から差し込み、庭に花々が輝きを照し出していた」、「彼女の笑顔が部屋に輝きを照し出した」など、「照し出す」という言葉は、光や輝きを放射して魅力を示す様子を表現する際に活用されます。その明るさや温かさが周囲に満ちる様子を描写する際に使われることが多いです。
「照し出す」という言葉の成り立ちや由来について解説
「照し出す」の成り立ちや由来については、漢字の「照」と「出」からなる言葉であり、古代から伝わる言葉とされています。光や熱を外部に向けて示すという基本的な意味合いから派生し、人や物事の魅力や輝きを表現する際に用いられるようになったと考えられています。
「照し出す」という言葉の歴史
「照し出す」という言葉は、古代より日常会話や文学作品などで使われてきました。日本の古代文学や漢詩にも「照し出す」の表現が登場し、光や輝きを放射する様子を描写する際に重要な言葉として広く認知されてきました。
「照し出す」という言葉についてまとめ
「照し出す」という言葉は、光や輝きを放射して周囲に魅力や温かさを示す様子を描写する際に用いられます。その成り立ちや由来は古代から続く言葉であり、日本の文学や日常会話など様々な場面で使用されてきました。明るさや輝きを表現する際に、ぜひ「照し出す」という言葉を活用してみてください。